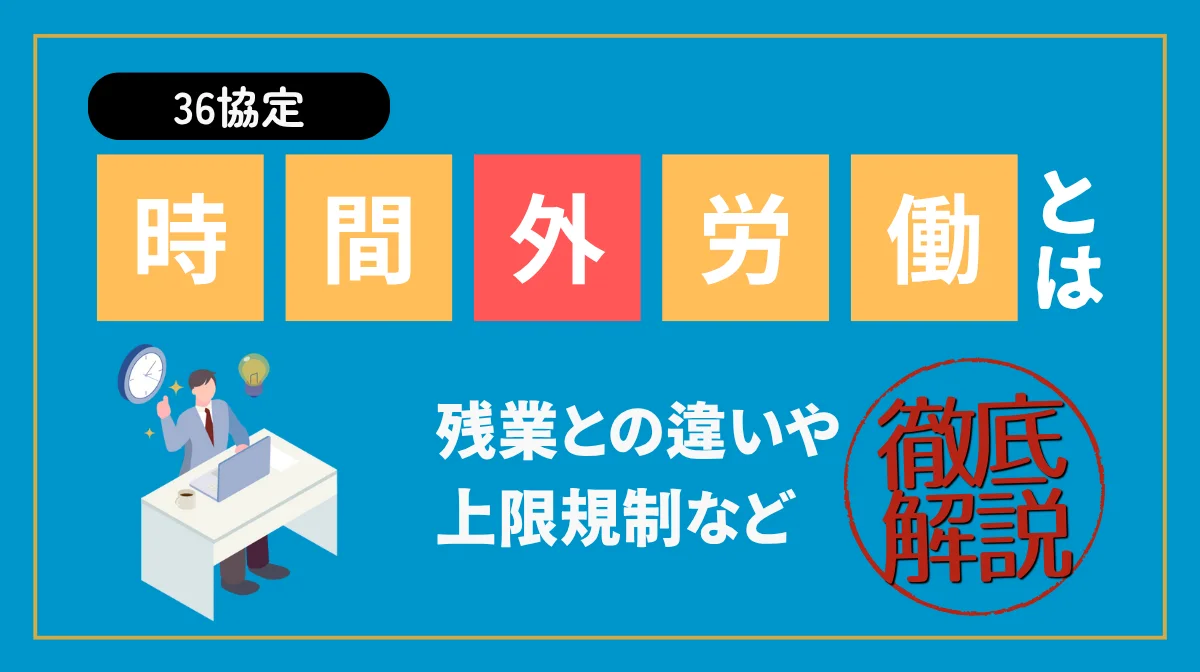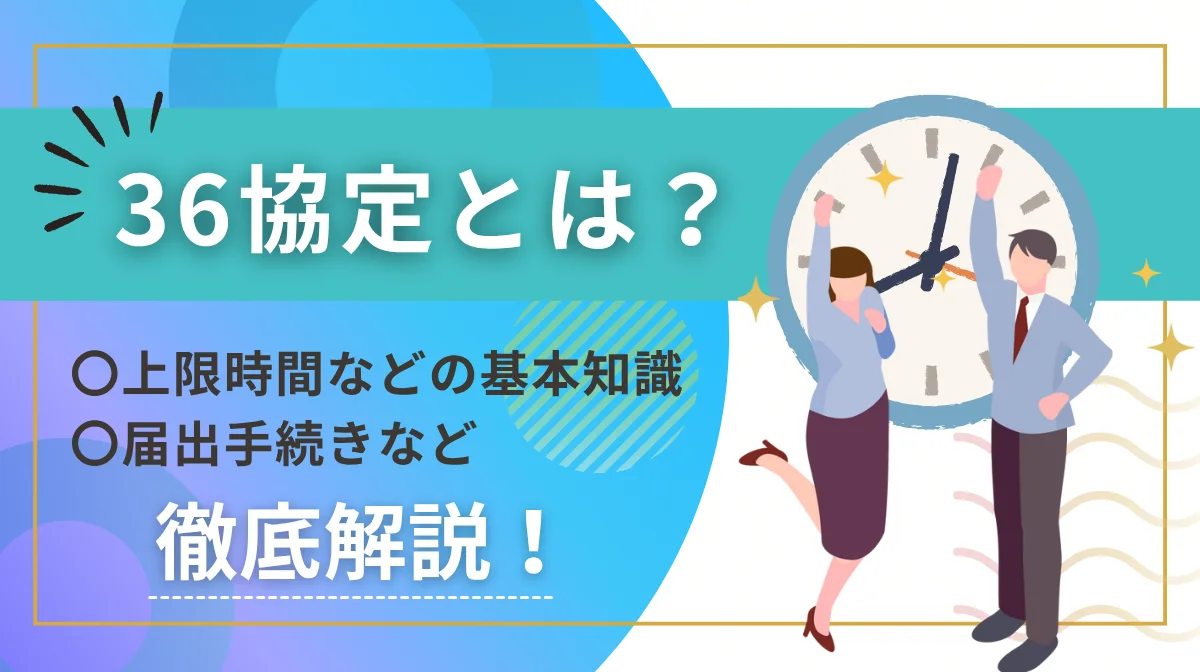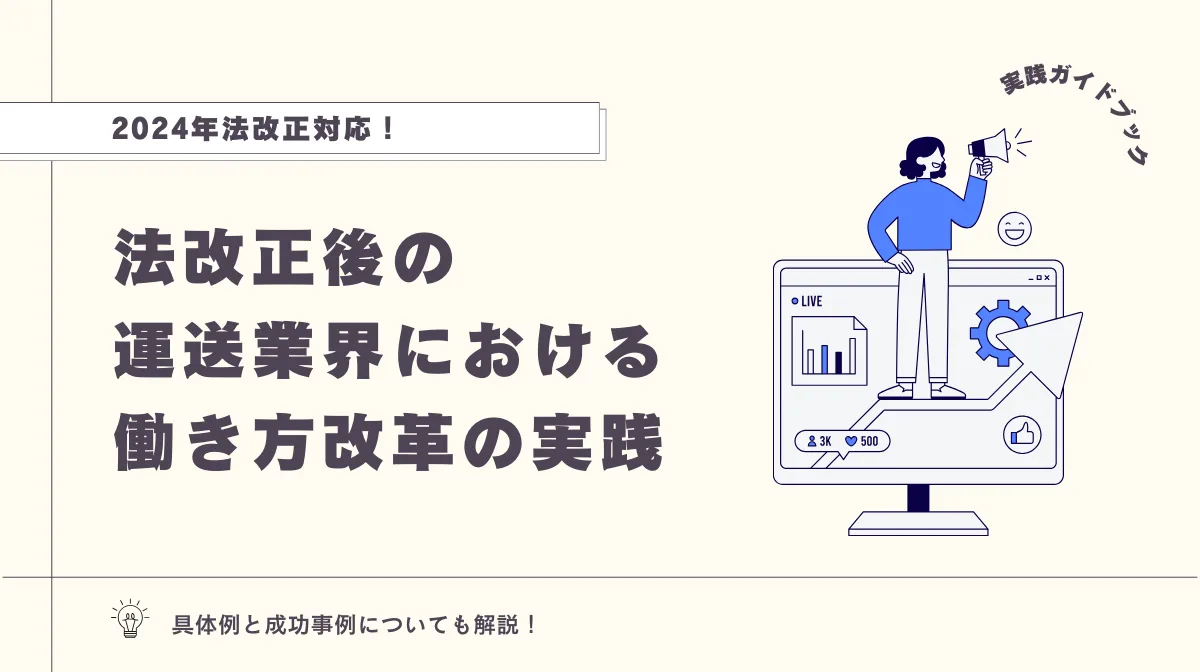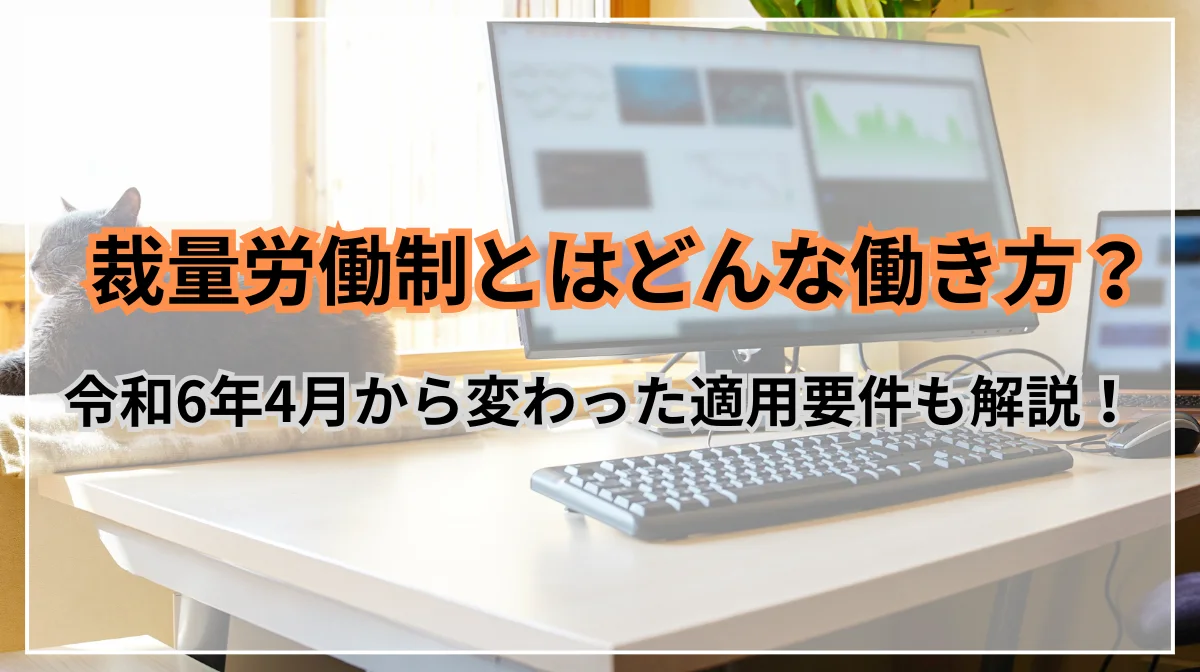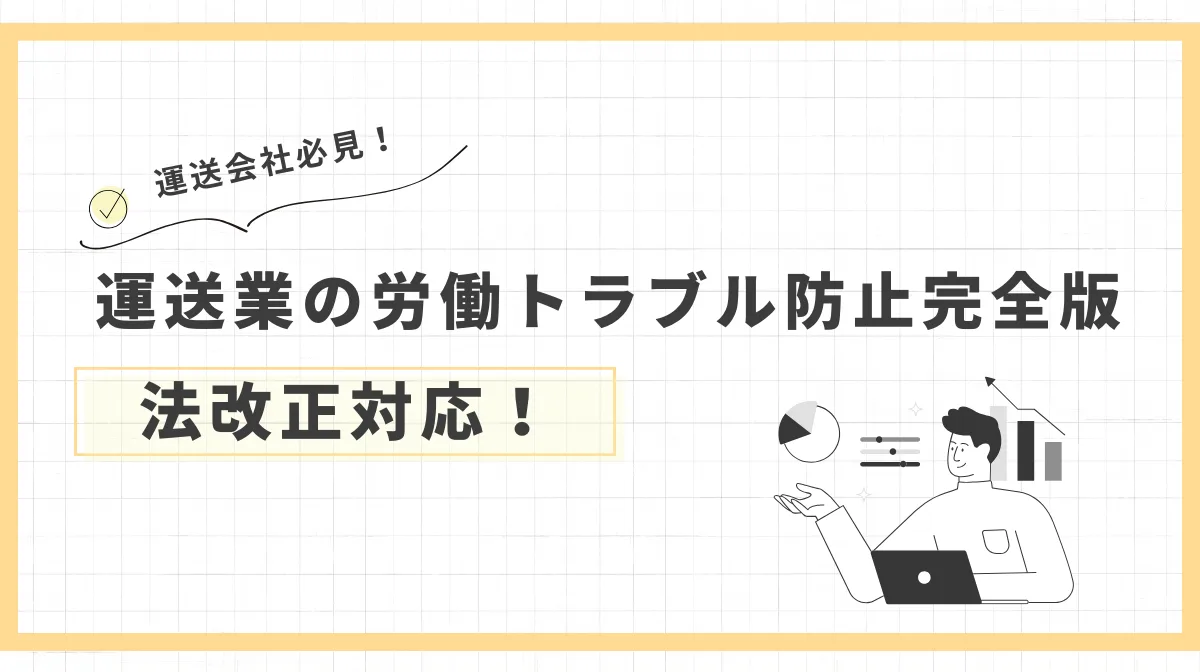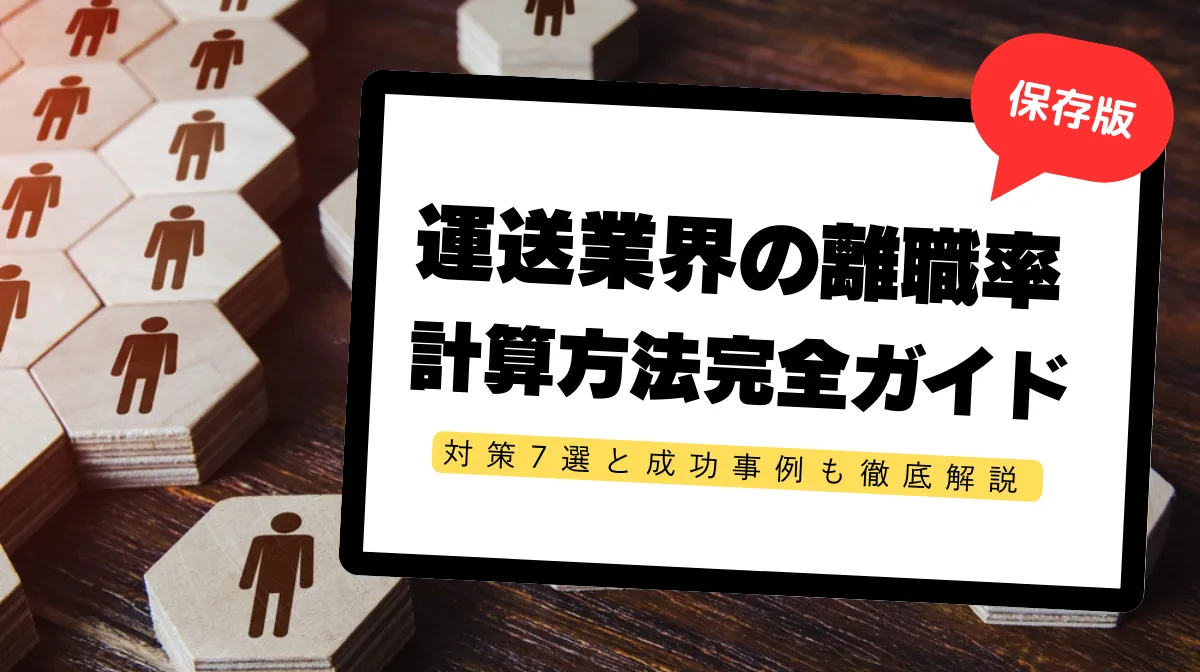時間外労働は、企業の人事・総務担当者が特に注意すべき労務管理の一つです。法定労働時間を超える労働には厳格なルールがあり、適切に管理しなければ罰則や従業員とのトラブルにつながります。
2019年の働き方改革関連法により、時間外労働の上限規制が法定化され、企業には以前にも増して正確な労働時間管理が求められるようになりました。法令を正しく理解し、従業員が健康的に働ける環境を整えることは、企業の信頼と成長にも直結します。
この記事では、時間外労働と残業の違い、36協定の基本、割増賃金の正しい計算方法などを、包括的に解説します。
- 時間外労働の定義や36協定の締結方法など、法令違反を防ぐための基礎知識
- 割増賃金の計算や管理監督者の扱いなどで、よくあるトラブルを防ぐ方法
- フレックス制度やノー残業デーなど、時間外労働を削減する具体的な施策
1.時間外労働の基本を理解しよう

時間外労働を適切に管理するには、まず法律上の定義と基本的なルールを正しく理解することが大切です。ここでは、時間外労働の基本概念と関連用語について解説します。
時間外労働とは法定労働時間を超えた労働のこと
時間外労働とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超えて働いた時間のことを指します。労働基準法第32条では、法定労働時間を「1日8時間、週40時間」と定めており、この時間を超える労働が時間外労働にあたります。
具体例をみていきましょう。
- 1日で9時間働いた場合
⇒1時間分が時間外労働 - 1日の労働時間は8時間以内だが週の合計が40時間を超えた場合
⇒超過分が時間外労働
企業は時間外労働に対して割増賃金を支払う義務があり、適切な労働時間管理が求められます。
参照:厚生労働省「労働時間・休日」
残業・所定外労働時間との違い
時間外労働と似た言葉に「残業」や「所定外労働時間」がありますが、それぞれ意味が異なります。
| 残業 | 就業規則で定めた所定労働時間を超えて働くこと |
| 所定外労働時間 | 所定労働時間を超えているものの、法定労働時間(1日8時間・週40時間)の範囲内に収まっている労働時間のこと |
■例えば:就業規則で定めた所定労働時間が7時間の企業
毎日1時間残業して週5日働いた場合
⇒週5日×(所定労働時間7時間+残業1時間)=40時間
1時間の残業は所定外労働時間だが、法定労働時間内のため時間外労働には該当しない
この場合、法律上は割増賃金の支払い義務はありませんが、就業規則で割増賃金を支払うと定めている企業もあるため、自社の規定を確認しましょう。
時間外労働を命じるには36協定が必須
企業が従業員に時間外労働をさせるには、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結が必須です。
36協定とは
時間外労働や休日労働について、会社と労働者の代表が書面で合意する協定。この協定を結ばずに時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性がある。
36協定は、締結するだけでなく、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。届出を怠ると法的効力が生じないため、協定の締結から届出までの手続きを確実に行う必要があります。
参照:厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」
日本における時間外労働の平均的な実態
dodaの調査によれば、2024年の平均残業時間は月21.0時間でした。また、厚生労働省の統計では運輸業・郵便業などで特に残業時間が長い傾向が見られます。
2.36協定の締結と届出の実務
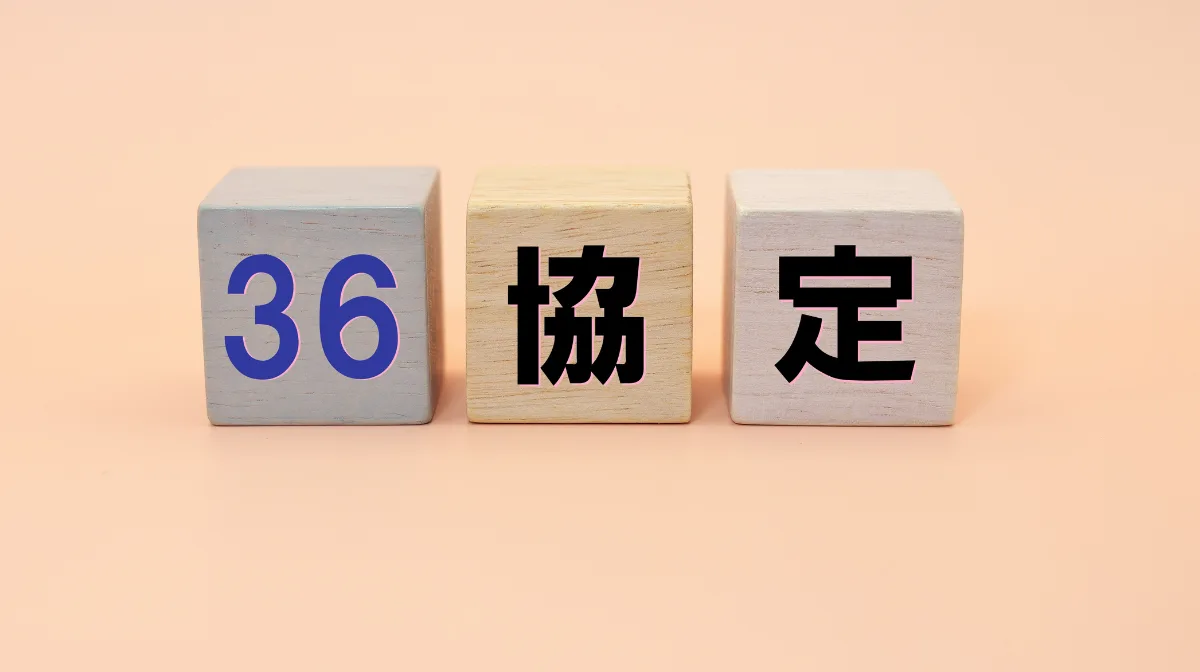
36協定の締結と届出は、時間外労働を適法に行うための必須手続きです。ここでは、協定の内容や締結の流れ、届出方法について実務的なポイントを解説します。
36協定で定める内容と記載事項
36協定では、時間外労働や休日労働について具体的な内容を定める必要があります。記載すべき主な事項を確認していきましょう。
- 延長できる労働時間の上限
原則として1ヶ月45時間、1年360時間が上限 - 時間外労働の対象となる業務の種類
「営業業務」「製造業務」など、具体的に業務内容が分かる表現で記載 - 対象となる労働者の範囲
「営業部門の従業員」「製造部門の従業員」など、部門や職種ごとに具体的に記載 - 協定の有効期間と起算日など
協定の有効期間は1年間とするのが一般的
労使協定の締結手続きと注意点
36協定を締結するには、会社側と労働者側の代表が合意する必要があります。締結した協定書は、労働基準監督署への届出だけでなく、社内での周知も必要です。
労働者側の代表は、労働組合がある場合はその労働組合、労働組合がない場合は、従業員の過半数によって選出された方が代表となります。
過半数代表者を選出する際は、民主的な方法で選ぶよう注意しましょう。使用者が一方的に指名したり、親睦会の代表を自動的に選んだりすることは認められません。
労働基準監督署への届出方法
36協定は、締結後に所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。届出のタイミングは、協定の効力が発生する日の前日までに行うのが原則です。厚生労働省が定める様式の「時間外労働・休日労働に関する協定届」で届け出てください。
届出方法は、以下の3種類から選択できます。
- 労働基準監督署の窓口へ持参
- 郵送
- 電子申請(e-Gov)
届出が受理されると、協定の効力が発生し、時間外労働や休日労働を命じられるようになります。届出を怠ると法的効力が生じないため、期限管理を徹底しましょう。

電子申請は窓口に行く手間が省け、24時間いつでも届出できるため便利です。
▼あわせて読みたい
こちらの記事でも、36協定の締結から届出まで、実務で必要な知識を網羅的に解説しています。労働基準監督署への届出書類の記入例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
■労働時間管理で困っていませんか?
36協定の締結や時間外労働の管理など、労務管理の複雑さに悩んでいませんか。カラフルエージェントでは、人事担当者の負担を軽減する採用支援を通じて、適切な労務管理体制の構築をサポートしています。
▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら
3.時間外労働の上限規制を正しく把握する
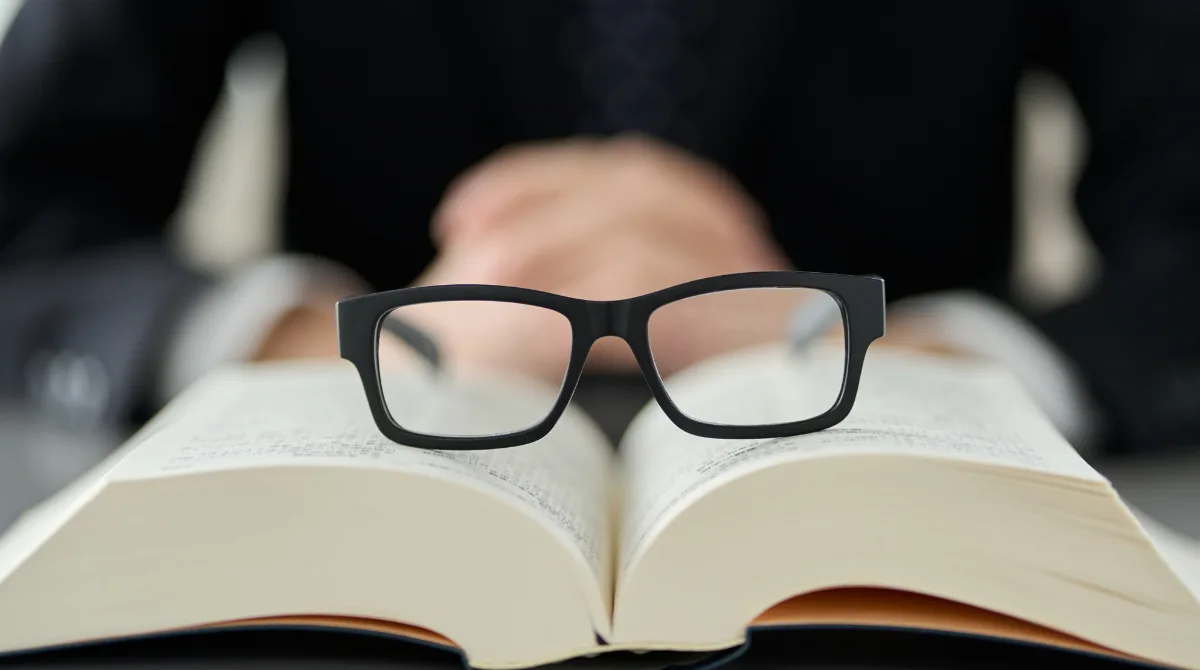
2019年の働き方改革関連法により、時間外労働の上限が法律で明確に定められました。ここでは、上限規制の内容と違反した場合のリスクについて詳しく解説します。
原則は月45時間・年360時間まで
時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間までと法律で定められています。これは2019年4月に施行された働き方改革関連法によって法定化されたもので、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用されました。
この上限を超えて時間外労働をさせた場合、企業には罰則が科されます。具体的には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があるのです。月ごと、年ごとの時間外労働時間を正確に把握し、上限を超えないよう管理することが重要です。
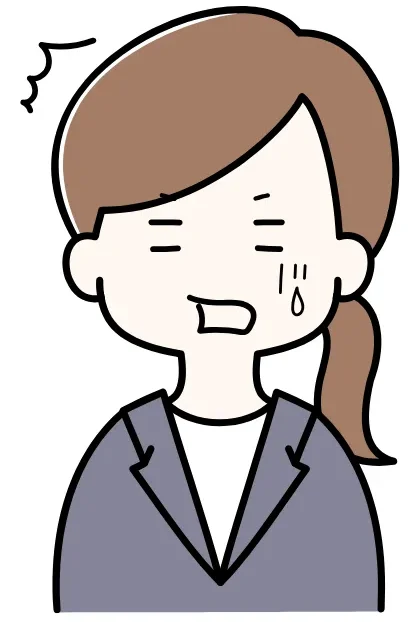
それまでは行政指導の対象でしたが、法定化により罰則付きの規制となったため、企業はより厳格な労働時間管理が求められるようになりました。
特別条項付き36協定で上限を延長できる条件
臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項付きの36協定を締結することで、月45時間・年360時間の上限を超える時間外労働が認められます。ただし、この場合でも守るべき上限があります。
- 年間の時間外労働は720時間以内に収める
- 時間外労働と休日労働はあわせて月100時間未満
- 2ヶ月から6ヶ月の平均勤務時間を月80時間以内に収める
- 月45時間を超える時間外労働は年6回まで
これらの条件をすべて満たす必要があり、一つでも超えると法律違反となります。特別条項を設ける際は、これらの複数の上限を同時に管理する仕組みを整えることが不可欠です。
上限規制違反のリスクと企業への影響
時間外労働の上限規制に違反した場合、企業には深刻な影響が及びます。
法令遵守は企業の社会的責任であり、上限規制を守ることは従業員の健康を守ることにもつながります。日々の労働時間管理を徹底し、違反を未然に防ぐ体制を整えましょう。
▼あわせて読みたい
時間外労働の削減には、組織全体の働き方を見直す必要があります。こちらの記事では、具体的な施策から成功事例まで、運送会社向けに詳しく解説しています。
4.時間外労働の割増賃金を正しく計算する

時間外労働には、通常の賃金に加えて割増賃金を支払う義務があります。ここでは、割増賃金の計算方法と、複数の割増が重なる場合の取り扱いについて解説します。
時間外労働の割増率は25%以上
時間外労働に対する割増賃金の割増率は、労働基準法第37条で25%以上と定められています。
■例えば…
時給1,500円の従業員が1時間の時間外労働を行った場合
⇒1,500円×1.25=1,875円
さらに、月60時間を超える時間外労働については、割増率が50%以上に引き上げられます。この規定は、以前は大企業のみに適用されていましたが、2023年4月からは中小企業にも適用されました。
割増賃金の未払いは労働基準法違反となり、従業員とのトラブルの原因にもなるため、1分単位で正確に計算しましょう。
深夜労働・休日労働が重なる場合の計算
深夜労働や休日労働が時間外労働と重なる場合、割増率の計算には注意が必要です。
深夜労働とは
午後10時から午前5時までの労働のことで、通常の賃金に25%以上の割増賃金が発生する。
時間外労働と深夜労働が重なる場合は、両方の割増率を合算し、50%以上の割増賃金を支払います。
■例えば…
時給1,500円の従業員が深夜に時間外労働を1時間行った場合
⇒1,500円×1.50=2,250円
また、法定休日に労働した場合は、35%以上の割増賃金が必要です。法定休日の深夜労働では、35%と25%を合算して60%以上の割増率となります。複数の割増が重なる場合は計算ミスが起きやすいため、労務管理システムの活用も検討しましょう。
割増賃金の具体的な計算方法と事例
月給制の割増賃金を計算する際は、まず1時間あたりの基礎賃金を算出します。
【計算方法】月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割って時給を求める
月給24万円で1ヶ月の平均所定労働時間が160時間の場合
⇒24万円÷160時間=1時間あたりの基礎賃金1,500円
この従業員が10時間の時間外労働を行った場合、1,500円×1.25×10時間で18,750円の割増賃金が発生します。パートやアルバイトなど時給制の場合は、時給に割増率を乗じて計算してください。
5.振替休日と代休の違いと正しい運用

休日に労働させた場合の対応として、振替休日と代休という2つの制度があります。両者は似ていますが、法律上の扱いが異なるため、正しく理解して運用する必要があります。
振替休日は事前の手続きで割増賃金不要
振替休日とは、事前に休日と労働日を入れ替える制度です。たとえば、日曜日を労働日とし、代わりに翌週の水曜日を休日とする場合、事前に振替の手続きを行えば、日曜日の労働は通常の労働日として扱われます。
この場合、休日労働の割増賃金(35%)は発生しません。ただし、振替休日制度を適用するには、就業規則に振替休日の規定を設けておく必要があります。また、振替は事前に行うことが原則で、労働日の前日までに従業員に通知することが求められます。
代休は休日労働の割増賃金が必要
代休とは、休日に労働した後に、その代わりとして別の日に休暇を与える制度です。振替休日との大きな違いは、休日労働が発生した時点では「法定休日労働」として扱われる点です。
したがって、代休を取得した場合でも、休日労働に対する35%以上の割増賃金を支払う義務が発生します。
■例えば…
日曜日に8時間労働した従業員に翌週の水曜日に代休を与えた場合
⇒日曜日の労働には35%の割増賃金が発生、水曜日は通常の休日扱いとなる
代休制度は、従業員の疲労回復には役立ちますが、割増賃金の支払い義務は残ることを理解しておきましょう。
■勤怠管理の効率化をお考えですか?
適切な人材配置と効率的な勤務体制の構築で、労務管理の負担軽減を目指しませんか。カラフルエージェントでは、貴社に最適な人材のご紹介を通じて、労務管理体制の改善をサポートしています。
▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら
6.多様な働き方における時間外労働の扱い

近年、働き方の多様化が進んでおり、リモートワークやフレックスタイム制、時短勤務など、さまざまな勤務形態が導入されています。
リモートワーク・在宅勤務での時間外労働管理
リモートワークや在宅勤務の場合でも、時間外労働に関する原則は変わりません。従業員が法定労働時間を超えて働いた場合、企業は割増賃金を支払う義務があります。ただし、在宅勤務では労働時間の把握が難しくなるため、次のように勤怠管理の工夫を取り入れましょう。
- 始業・終業時刻の報告を義務付ける
- 勤怠管理システムを導入する
- 定期的にオンラインでコミュニケーションを取るなど
また、業務指示の有無を明確にすることも重要です。自主的な作業なのか、会社からの指示による業務なのかを区別し、指示による業務の場合は時間外労働として扱います。
フレックスタイム制の時間外労働計算
フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)内で労働時間を調整できるため、1日ごとの残業計算を行う必要がありません。時間外労働は、清算期間全体の労働時間が法定労働時間の総枠を超えた場合に発生します。
■例えば…
清算期間:1ヶ月/その月の法定労働時間の総枠:160時間の場合
⇒実際の労働時間が170時間であれば、10時間が時間外労働
時短勤務者の時間外労働の注意点
時短勤務の従業員であっても、法定労働時間(1日8時間)を超えて働いた場合は、通常の従業員と同様に割増賃金の支払い義務が発生します。
■例えば…
所定労働時間が6時間の時短勤務者が9時間働いた場合
⇒法定労働時間の8時間を超える1時間分について、25%以上の割増賃金が必要
一方、所定労働時間の6時間を超えているものの法定労働時間内に収まる2時間分については、割増賃金の支払い義務はありません。

時短勤務者に時間外労働をさせる場合は、育児や介護との両立に配慮した運用を心がけましょう。
▼あわせて読みたい
裁量労働制についても理解を深めておくと、多様な働き方への対応力が高まります。こちらの記事では、制度の基礎から実務のポイントまで詳しく解説しています。
7.実務で注意すべき時間外労働のトラブル

ここでは、時間外労働の管理において、特に注意が必要な3つの事例について解説します。
管理監督者の条件と割増賃金
労働基準法では、「管理監督者」に該当する場合、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用除外されるため、時間外手当の支払い義務はありません。しかし、管理監督者と認められるには、単に部長や課長という役職名があるだけでは不十分です。
次の要件を満たさない場合、「名ばかり管理職」として残業代の未払いを指摘され、過去にさかのぼって多額の支払いを命じられるリスクがあるため注意が必要です。
- 経営者と一体的な立場にあること
- 重要な責任と権限があること
- 勤務時間に裁量があること
- 相応の待遇を受けていることなど
管理監督者であっても、労働基準法上の年次有給休暇や、深夜労働(午後10時から午前5時)に対する25%以上の割増賃金は支払う必要があります。
みなし残業制度の正しい運用とリスク
みなし残業(固定残業)制度を導入する場合、賃金規定や雇用契約書に、対象となる残業時間数と割増賃金額を明示する必要があります。
例えば、「月30時間分の時間外手当として5万円を含む」といった形で、基本給と固定残業代を明確に区別してください。みなし残業時間を超える労働が発生した場合は、別途残業代を追加で支払う義務があります。
さらに、基本給が最低賃金を下回らないよう注意が必要です。みなし残業代を差し引いた基本給が最低賃金を下回る場合、最低賃金法違反となります。
自主的な残業も黙認すれば時間外労働になる
従業員が自主的に行った残業であっても、使用者がこれを認識しながら黙認していた場合、「指示による労働」とみなされ、時間外労働として扱われます。
■例えば…
上司が部下の残業を知っていながら何の対応もしなかった場合
⇒部下から残業申請がなくても、未払賃金の支払い義務が生じる可能性がある
自主的な残業を防ぐためにも、時間外労働の事前申請制を徹底しましょう。残業が必要な場合は事前に上司の承認を得るルールを設け、無許可の残業は原則禁止としてください。

勤怠管理システムなどで勤務実態を可視化し、長時間在席している従業員には声をかけるなど、組織全体で労働時間管理の意識を高めることが大切です。
▼あわせて読みたい
労働トラブルを未然に防ぐには、日頃からの適切な対応が重要です。時間外労働に関するトラブルを含め、運送会社で起こりがちな労働トラブルの予防と解決のコツについて、実践的な対策を紹介しています。
8.時間外労働を削減するための具体策

働き方改革を推進し、従業員の健康を守るためには、時間外労働を削減する取り組みが不可欠です。ここでは、企業が実践できる具体的な施策を紹介します。
業務効率化ツールの導入と従業員教育
業務の効率化は、時間外労働削減の第一歩です。タスク管理ツールやチャットツールを導入することで、業務の可視化や迅速なコミュニケーション体制を整え、無駄な時間を減らすことができます。
また、従業員向けの業務改善研修を実施し、業務の優先順位付けや効率的な作業方法を学ぶ機会を設けることも効果的です。小さな改善でも、積み重ねることで大きな時間短縮につながります。
■例えば…
- 会議の時間を短縮する
- 資料作成の手順を標準化する
- 定型業務を自動化するなど
さらに、時間外労働のリスクや法令遵守の重要性を周知することで、従業員一人ひとりの「労働時間内に業務を終わらせる」という意識を高めます。
■働き方改革を推進したい企業様へ
時間外労働の削減には、適切な人材配置と業務効率化が欠かせません。カラフルエージェントでは、貴社のニーズに合った即戦力人材のご紹介を通じて、働き方改革の推進をサポートします。
▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら
フレックスタイム制で柔軟な働き方を実現
フレックスタイム制を導入することで、業務の繁閑に合わせた柔軟な働き方が実現し、残業時間の抑制につながります。従業員は清算期間内で所定労働時間を調整できるため、忙しい時期に長く働いた分を、別の日に早く帰ることで調整します。
これにより、無理な残業を減らし、ワークライフバランスの向上も期待できるでしょう。柔軟な働き方は、従業員の満足度向上と生産性向上の両立につながるのです。
フレックスタイム制を導入するには
労使協定の締結と就業規則の整備が必要
対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間内の総労働時間などを明確に定め、従業員に周知します。
ノー残業デーの制度化と定着のコツ
毎週特定の曜日を「ノー残業デー」と設定し、定時退社を促す取り組みも有効です。単なるスローガンで終わらせないためにも、具体的な行動指針を設けてください。一般的によく取り入れられている工夫をみていきましょう。
- 管理職が率先して定時に退社する
- ノー残業デーには会議を設定しない
- 業務スケジュールを見直して定時内に終わるよう調整するなど
実施状況は定期的にモニタリングし、退社時刻のデータを集計して部署ごとに共有することで、取り組みの定着を図ります。形骸化させないためには、経営層が強いリーダーシップを発揮し、制度の重要性を継続的に発信することが不可欠です。
時間外労働の事前申請制で不要な残業を抑制
時間外労働を行う場合に、事前に上司への申請・承認を必須とする制度を導入することで、不要な残業を抑制できます。原則として無許可の残業を禁止し、違反があった場合の対応も就業規則で明確にしておきましょう。
ただし、やむを得ず事後申請となった場合でも、適切に労働時間を記録し、割増賃金を支払ってください。

制度導入時には、従業員に趣旨を丁寧に説明し、サービス残業を強要するものではないことを明確に伝えましょう。
▼あわせて読みたい
従業員の離職を防ぎ、定着率を向上させることも、時間外労働削減につながります。こちらの記事では、離職率の計算方法から具体的な改善策まで、運送会社の成功事例を交えて詳しく解説しています。
9.時間外労働の適正管理で職場環境を整える
時間外労働の適切な管理は、法令遵守と従業員の健康を守るために不可欠です。本記事では、時間外労働の基本から36協定、上限規制、割増賃金の計算まで、人事担当者が押さえるべき法的要件と実務知識を網羅的に解説しました。
適切な労務管理体制を構築することは、企業のコンプライアンスを担保するだけでなく、持続的な成長を支える経営基盤となります。本記事の情報を、従業員が安心して働ける職場環境の整備にお役立てください。
■人事労務でお困りの企業様をサポートします
時間外労働の管理から人材配置まで、人事労務の課題は多岐にわたります。カラフルエージェントでは、採用支援を通じて貴社の労務管理体制の改善をお手伝いしています。
▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら