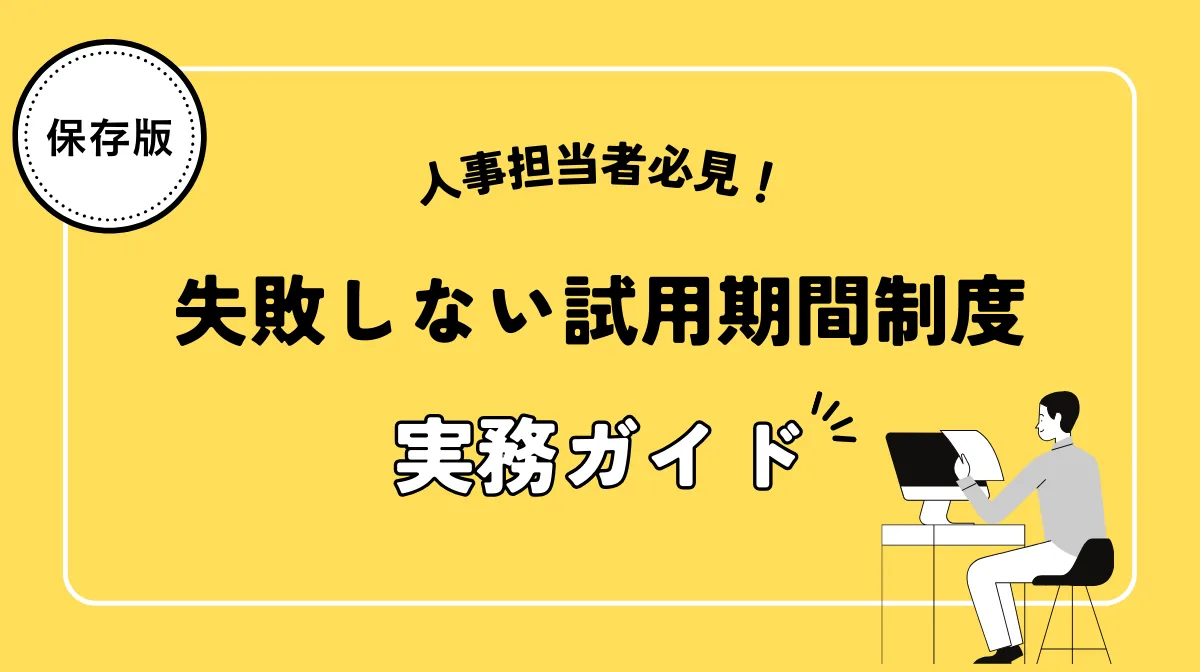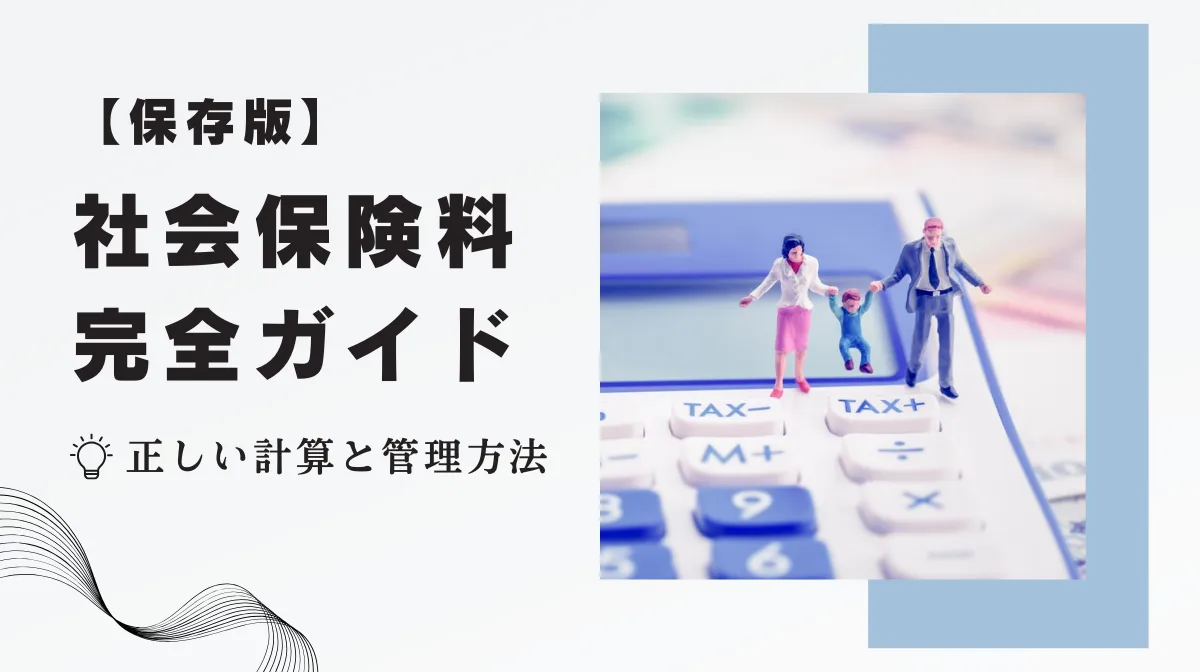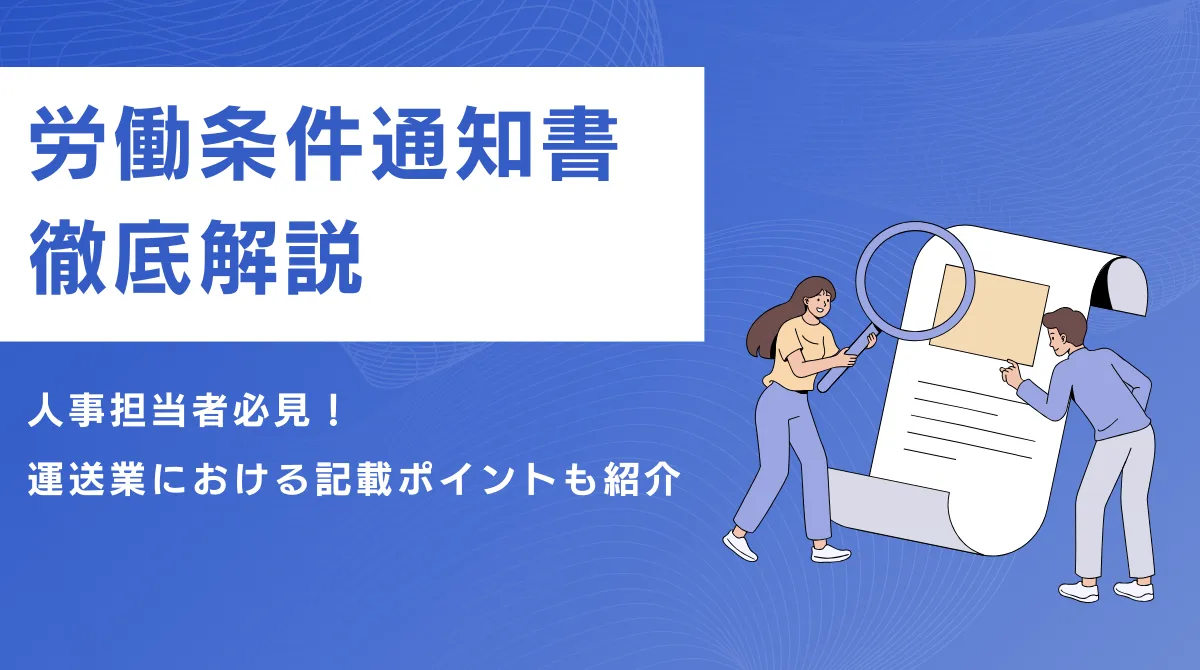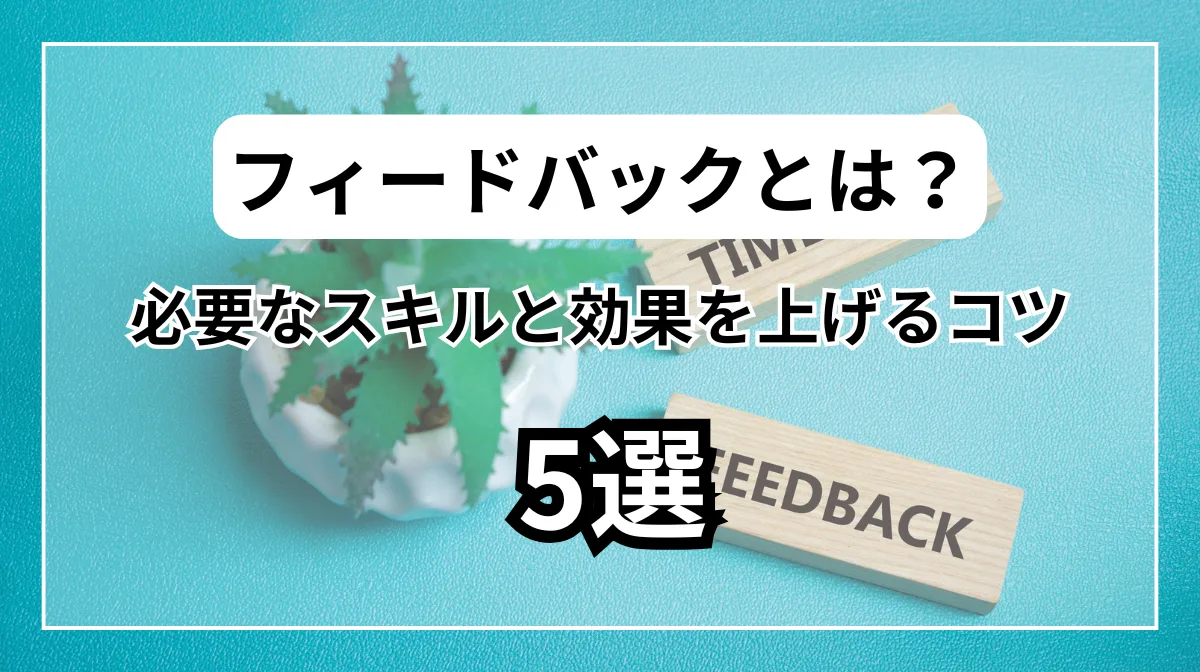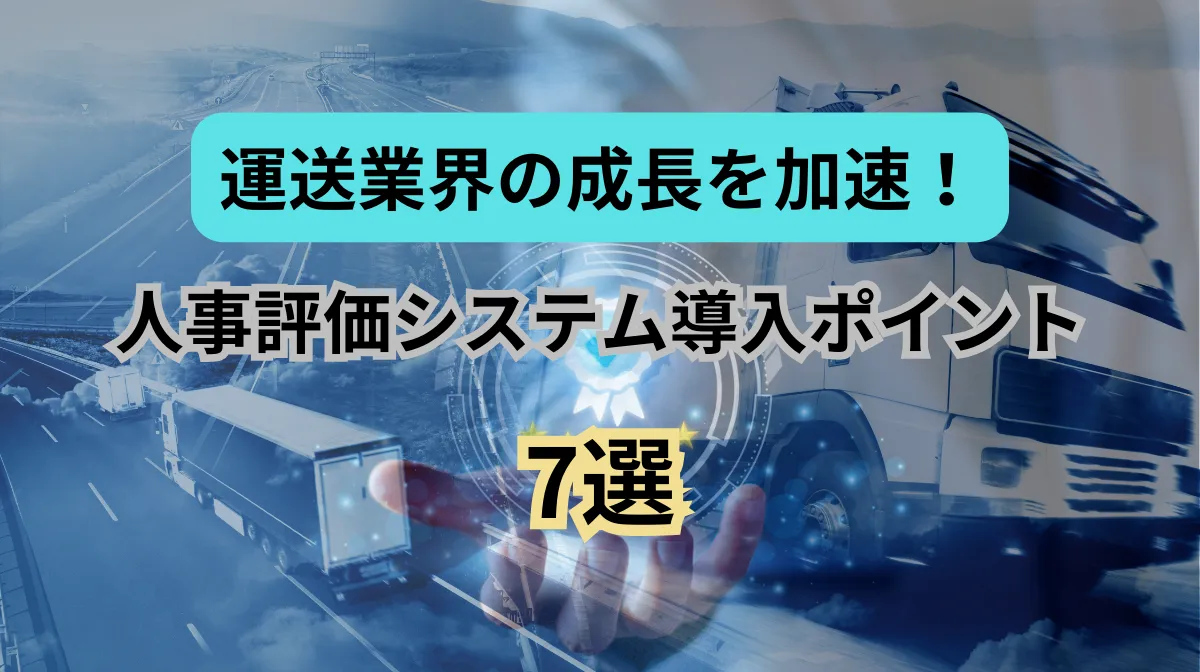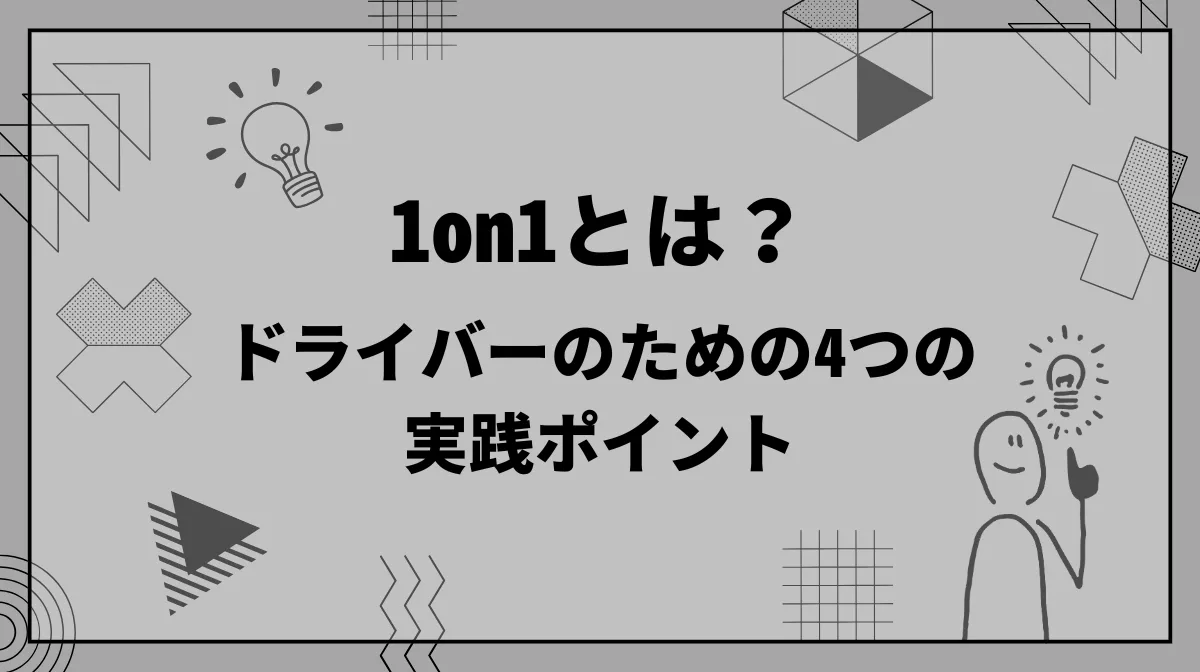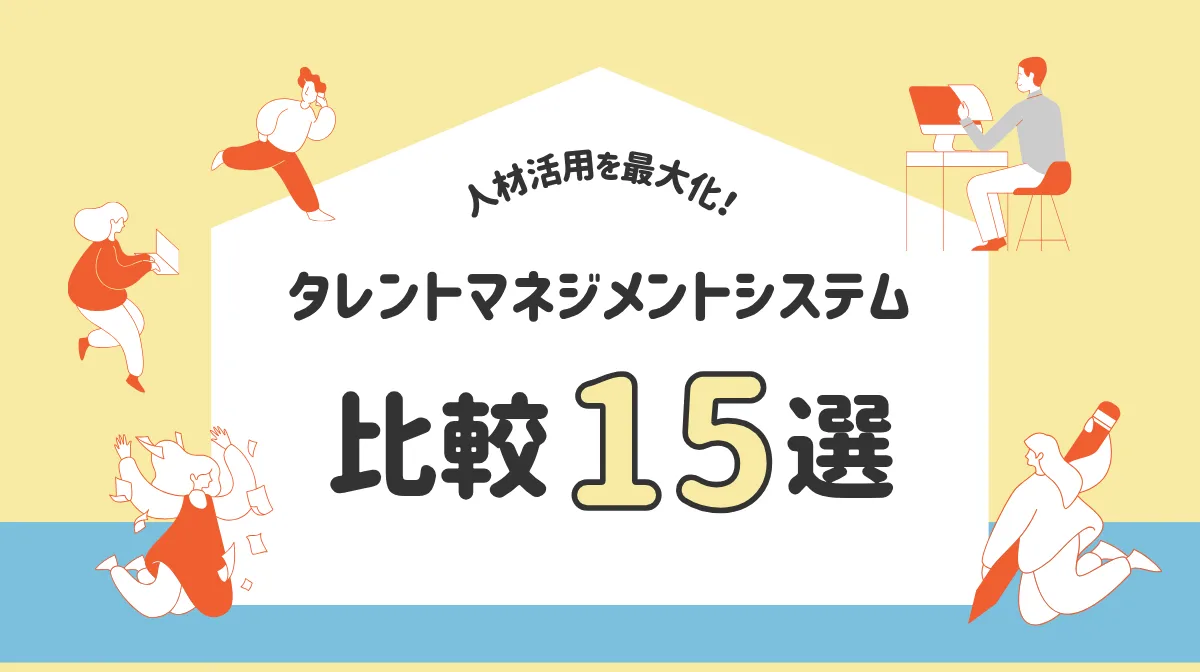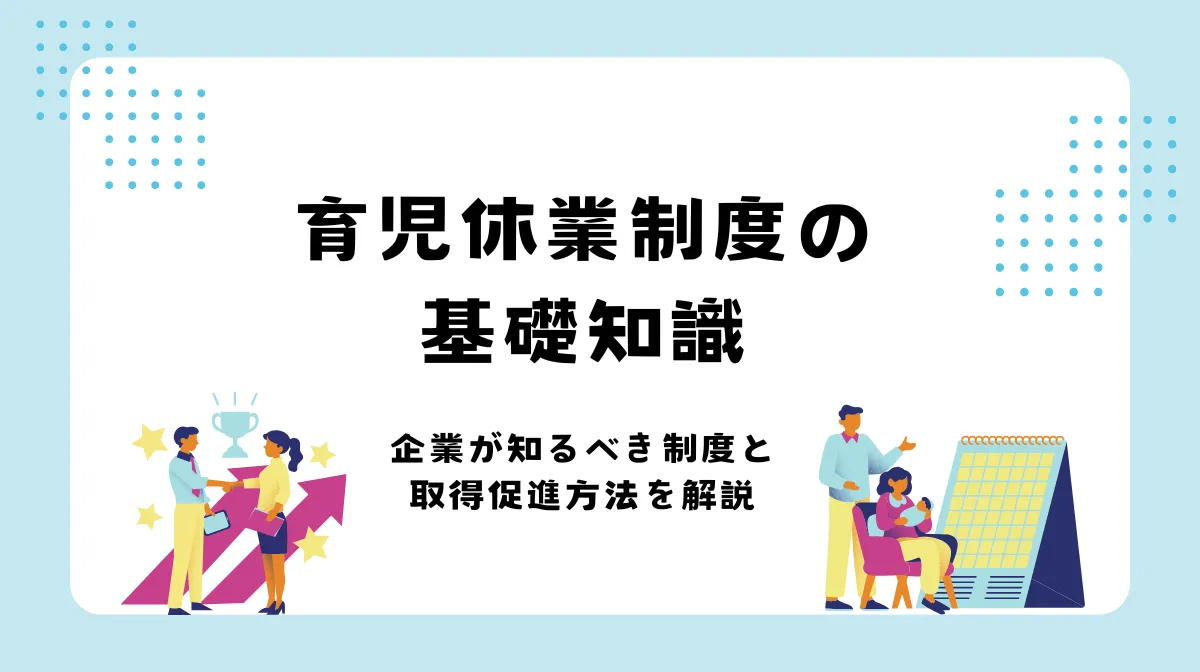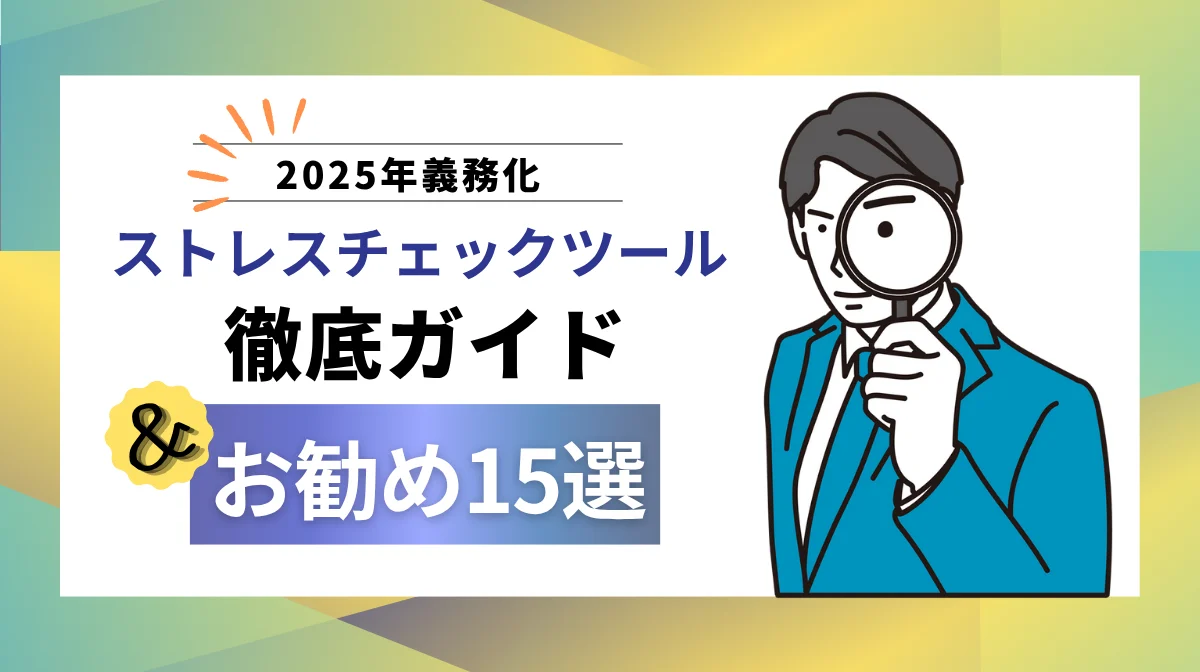試用期間制度は、企業が新規採用者の適性を見極めるための重要な仕組みです。しかし、その運用を誤ると労働トラブルを引き起こすリスクもあります。
本記事では、人事担当者や経営者が押さえておくべき試用期間制度の基礎知識から、トラブル防止のための実践的なポイントまでを、法的観点と実務の両面から解説します。
- 試用期間制度の法的位置づけと適切な運用方法
- 試用期間中の労務管理と評価のポイント
- トラブルを防ぐための具体的な対応策と注意点
1.試用期間制度とは
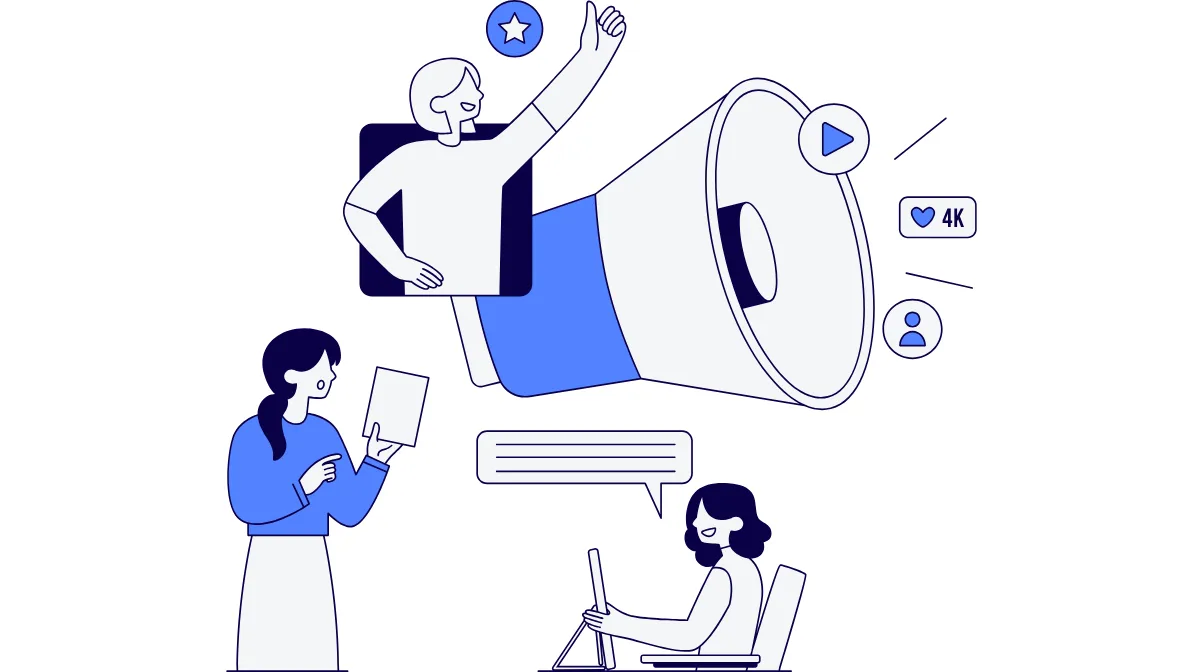
企業が新規採用者の適性や能力を見極めるために設ける重要な期間について、その基本的な概念と法的な位置づけを解説します。
試用期間制度の目的と意義
試用期間制度は、採用時の面接や書類選考だけでは把握しきれない能力を、総合的に評価する機会を提供します。
- 職場での実践的な能力
- チームワーク
- コミュニケーション能力 など
企業にとっては人材のミスマッチを防ぎ、適材適所の人員配置を実現するための重要なプロセスとなります。
また、従業員側にとっても、実際の業務を通じて職場環境や業務内容との相性を確認できる期間として機能します。
法的位置づけと雇用契約上の特徴
試用期間は労働基準法などの法律で直接的な規定はありませんが、判例上では「解約権留保付労働契約」として位置づけられています。
この期間中も正式な雇用契約関係が成立しており、労働法規や社会保険関係の規定は通常の従業員と同様に適用されます。ただし、企業側には通常よりも広い解約権が認められており、一定の条件下では本採用を拒否することが可能です。
その判断は客観的に合理的で、社会通念上相当であることが求められ、恣意的な判断は認められません。
参考:「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」中間取りまとめ(抄)(労働関係の成立)|厚生労働省
2.試用期間の設定方法
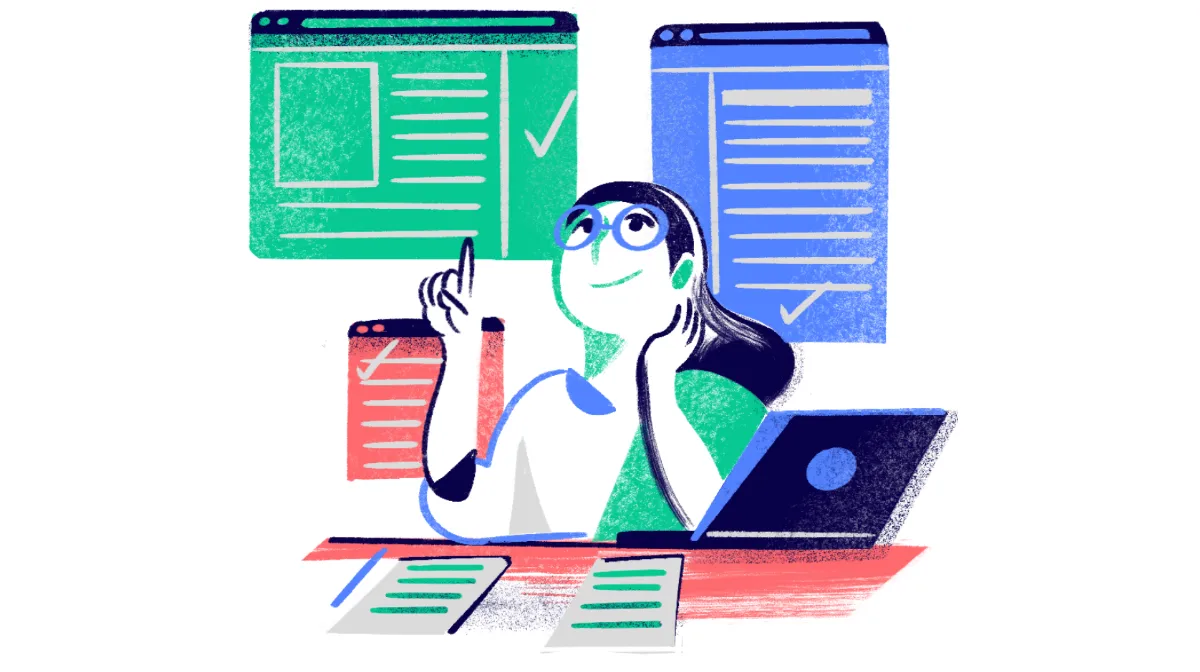
試用期間の設定は企業の裁量に委ねられていますが、適切な運用のためには明確なルールと手続きの確立が不可欠です。ここでは具体的な設定方法について解説します。
適切な期間の設定基準
試用期間の長さは、業種や職種、企業規模によって異なりますが、一般的には3ヶ月から6ヶ月程度が標準的です。この期間設定には、業務の複雑性や必要なスキルの習得期間、企業文化への適応期間などを考慮する必要があります。
特に専門性の高い職種では最長1年程度まで認められる場合もありますが、過度に長期の設定は従業員の不安定な立場を長引かせることになるため避けるべきです。また、パートタイムや契約社員など、雇用形態によっても適切な期間は異なってきます。
参考:従業員の採用と退職に関する実態調査|独立行政法人 労働政策研究・研修機構
就業規則への記載事項
就業規則への試用期間に関する記載は、労使間のトラブルを防ぐ上で極めて重要であり、明確に定める必要があります。
- 試用期間の長さ
- 期間中の労働条件
- 評価基準
- 本採用の要件 など
特に重要なのは、試用期間中の賃金や手当、福利厚生などの処遇条件、また試用期間の延長や本採用拒否の条件などについても具体的に明記することです。

これらの規定は、労働基準監督署への届出や従業員への周知が必要となります。
雇用契約書での明示方法
雇用契約書における試用期間の明示は、労働条件明示の一環として法的にも重要な意味を持ちます。契約書には、試用期間の具体的な期間(○年○月○日から○年○月○日まで)を明記し、この期間中の労働条件や本採用後の条件との違いがある場合はその内容も明確に示す必要があります。
また、試用期間中の評価方法や本採用の判断基準についても、可能な限り具体的に記載することで、後のトラブルを防ぐことができます。さらに、試用期間の延長可能性がある場合は、その条件や手続きについても明記しておくことが望ましいでしょう。
参考:職業安定法施行規則4条の2第3項2号の2|e-Gov 法令検索
3.試用期間中の労務管理
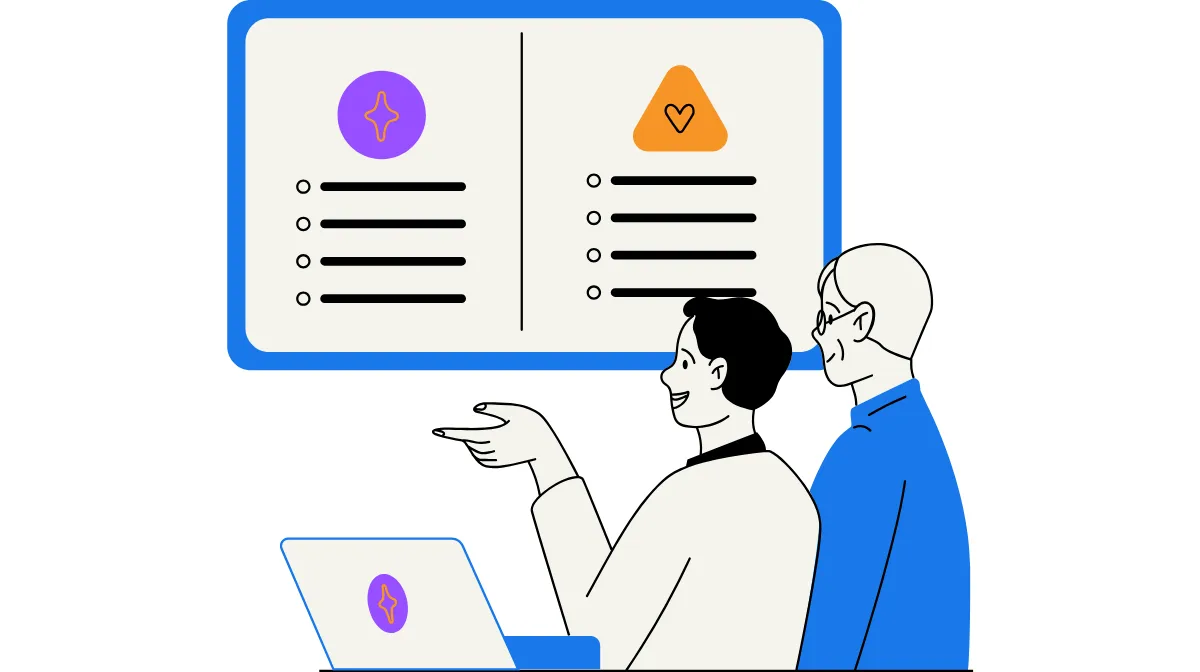
試用期間中の労務管理は通常の従業員と基本的に同じ基準で行う必要がありますが、いくつかの重要な特徴と注意点があります。以下では主要な管理項目について詳しく解説します。
給与・手当の取り扱い
試用期間中の給与や手当については、法令に基づいた適切な支払いが求められます。
- 基本給は最低賃金以上の確保が必須
- 時間外労働や深夜労働に対する割増賃金は通常通りの支払いが必要
- 通勤手当や役職手当は就業規則の基準に従って支給
試用期間中は本採用後よりも低い給与水準を設定することは可能ですが、その場合は雇用契約時に明確な説明と合意が必要です。
社会保険・労働保険の適用
試用期間中であっても、該当する要件を満たす従業員には社会保険および労働保険への加入が必須となります。
加入が必要な保険制度
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 労災保険
- 雇用保険
加入要件は雇用形態や労働時間、給与額などによって定められており、試用期間という理由での加入除外は認められません。
特に、週20時間以上勤務する場合の社会保険加入や、1日でも勤務がある場合の労災保険の適用などは、試用期間中でも確実に行う必要があります。
▼関連記事
下記の記事では、企業における社会保険料の基本から計算方法、実務上のトラブル対応まで、人事担当者必見の管理術を詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
労働条件の明示と変更
試用期間中の労働条件は、採用時に書面で明示した内容を遵守する必要があります。
基本的な労働条件(本採用と同様の扱い)
- 労働時間
- 休憩時間
- 休日
- 福利厚生
- 各種手当
基本的な労働条件は、原則として本採用後と同様の扱いとなりますが、業務の必要性や本人の適性に応じて、配属部署や担当業務の変更を行うことは可能です。
その場合でも、労働条件の不利益変更とならないよう注意が必要で、変更する際は本人との十分な協議と合意が必要となります。また、試用期間終了後に労働条件を変更する場合は、その内容を事前に明確に説明し、書面での合意を得ることが重要です。
▼関連記事
下記の記事では、労働条件通知書基本から実務での作成・運用方法、トラブル防止策まで、人事労務担当者向けに解説します。あわせて参考にしてください。
4.試用期間中の評価と対応

試用期間における評価は、本採用の判断を左右する重要なプロセスです。公平かつ客観的な評価基準の設定と、適切なフィードバックの実施が求められます。以下で具体的な実施方法を解説します。
評価基準の設定方法
評価基準は複数の観点から包括的に設定する必要があります。
- 職務遂行能力
- 勤務態度
- チームワーク
- 成長性 など
具体的には、業務の正確性や効率性、規律性、コミュニケーション能力、習熟度などの項目について、できるだけ数値化や段階評価が可能な形で基準を設定します。
特に重要なのは、評価基準が職務内容や求められる役割と整合性を持っていることです。また、評価者による主観的な判断の偏りを防ぐため、複数の評価者による多面的な評価システムを構築することも推奨されます。
面談・フィードバックの実施
試用期間中は定期的な面談とフィードバックを実施し、従業員の成長を支援するとともに、課題がある場合は早期の改善を促す必要があります。
面談は通常、月1回程度の頻度で実施し、業務の進捗状況や課題、目標の達成度などについて話し合います。フィードバックは具体的な事実に基づいて行い、改善すべき点がある場合は、具体的な行動指針や目標を示すことが重要です。

面談内容は記録として残し、後の評価や指導の参考資料として活用しましょう。
▼関連記事
下記の記事では、フィードバックの基本から実践的なテクニックまで完全解説しています。効果的な伝え方と受け方のポイントを、具体例を交えて紹介しています。あわせて参考にしてください。
本採用・不採用の判断基準
本採用の判断は、試用期間中の評価結果を総合的に考慮して行います。
- 業務遂行能力の達成度
- 勤務態度
- 職場への適応度
- 将来性 など
不採用とする場合は、客観的な事実に基づく合理的な理由が必要で、単なる印象や主観的な判断だけでは不十分です。
特に重要なのは、評価過程の透明性と公平性を確保することです。判断結果は、具体的な評価内容とともに本人に明確に説明し、必要に応じて書面での通知も行います。
5.試用期間での解雇と退職

試用期間中の解雇や退職については、一般の従業員とは異なる特別な規定が適用される場合があります。しかし、その運用には慎重な判断と適切な手続きが必要です。以下で具体的な対応方法を解説します。
解雇可能事由と手続き
試用期間中の解雇は、通常の従業員よりも広い範囲で認められますが、その判断には客観的な合理性と社会通念上の相当性が求められます。具体的な解雇事由としては以下が該当します。
- 重大な規律違反
- 虚偽の経歴申告
- 業務遂行能力の著しい不足 など
手続きとしては、まず当該従業員に対して具体的な問題点を指摘し、改善の機会を与える必要があります。
また、解雇を決定する際は、人事部門や上司など複数の関係者による協議を経て、慎重に判断することが重要です。
解雇予告・解雇予告手当
試用期間中であっても、採用から14日を超えて勤務している従業員を解雇する場合は、原則として30日前の解雇予告か、30日分の平均賃金に相当する解雇予告手当の支払いが必要です。
ただし、入社後14日以内の解雇については、予告や手当の支払いなしで即時解雇が可能です。
解雇予告を行う場合は、その理由を具体的に説明し、書面で通知することが望ましいです。また、解雇予告期間中も通常通りの給与支払いと労務管理が必要となります。
試用期間中の退職対応
試用期間中の従業員から退職の申し出があった場合も、適切な対応が求められます。退職の意思表示があった場合は、その理由をヒアリングし、可能な範囲で改善策を検討することが望ましいです。
退職手続きについては、就業規則に定められた手続きに従って進める必要があり、一般的には2週間前までの退職届の提出が求められます。また、業務の引き継ぎや社内物品の返却など、退職に伴う諸手続きについても漏れなく実施する必要があります。
6.トラブル防止のポイント

試用期間中のトラブルは、企業にとって大きな損失につながる可能性があります。適切な制度設計と運用によって、トラブルを未然に防ぐための重要なポイントを解説します。
採用時の注意点
採用プロセスにおいて、試用期間に関する明確な説明と合意形成が重要です。募集要項や面接時には、試用期間の存在とその条件について具体的に説明し、応募者の理解を得る必要があります。

特に、以下については誤解が生じないよう丁寧な説明が求められます。
- 試用期間中の労働条件
- 評価基準
- 本採用までのプロセス など
また、採用時の書類選考や面接での評価内容と、試用期間中の評価基準との整合性を確保することで、ミスマッチを防ぐことができます。
試用期間中の教育・指導の進め方
試用期間中の教育・指導は、計画的かつ体系的に実施する必要があります。
- 業務に必要な基本的なスキルや知識の習得を支援する研修プログラムを用意する
- 日常的な業務指導においては、具体的な目標設定と達成度の確認を定期的に行い、必要に応じて適切なフィードバックを提供する
特に重要なのは、問題が発生した際の早期発見と対応です。上司や先輩社員による日常的なサポート体制を整え、従業員が相談しやすい環境を整備することが求められます。
書類・記録の管理方法
試用期間に関する書類や記録は、適切に作成・保管するとともに、人事部門で一元管理し、必要に応じて閲覧・参照できる体制を整えます。
- 試用期間に関する規定を含む就業規則
- 労働条件通知書
- 評価シート
- 面談記録
- 指導記録 など
特に、評価に関する記録は、本採用の判断や将来的な人材育成の基礎資料となるため、客観的な事実に基づいて詳細に記録することが重要です。
また、トラブルが発生した際の証拠資料としても活用できるよう、適切な保管期間を設定し、管理することが求められます。
7.実務者のための試用期間
試用期間制度は、企業と従業員双方にとって重要な意味を持つ制度です。企業側には人材の見極めと適材適所の実現、従業員側には職場との相性確認という目的があります。
この制度を効果的に運用するためには、明確な評価基準の設定、適切な労務管理、丁寧なコミュニケーション、そして何より法令遵守が不可欠です。
トラブルを防ぎながら制度の本来の目的を達成するためには、本記事で解説した実務的なポイントを押さえた上で、自社の状況に応じた適切な制度設計と運用を心がけることが重要です。