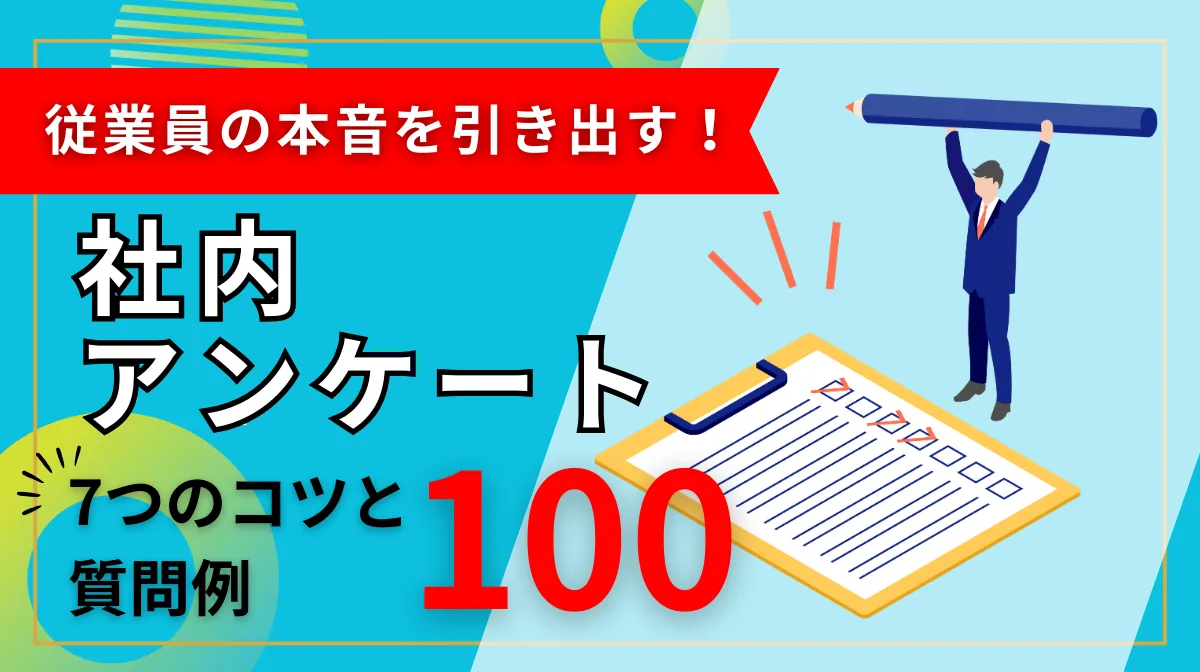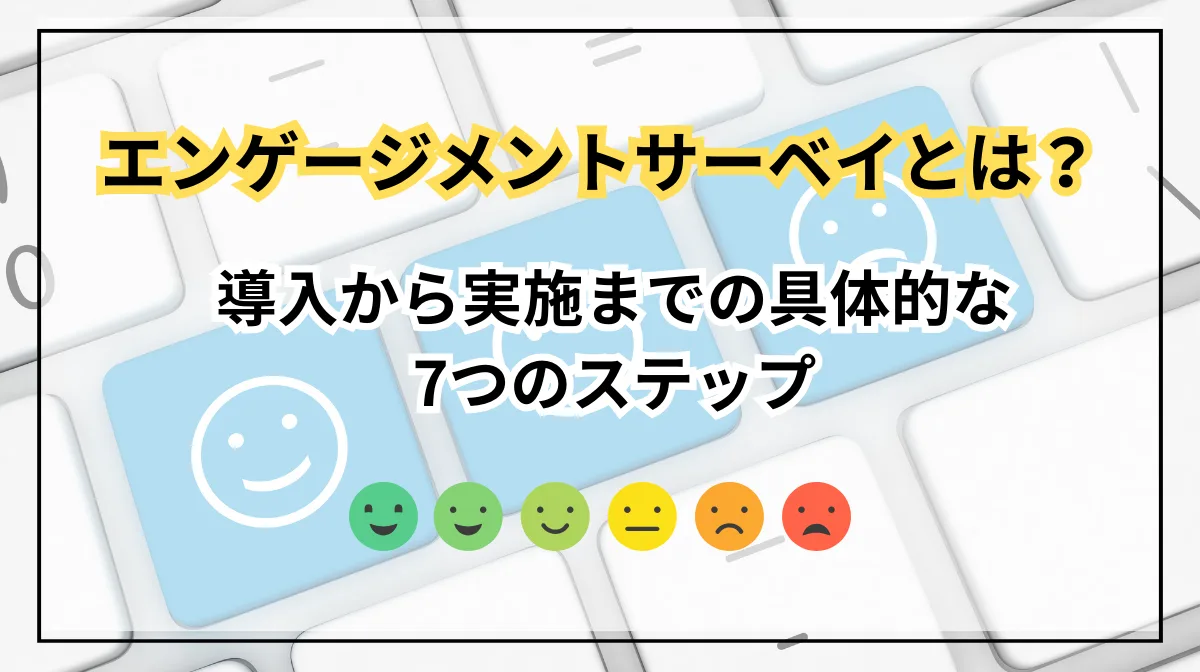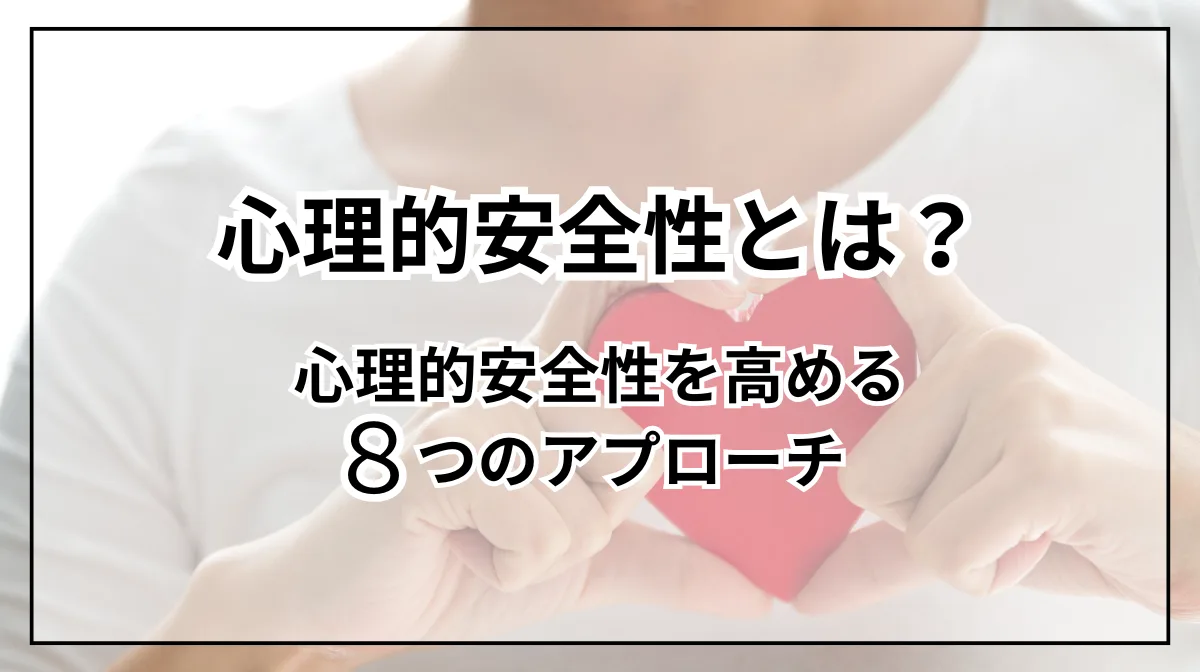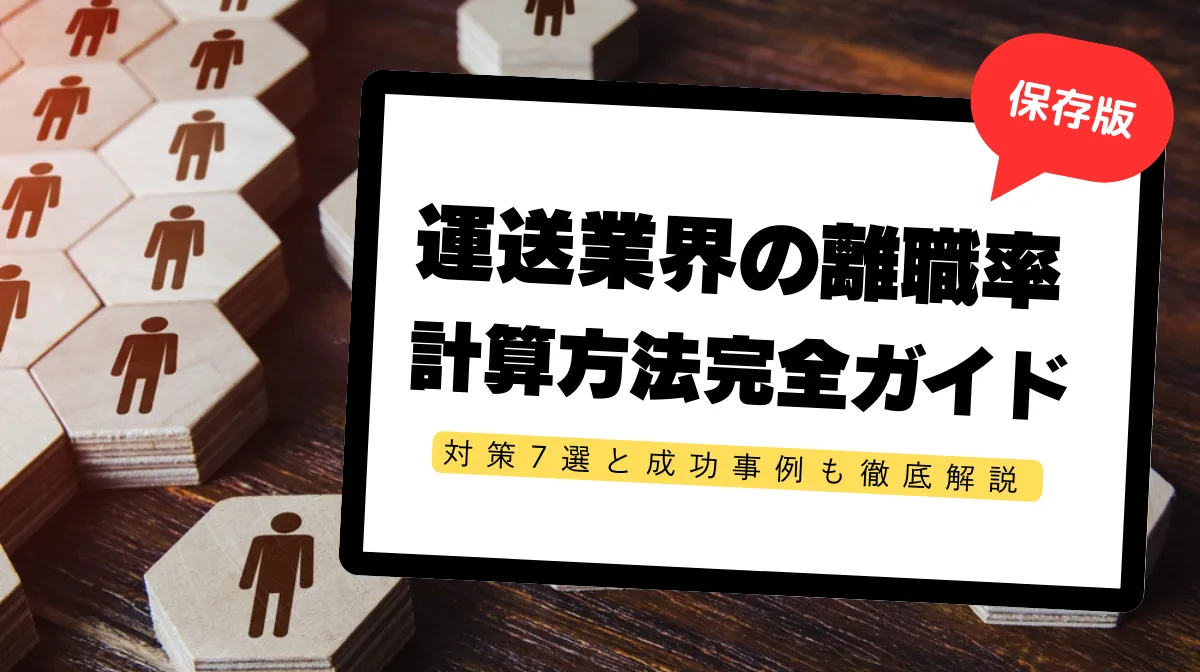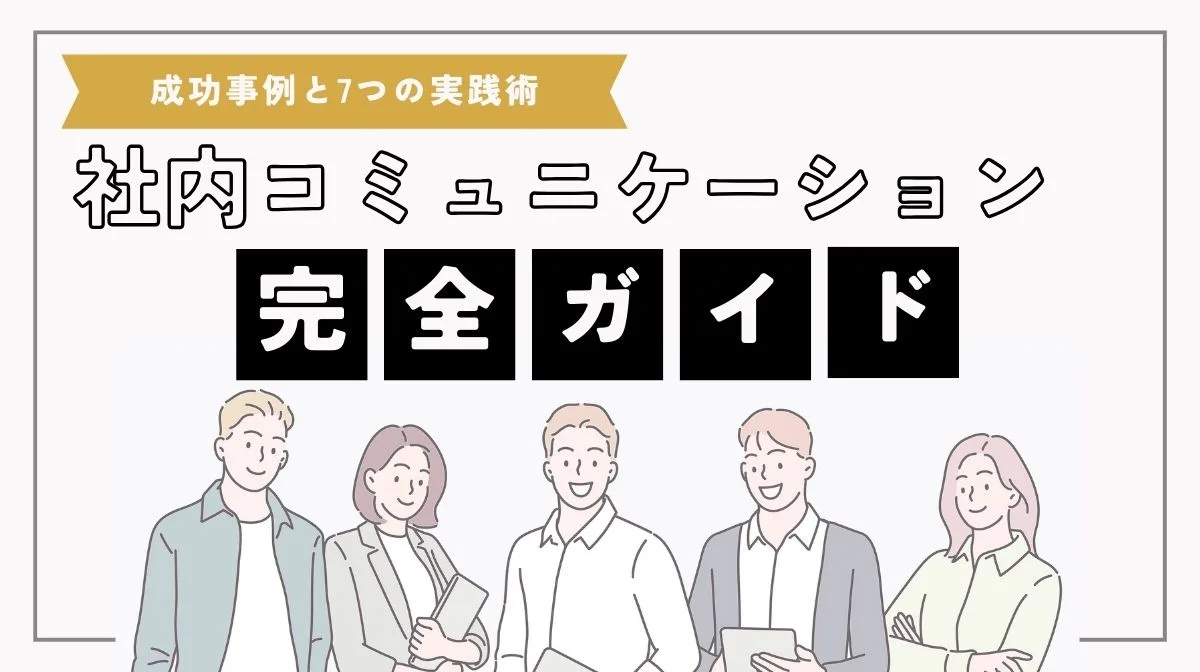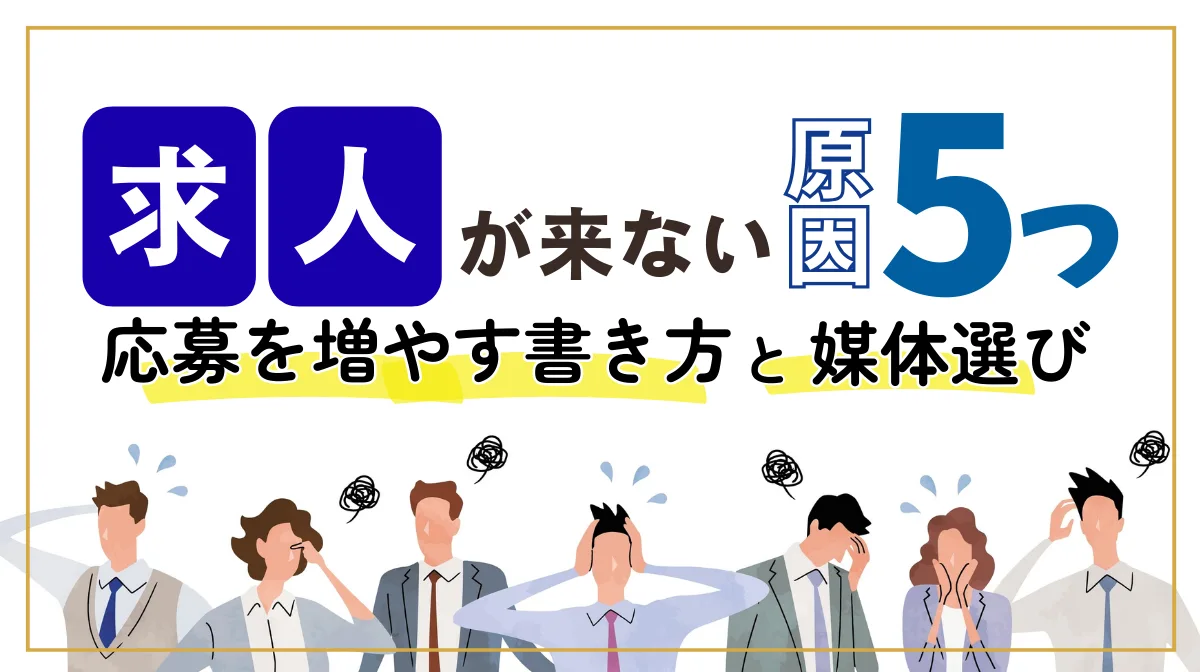「従業員の本音が見えない」「組織の課題を具体的に把握したい」といった悩みを抱える人事担当者も多いでしょう。
厚生労働省の調査によれば、現在の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は8割を超えています。このような従業員が抱える課題を放置すれば、離職率の悪化や生産性の低下に直結しかねません。
その解決策の一つが、社内アンケートです。適切に設計・実施すれば、従業員の率直な声を収集し、データに基づく組織改善につなげられます。
本記事では、社内アンケートの基本から実践的な質問例まで、人事担当者が押さえておくべき要点を網羅的に解説します。
- 従業員の率直な意見を引き出すための具体的なテクニックと実践ポイント
- ハーズバーグ理論を活用した質問設計や100の質問例により、離職防止や従業員満足度向上が目指せる
- 準備段階から結果活用まで7つのステップと注意点を理解し、成功率の高いアンケートを実施できる
1.社内アンケートとは?基本的な仕組みやメリット

社内アンケートの基本から実際の効果まで、人事担当者が知っておくべき重要なポイントをご紹介します。
社内アンケートの定義と目的
社内アンケートとは、企業が従業員を対象に実施する調査のことです。主に、次のような情報を把握するために行われます。
- 職場環境
- 業務内容
- 人間関係
- 待遇などに対する従業員の意見や満足度など
「従業員満足度調査」や「ES調査」とも呼ばれており、年に1回から数ヵ月に1度の頻度で実施されるのが一般的です。主に人事部門や総務部門が企画・実施しますが、労働組合が主体となって行うケースもあります。
▼あわせて読みたい
こちらの記事では、エンゲージメント向上に特化したサーベイの実施方法について詳しく解説しています。組織改革に向けてサーベイの導入を考えている企業は、ぜひ参考にしてください。
社内アンケートがもたらす5つのメリット
社内アンケートの実施には大きく分けて5つのメリットがあります。
- 従業員の本音や生の声を収集できる
普段の業務では言いづらい意見も、匿名性が確保されたアンケートなら率直に回答してもらえる - データに基づいた客観的な意思決定ができる
感覚や推測ではなく、具体的な数値データを根拠に改善策を立案できる - 組織の課題を早期に発見し、迅速な対応ができる
問題が深刻化する前に手を打つことで、従業員のストレス軽減や職場環境の改善につながる - 従業員のエンゲージメント向上が期待できる
自分たちの意見が聞き入れられているという実感が、組織への帰属意識を高める
これらの効果により離職防止と人材定着、さらには業績向上という好循環が生み出されるのです。実際に、厚生労働省の調査でも従業員満足度を重視する企業ほど売上高や営業利益率において良好な結果を示していると報告されています。
参照:厚生労働省「今後の雇用政策の実施に向けた現状分析に関する調査研究事業報告書」
■人材定着でお悩みの企業様へ
社内アンケートで離職の原因を把握したら、次は優秀な人材の確保が重要です。カラフルエージェントでは、長期定着が期待できるドライバーをご紹介し、入社後のアフターサポートで離職防止にも努めています。人材定着でお困りの際は、ぜひご相談ください。
▼カラフルエージェントへのお問い合わせはこちら
2.社内アンケート実施前に押さえるべき6つの準備項目
6つの準備項目
成功する社内アンケートの実施には、入念な事前準備が欠かせません。ここでは、必ず押さえておきたい6つの準備項目について解説します。
目的の明確化
まずは、アンケート実施の目的を明確にしましょう。目的が曖昧なままでは、設問設計が適切にできず、期待する結果を得られません。以下のように、具体的で明確な目的設定が必要です。
- 新しく導入した人事制度に対する印象を把握する
- 職場のハラスメント防止のため現状を把握する
- 新入社員の不満や悩みを知る
- 生産性向上のため現場のアイデアを収集するなど
目的の明確化は従業員の参加意欲を高める効果もあります。なぜこのアンケートが必要なのか、どのように活用するのかが伝わることで、協力的な回答を得やすくなるでしょう。
対象者の選定
実施目的に応じて適切な対象者を選定しましょう。全従業員を対象とするか、特定の部署や役職、入社年次に限定するかなど、慎重な検討が必要です。選定の際は、以下の3つの視点を意識してください。
- 率直な意見を集められる人数か
- 目的達成に必要な対象者が含まれているか
- 回答者の心理的安全性は確保されているか
対象者選定では匿名性の確保も重要な要素となります。たとえば、ある部署の10人程度といった少人数を対象とすると、誰が回答したかが特定されやすくなり、回答者が本音を書きづらくなる可能性があるのです。

管理職と一般社員では立場や視点が異なるため、同じ質問でも回答傾向が変わります。アンケートの目的達成に必要な対象者かどうかは、役職も考慮して検討しましょう。
実施期間と頻度
アンケートの実施期間は回答率と回答の質に大きく影響します。一般的な実施スタイルをみていきましょう。
■実施タイミング:繁忙期を避ける
月末や四半期末といった繁忙期は避け、比較的余裕のある時期を選ぶと、質の高い回答を得やすくなります。
■回答期間:1週間から2週間程度
期間が短すぎると回答者が十分に考える時間がなく、長すぎると回答を後回しにされて忘れられるリスクが高まります。
■頻度:年1回から2回程度
NTTコムリサーチの調査によると、年2回以上実施している企業が42.5%、年1回が57.5%となっています。
ただし、新制度導入時や組織変更時には臨時のアンケートを実施するケースも少なくありません。
参照:NTTコムリサーチ「従業員満足度調査」に関する調査結果」
アンケート媒体の選択
社内アンケートの媒体は主にWeb形式、紙面、メール添付の3つから選択します。重要なのは、従業員の働き方や職場環境に合わせて最適な媒体を選ぶことです。
以下の表を参考に、自社にあったアンケート媒体を選択しましょう。
| 形式 | おすすめの環境 | メリット |
|---|---|---|
| Web | デスクワークが中心の部署 | ・回答データの集計が簡単 ・普段使用しているパソコンから気軽に回答できる |
| 紙面 | 工場の製造ラインや建設現場 高齢の従業員が多い職場 | ・PCへのアクセスが限られる環境では紙面形式が現実的 ・高齢の従業員が多い職場では、慣れ親しんだ紙面形式の方が回答しやすい場合も |
回答形式の設計
回答形式は主に選択式と自由記述式の2つがあります。
選択式
■「はい・いいえ」や5段階評価から選ぶ方式
リッカート尺度(「全く満足していない」から「非常に満足している」までの段階評価)など
≪メリット≫
回答者の負担が少なく集計が簡単
全体的な傾向を把握するのに適している
自由記述形式
■回答者が意見を文章で記述する方式
≪メリット≫
具体的な改善提案など詳しい意見を集められる
※集計に時間がかかるため、自由記述は2~3個程度にとどめるとよい
効果的なアンケートにするためには、選択式を8~9割、自由記述式を1~2割程度の割合で設計するとよいでしょう。
匿名か記名かの判断
匿名・記名の選択は回答の質に大きく影響する可能性がある検討事項です。
■匿名方式
ハラスメントや職場環境の改善など、デリケートな内容を扱う場合は匿名での実施が望ましい
≪メリット≫
回答者が心理的な負担を感じにくく、率直な意見を集めやすい
■記名方式
≪メリット≫
回答内容について個別の確認や詳しい聞き取りができる
※ただし、人事評価への影響を懸念して本音を述べにくい傾向がある
匿名アンケートであっても、部署や年次などの基本情報から個人が特定される可能性を懸念する従業員も少なくありません。そのため、個人特定のリスクについて事前に説明し、必要に応じて該当する基本情報を非公開にする配慮も必要です。
3.従業員の本音を引き出す7つのコツ
本音を引き出す
7つのコツ
従業員の率直な意見を収集するための7つのコツを、実践的なポイントとともにご紹介します。
心理的安全性を確保する環境づくり
心理的安全性とは、自分の意見を率直に発言できる環境のことです。社内アンケートで本音を引き出すためには、この心理的安全性の確保が最も重要です。
■具体的には…
- 匿名形式での実施
- 筆跡で特定されないようWebでの実施
- 人事評価に影響しないことを明確に伝えるなど
誰がアンケート結果を閲覧するのか、どのように利用するのかを明記することも大切です。アンケート結果のフィードバック時に個人が特定される可能性がある場合は、該当する基本情報を非公開とする旨を事前に説明しておきましょう。
▼あわせて読みたい
心理的安全性は、組織を強める重要なポイントです。こちらの記事では、具体的な手法や実践的なアプローチ方法について詳しく解説しています。
経営層の本気度を伝える方法
社内アンケートで本音を引き出すには、経営層が改善に向けた強い意志を示すことが重要です。以下のような施策を取り入れ、経営層の本気度を明確に示しましょう。
- 朝礼や部門会議で経営層から呼びかける
- アンケートの依頼文に社長からのメッセージを添える
- 回答期限が近づいた際に部長から直接声がけするなど
組織が一丸となって取り組む姿勢を示すことで、従業員の協力意識も高まります。「会社が本気で職場環境を改善したい」「従業員の声に真剣に耳を傾ける」という経営層の姿勢が伝わることで、従業員も安心して本音を話せるようになるでしょう。

形式的な調査に終わらせないという意思表示が、従業員の信頼感を高めます。
質問設計で回答を誘導しない工夫
質問文の表現によっては、回答者を特定の回答に誘導してしまう恐れがあります。
■避けるべき表現例:
「会社としては○○することを検討していますが、あなたは賛成ですか?」
「一般的に〜と言われていますが、あなたもそう思いますか?」など
中立的な質問設計を心がけ、「はい」「いいえ」だけでなく「どちらでもない」といった選択肢も設けることが重要です。質問文が中立的な立場で作成できているかを客観的に確認するため、他部門の担当者にチェックを依頼することも有効な方法です。
回答しやすい質問数への絞り込み
アンケートの質問項目を検討する際、「あれも聞きたい、これも聞きたい」と欲張りすぎるのは禁物です。多すぎる設問は回答者の負担となり、回答率の低下や回答の信頼性を損ねかねません。アンケートの目的に照らして、優先順位の高い質問に絞り込みましょう。
まずは幅広く質問項目を洗い出し、それらの整理・統合作業をしてください。類似した質問をまとめ、アンケートの趣旨から外れた設問は除外します。
40問を超えてしまう場合には、カテゴリを分けて複数ページに分散させる工夫も必要です。
分かりやすい告知と説明
アンケートの告知方法は回答率を大きく左右する重要なポイントです。記載すべき内容は以下のとおりです。
■告知メールについて
≪件名≫
- 所要時間を明記する
≪本文≫
- アンケートの実施目的
- 回収したらどのように使うのか
- 従業員へのフィードバック方法など
メールには匿名性が担保されている点や、回答内容が人事評価に影響しない点なども明記します。これらを事前にきちんと伝えることで、協力してくれる従業員が増え、回答率も高まるでしょう。

いきなりメールを配信しても他の業務メールに埋もれてしまったり、迷惑メールと勘違いされたりする可能性があるため、部門長の会議や朝礼などで事前に予告しておくことが大切です。
回答率を上げるリマインド戦略
設定した期間内により多くの回答を集めるため、適切なタイミングでリマインドを実施しましょう。特に終了直前の声かけは回答数を増やすのに効果的です。
効果的なリマインドのタイミングは、実施期間の中間地点と終了3日前、終了前日の3回程度が目安です。ただし、あまり頻繁にリマインドを送ると従業員にプレッシャーを与えてしまう可能性もあるため、適度な頻度で実施してください。
未回答者を特定できる仕組みがある場合は、対象者を絞ってリマインドを送ることで、より効率的な回答率向上を図ることができます。
結果を必ず行動につなげる
アンケートで得た情報は必ず組織課題の改善につなげましょう。「意見が反映された」「会社が動いてくれた」と感じられると、従業員の組織に対する信頼感が高まり、次回調査への協力も得やすくなります。
分析結果に基づく具体的な改善行動と、その進捗状況を従業員にフィードバックすることで、アンケートの価値を最大限に活用しましょう。PDCAサイクルを意識した継続的な改善活動につなげることが重要です。
▼あわせて読みたい
フィードバックスキルをさらに深めたい方におすすめの記事です。効果的なフィードバックの与え方から、相手のモチベーションを高める実践的な手法まで体系的に学べます。
■従業員の本音を聞いて組織改善を実現
社内アンケートで従業員の不満要因が明確になったら、根本的な解決策を検討しましょう。特に人材不足が原因の場合、即戦力となる有資格者ドライバーの採用が効果的です。カラフルエージェントでは登録者の91%以上が有資格者で、即日ご紹介が可能です。
▼カラフルエージェントへのお問い合わせはこちら
4.効果的な質問文の作り方|ハーズバーグの二要因理論を活用

心理学の「ハーズバーグの二要因理論」を活用する、従業員の満足度を正確に測定できる質問設計の方法をご紹介します。
二要因理論の基本概念
ハーズバーグの二要因理論とは、仕事における満足と不満足を引き起こす要因はそれぞれ異なるという理論です。満足に関わる「動機づけ要因」と不満足に関わる「衛生要因」の2つに分類されており、社内アンケートに応用することで、それぞれの要因を効果的に特定できます。
| 動機づけ要因 従業員のモチベーションを高める要素 | 達成感、承認、仕事内容の魅力、責任、昇進の機会など |
| 衛生要因 不満を防ぐための基本的な要素 | 給与、労働条件、職場環境、人間関係、会社の方針など |
二つの要因に分けて項目を作成することで、モチベーションを高める施策と不満を取り除く施策を明確に区分して考えやすくなるのです。
動機づけ要因に関する質問設計
動機づけ要因に関する設問は、次のような質問を3~5段階評価で確認します。
■仕事の達成感
- 現在の業務に達成感を感じていますか
- 自分の成長を実感できる機会がありますかなど
■承認と評価
- 上司から適切な評価を受けていますか
- チーム内で自分の意見が尊重されていますかなど
■キャリア展望について
- 今の仕事を通じて成長できていますか
- キャリアアップの機会は十分にありますかなど
これらの質問に対して自由記述欄を設けることで、より具体的な意見も収集できるでしょう。動機づけ要因の調査により、従業員のやりがいやモチベーション向上につながる具体的な施策を立案できます。
衛生要因に関する質問設計
衛生要因に関する質問では、次のような質問を設計します。
■労働環境
- 職場の設備は快適ですか
- 残業頻度は適切ですか
- 安全対策は十分に講じられていますかなど
■制度と待遇
- 給与水準に満足していますか
- 評価制度は公平だと感じますか
- 福利厚生制度は充実していますかなど
■職場の人間関係
- 上司とのコミュニケーションは円滑ですか
- 同僚との協力体制は整っていますか
- 職場の雰囲気は良好ですかなど
これらの質問に対する回答を分析すると、職場の基本的な課題を具体的に特定できるため、不満の解消に直結する改善策を検討できます。
5.すぐに使える質問例100選!分野別完全リスト

4章で解説した「二要因理論」に基づき、質問例を「動機づけ要因」と「衛生要因」に分けてご紹介します。
動機づけ要因に関する質問例(満足度を高める要素)
仕事内容・やりがいに関する質問(20選)
- 現在の業務内容に満足していますか
- 仕事に達成感を感じることがありますか
- 自分の能力を活かせる仕事ができていますか
- 業務の難易度は適切だと思いますか
- 仕事の裁量権は十分に与えられていますか
- 新しいことに挑戦する機会がありますか
- 自分の意見やアイデアが業務に反映されることがありますか
- 仕事を通じて成長を実感できますか
- 担当業務の重要性を理解していますか
- 目標設定は明確で達成可能だと思いますか
- 業務の進め方について十分な説明を受けていますか
- 創意工夫を活かせる環境がありますか
- 専門性を高める機会が提供されていますか
- 他部署との連携はスムーズに行えていますか
- 業務改善の提案をしやすい環境がありますか
- 仕事の成果が適切に評価されていると感じますか
- 責任の重さと権限のバランスは適切ですか
- 業務の優先順位は明確に示されていますか
- 仕事を通じて社会貢献を実感できますか
- 現在の職務に誇りを持っていますか
経営・組織風土に関する質問(10選)
- 会社の経営方針に共感できますか
- 会社の将来性に期待が持てますか
- 経営陣の方針は明確に伝わっていますか
- 会社の社会的責任を果たしていると思いますか
- 組織の風通しの良さを感じますか
- 会社の価値観や企業文化に共感できますか
- 変化に対応できる柔軟な組織だと思いますか
- 従業員の意見が経営に反映される仕組みがありますか
- 会社に誇りを持っていますか
- 長期的に働き続けたい会社だと思いますか
衛生要因に関する質問例(不満を解消する要素)
職場環境・人間関係に関する質問(20選)
- 職場の設備や環境は働きやすいですか
- オフィスの温度や照明は適切ですか
- 必要な備品や機器は充実していますか
- 職場の清潔さは保たれていますか
- 安全対策は十分に講じられていますか
- 騒音レベルは仕事に支障がない程度ですか
- プライベートスペースは確保されていますか
- 同僚との関係は良好ですか
- チーム内の協力体制は整っていますか
- 職場の雰囲気は良好だと感じますか
- 困ったときに相談できる人がいますか
- 職場でのコミュニケーションは活発ですか
- 新人や転入者を受け入れる雰囲気がありますか
- ハラスメントのない職場環境だと思いますか
- 多様性が尊重される職場だと感じますか
- 職場でのストレスは適度な範囲内ですか
- 休憩時間は十分に確保されていますか
- 職場の情報共有は適切に行われていますか
- 他部署との関係は円滑ですか
- 職場での人間関係にストレスを感じることはありますか
上司・マネジメントに関する質問(15選)
- 直属の上司との関係は良好ですか
- 上司からの指導やアドバイスは適切ですか
- 上司は部下の話をよく聞いてくれますか
- 上司からの評価は公正だと思いますか
- 上司は部下の成長を支援してくれますか
- 上司とのコミュニケーション頻度は適切ですか
- 上司からの業務指示は明確ですか
- 上司は部下の意見を尊重してくれますか
- 上司のリーダーシップに満足していますか
- 上司は適切な権限移譲を行っていますか
- 上司からのフィードバックは建設的ですか
- 上司は部下の個性や特徴を理解していますか
- 上司との面談の機会は十分にありますか
- 上司は職場の問題解決に積極的ですか
- 上司のマネジメント手法に満足していますか
処遇・評価制度に関する質問(15選)
- 現在の給与水準に満足していますか
- 賞与の支給基準は明確だと思いますか
- 昇進・昇格の基準は公正だと感じますか
- 人事評価制度は適切に運用されていますか
- 評価結果についての説明は十分ですか
- 能力や成果に見合った処遇を受けていますか
- 同業他社と比べて待遇は適切だと思いますか
- 評価制度の透明性は確保されていますか
- 目標管理制度は効果的に機能していますか
- 昇進の機会は平等に提供されていますか
- 給与改定のタイミングは適切ですか
- 諸手当の支給基準は明確ですか
- 退職金制度は充実していると思いますか
- 年収に見合った仕事内容だと感じますか
- 処遇に関する不満や要望を伝える機会がありますか
福利厚生・制度に関する質問(10選)
- 有給休暇は取りやすい環境ですか
- 育児・介護支援制度は充実していますか
- 健康管理支援は十分に提供されていますか
- 研修・教育制度は充実していますか
- 社員食堂や休憩施設は満足できる水準ですか
- 社員旅行やイベントは充実していますか
- 住宅手当や交通費などの諸手当は適切ですか
- 退職金制度や企業年金は安心できる内容ですか
- 健康診断や人間ドックなどの健康管理は充実していますか
- 自己啓発支援制度は活用しやすいですか
業務負荷・ワークライフバランスに関する質問(10選)
- 現在の業務量は適切だと思いますか
- 残業時間は許容できる範囲内ですか
- 仕事とプライベートのバランスは取れていますか
- 業務上のストレスは適度な範囲内ですか
- 休日出勤の頻度は適切ですか
- 有給休暇を計画的に取得できていますか
- 長時間労働による健康への不安はありますか
- 業務の効率化が図られていると感じますか
- 働き方の柔軟性(在宅勤務など)は確保されていますか
- 現在の働き方に満足していますか
参考:(公財)日本生産性本部 「従業員満足度調査「Niser(ナイサー)ES」」
6.社内アンケート実施時の注意点と失敗を避けるポイント

よくある失敗を避け、効果的なアンケートを実現するためのポイントを解説します。
個人特定リスクへの配慮
匿名アンケートであっても、基本情報の組み合わせによって個人が特定される可能性があります。特に少人数部署では、部署名、年齢、勤続年数などの情報から個人を特定しやすくなるため注意が必要です。
このリスクを軽減するため、部署は「営業系」「技術系」といった大まかな分類にする、年齢は年代区分にする、勤続年数は「3年未満」「3年以上10年未満」といった範囲で設定するなどの工夫が求められます。
また、個人特定の可能性がある場合は、該当する基本情報を集計結果から除外することを事前に従業員に説明しておくことも重要です。
データの適切な管理と活用
収集したアンケートデータは適切に管理・活用する必要があります。以下でみていきましょう。
【情報セキュリティの観点】
- 回答データの暗号化
- アクセス権限の制限
- セキュアなサーバーでの保管など
【データ保存期間】
- 法的要件や社内規定に従って明確に定める
- 期間経過後は確実にデータを廃棄する
【分析結果の取り扱い】
- 個人を特定できる情報が含まれていないかを十分にチェックする
- アンケート結果は経営層だけでなく従業員にもフィードバックする
【データの活用】
- 部署別や年代別の分析を行い、具体的な改善策の立案につなげる
- PDCAサイクルを回し、継続的な改善活動の基盤として活用する
個人情報保護のためのチェックリスト
従業員が安心して回答できるよう、以下の点を確認しましょう。
☐ 目的外利用の禁止
→アンケートの目的、データの利用範囲を事前に明記しているか?
☐ 匿名性の担保
→回答によって個人が特定されない設計になっているか?(例:部署を「営業系」など大分類にする)
☐ 不利益がないことの明示
→回答内容が人事評価などに一切影響しないことを明確に伝えているか?
☐ データ管理責任者の明記
→誰がどのようにデータを管理するのかを提示しているか?
☐ 保存期間と廃棄方法
→データの保存期間と、期間終了後の廃棄方法を定めているか?
7.おすすめの社内アンケートツール

効率的なアンケート実施を支援する、おすすめのツールと選び方をご紹介します。
無料ツール|Googleフォームなど
「手軽にアンケートを試してみたい」と考えている企業には、無料ツールがおすすめです。特にGoogleフォームは最も手軽に利用できる無料ツールの代表例です。以下で特徴をみていきましょう。
- 無料で誰でも全機能を利用できる
- PCとスマートフォンの両方に対応
- 匿名回答の設定が可能
- 自動集計でリアルタイムに回答を確認
- 回答結果をスプレッドシートとして出力
その他の無料ツールとしては、Microsoft Formsやフォームメーラーなどがあります。ただし、これらの無料ツールは基本的な機能は十分に備えているものの、高度な分析機能や大規模なアンケート実施には限界があることを理解しておきましょう。
有料ツール|機能と投資対効果
有料の社内アンケート専用システムは、以下のような無料ツールでは実現できない高機能性を持っています。
- 高度な分析機能
クロス集計、統計解析、グラフィカルなレポート作成などが可能 - セキュリティ
企業レベルの暗号化、アクセス制御、監査ログなどが充実 - 大規模なアンケート実施にも対応可能
数千人規模の従業員を対象とした調査も安定して実行 - サポート体制も充実
アンケート設計から分析まで専門スタッフによるサポート
コスト面では月額数万円から数十万円の費用がかかりますが、人事担当者の作業時間削減やより精度の高い分析結果、継続的な改善サイクルの実現などを考慮すると、中長期的には十分な投資対効果が期待できるでしょう。

組織規模、実施頻度、求める機能レベルを総合的に検討して導入判断してください。
自社に最適なツール選択のポイント
自社に最適なツールを選択するためには、組織規模、予算、機能要件の3つの観点から検討します。
□組織規模
- 従業員数100名以下→無料ツールでも対応可能
- 従業員数1000名以上→有料ツールの導入を検討すべき
□予算面
年間のアンケート実施コスト(人件費を含む)と比較して判断
□機能要件
- 基本的なアンケート作成と集計のみ→無料ツールで充分な機能が使える
- 高度な分析や部署別レポートが必要→有料ツールの方が便利
既存システムとの連携性、セキュリティレベル、サポート体制なども考慮してください。
導入時の注意点として、まずは小規模なテストアンケートを実施し、使い勝手や機能を確認するとよいでしょう。長期的な視点では、将来的な組織拡大や機能拡張にも対応できるツールを選択することで、継続的な活用につながります。
■社内改善と並行して人材確保も重要
社内アンケートによる組織改善と並行して、新たな戦力の確保も考えましょう。カラフルエージェントなら面接調整から条件交渉まで代行し、工数をかけずにスムーズな採用活動が可能です。初期費用・月額費用は一切不要の成功報酬制で安心してご利用いただけます。
▼カラフルエージェントへのお問い合わせはこちら
▼あわせて読みたい
社内アンケートで職場環境を改善したら、その効果を数値として確認しましょう。離職率の計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
8.社内アンケートで組織力向上を実現しよう
社内アンケートは、従業員の声を経営に反映し、組織の持続的な成長を支える重要な経営ツールです。従業員が抱える課題や不満を解消し、働きやすい職場環境を整えることで、働きがいのある組織づくりを実現できます。
大切なのは、アンケートの実施自体を目的にせず、得られた結果を具体的な改善施策につなげることです。従業員一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、共に成長できる組織を目指して、ぜひ社内アンケートを有効活用してください。
▼あわせて読みたい
従業員の声を正しく把握するためには、社内コミュニケーションの改善も欠かせません。こちらの記事では、成功事例を交えながら、すぐに実践できる具体的な施策を詳しく解説しています。
■継続的な組織成長を支える人材戦略
社内アンケートで組織課題を解決した後は、持続的な成長を支えるための人材確保が鍵となります。カラフルエージェントでは、全国のドライバー登録者の中から貴社の条件に最適な人材を迅速にマッチング。地方企業様でも安心してご利用いただけるサポート体制を整えています。
▼カラフルエージェントへのお問い合わせはこちら