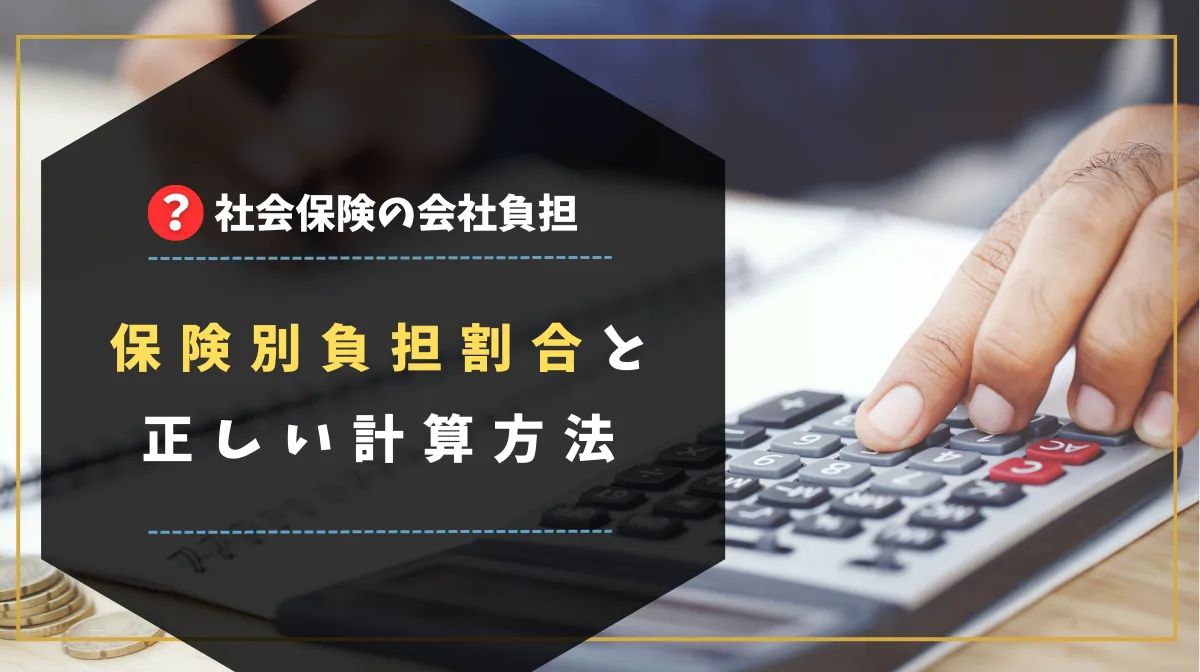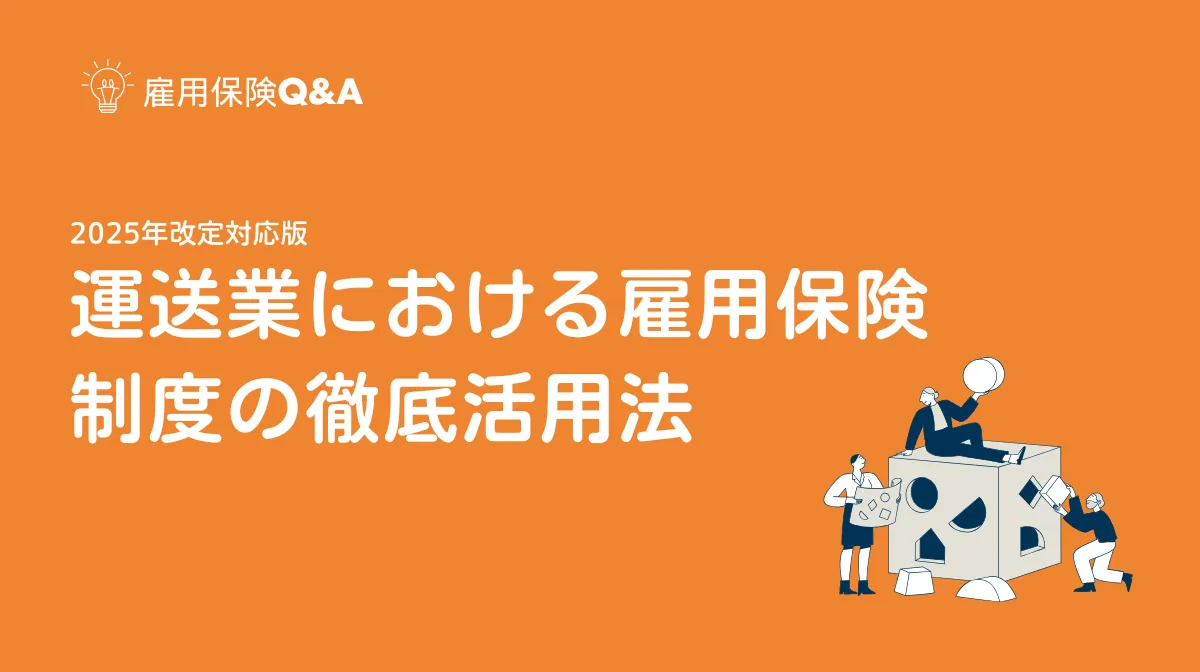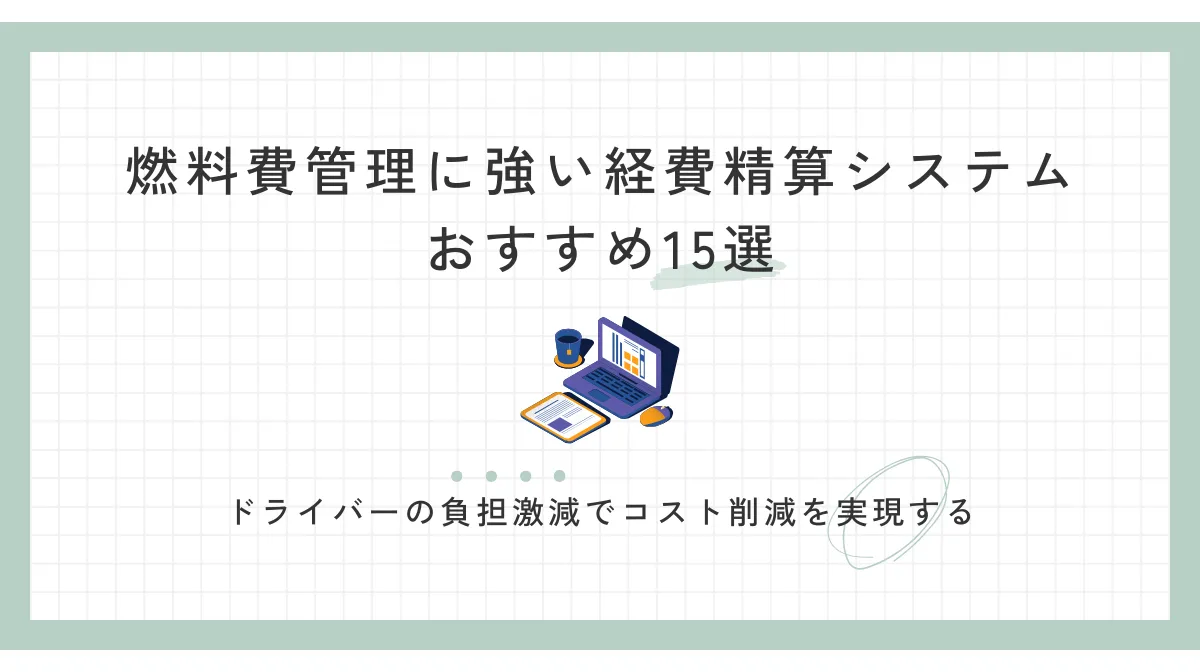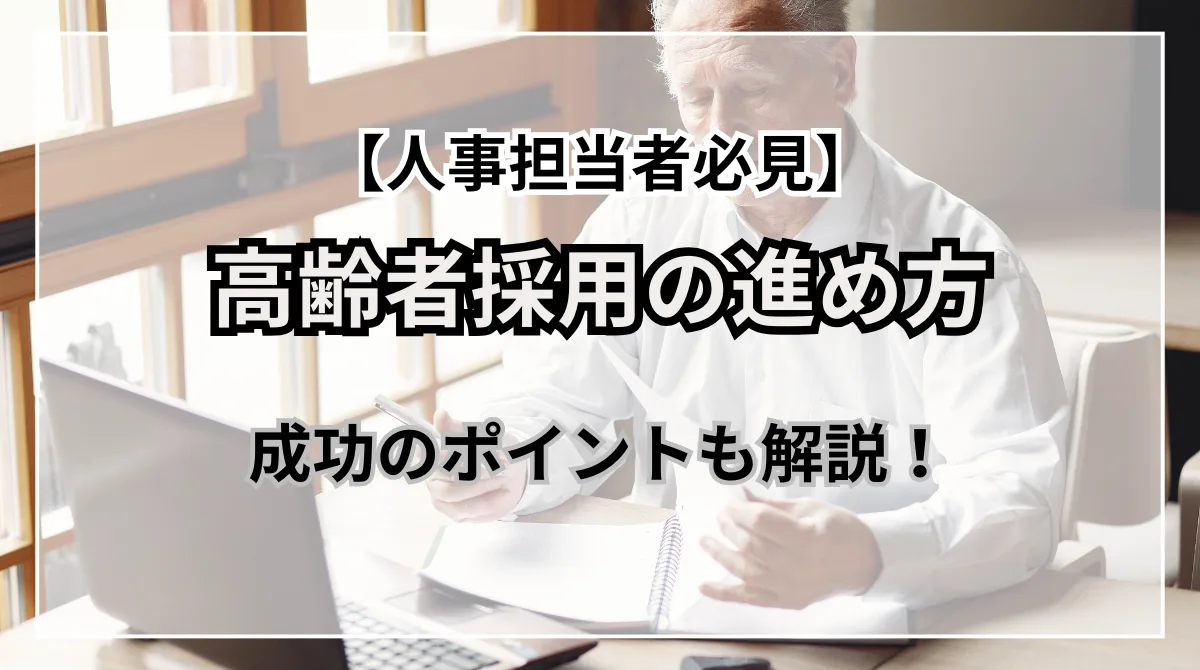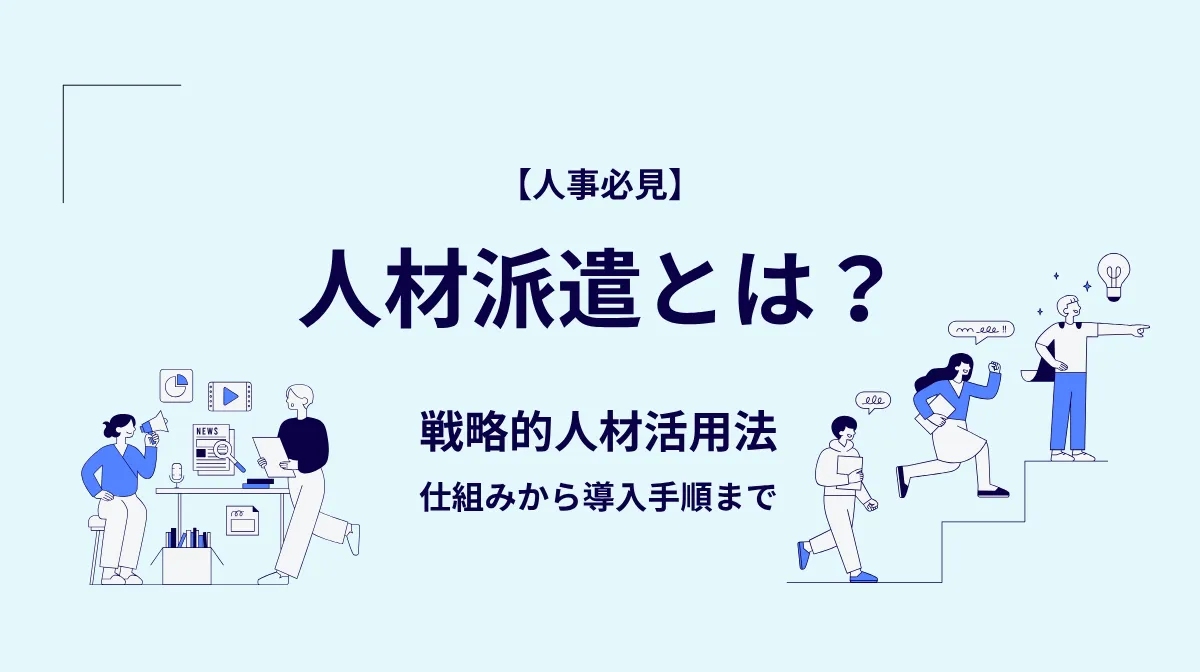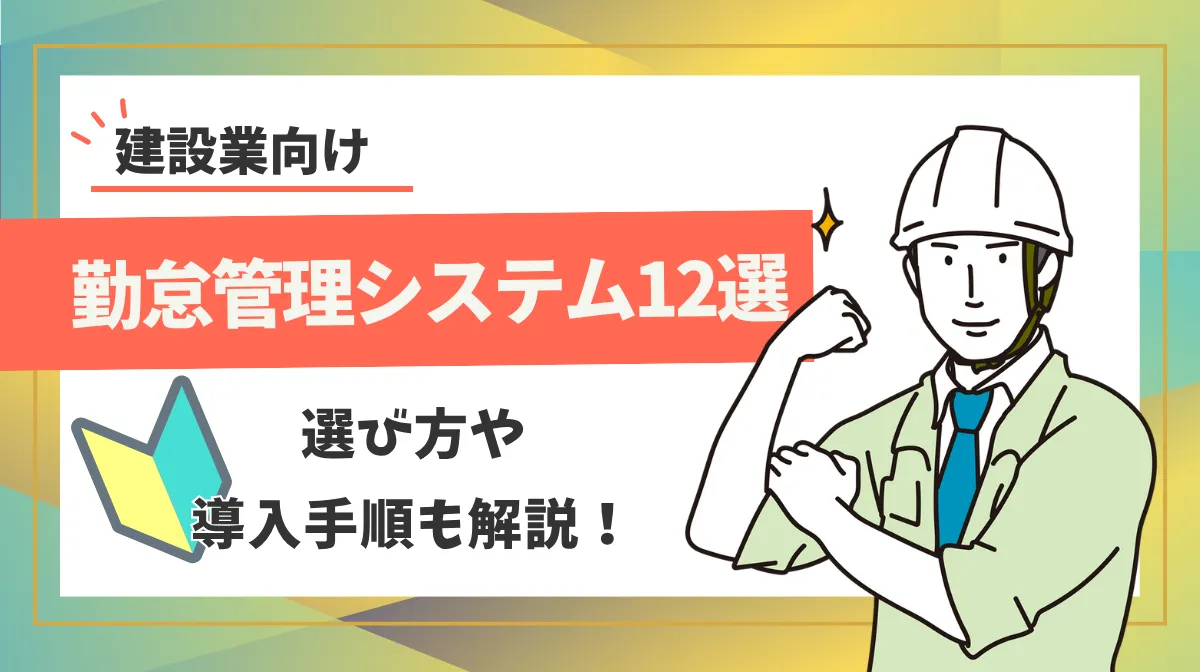「社会保険料の会社負担って、実際にはいくら払っているんだろう?」
「計算方法が複雑で、本当に正しく処理できているか不安…」
こうした疑問を抱えている人事・総務担当者の方も多いのではないでしょうか。
社会保険料は、従業員の給与から天引きする分と、会社が直接負担する分に分かれており、その仕組みを正しく理解することは、適切な給与計算に欠かせません。しかし、5つの保険ごとに負担割合が異なり、料率の改定も定期的に行われるため、常に最新情報を把握するのは容易ではありません。
本記事を読むことで、社会保険料の会社負担に関する疑問を解消できます。
会社が負担する社会保険料の合計額は、従業員の給与(額面)のおおよそ15%〜16%が目安となります。まずはこの数字を念頭に、詳しい内訳を見ていきましょう。
- 社会保険料の会社負担額を正確に把握でき、人件費シミュレーションの精度が向上する
- 各保険の負担割合と計算方法を理解し、給与提示時の説明力と信頼性がアップする
- 社会保険料を軽減する手法を知ることで、採用コストの最適化と競争力強化が実現できる
1.社会保険の会社負担とは?基本的な仕組みを理解しよう

社会保険料の会社負担制度は、従業員の生活保障と企業の社会的責任を両立させる重要な仕組みです。ここでは基本的な考え方を確認しましょう。
社会保険料は企業と従業員で分け合う制度
社会保険料は、原則として企業と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」の仕組みになっています。
■具体例:健康保険料が月額2万円の場合
従業員が1万円を給与から天引きされ、残りの1万円を会社が負担する
この制度により、従業員の保険料負担を軽減しつつ、企業も社会保障制度を支える役割を担います。
会社負担が必要な理由と法的根拠
健康保険法や厚生年金保険法などの法律により、事業主には保険料の半額負担が義務付けられています。これは、社会保障制度の安定的な運営と労働者の福祉を高めるための仕組みです。
また、企業が社会保険料を適切に負担することは、企業自身にとっても次のようなメリットがあります。
従業員の健康維持や老後の生活保障を支える
↓
従業員の安心感が高まる
↓
結果として生産性向上や人材定着につながる
強制適用事業所の範囲と加入義務
社会保険の加入義務は事業所の形態によって異なります。
| 法人事業所(株式会社など) | 従業員数に関係なく社会保険への加入義務がある |
| 個人事業所 | 常時5人以上の従業員を雇用している場合に強制適用 |
| 農林水産業や一部のサービス業など | 適用除外業種 ※法改正により適用範囲が拡大中 |
加入義務を怠った場合は、追徴課税や延滞金が課される可能性があるため注意が必要です。
2.社会保険5種類の会社負担割合一覧
社会保険等の会社負担割合
🏥 健康保険
👵 厚生年金保険
🧑⚕️ 介護保険 (40歳以上)
📄 雇用保険 (一般)
👷 労災保険
👶 子育て拠出金
社会保険は5つの保険から構成されており、それぞれ異なる負担割合が設定されています。正確な理解のために各保険の特徴を確認しましょう。
健康保険料:会社と従業員で50%ずつ負担
健康保険料は労使折半の原則に基づき、会社と従業員が50%ずつ負担します。協会けんぽの場合、都道府県ごとに料率が設定されており、例えば東京都では9.98%となっています。
■具体例:標準報酬月額30万円の従業員の場合(東京都)
30万×0.0998=健康保険料総額29,940円
29,940÷2=14,970円
会社負担:14,970円 従業員負担:14,970円
健康保険組合に加入している企業では、組合独自の料率が適用されるため、協会けんぽよりも負担が軽減される場合があります。
参考:全国健康保険協会|令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)
厚生年金保険料:18.3%を労使で半分ずつ
厚生年金保険料は全国一律で18.3%の料率が適用され、これを会社と従業員で半分ずつ負担します。この料率は2017年9月から固定されており、2025年現在も変更の予定はありません。
■具体例:標準報酬月額30万円の従業員の場合
30万×0.183=厚生年金保険料総額54,900円
54,900円÷2=27,450円
会社負担:27,450円 従業員負担:27,450円
厚生年金保険料は社会保険料の中でも負担額が大きく、人件費に占める割合も高いため、給与設計時には十分な検討が必要です。
介護保険料:40歳以上のみ対象で労使折半
介護保険料は40歳以上の従業員のみが対象となり、健康保険料に上乗せして徴収されます。2024年度の料率は1.60%で、これを会社と従業員が半分ずつ負担します。
■具体例:標準報酬月額30万円の40歳従業員の場合
30万×0.016=介護保険料総額4,800円
4,800円÷2=2,400円
会社負担:2,400円 従業員負担:2,400円
介護保険料は従業員が40歳に到達した月から徴収が開始され、65歳に到達する月の前月で終了します。年齢到達のタイミングでの処理漏れに注意しましょう。
雇用保険料:会社負担の方が多い仕組み
雇用保険料は他の社会保険と異なり、会社負担の方が従業員負担よりも大きく設定されています。また、業種ごとに料率が異なる点も大きな特徴です。
| 業種 | 料率 | 従業員負担 | 会社負担 |
|---|---|---|---|
| 一般事業 | 1.55% | 0.6% | 0.95% |
| 建設業 | 2.05% | 0.7% | 1.35% |
| 農林水産業 | 2.30% | 0.7% | 1.60% |
雇用保険料は標準報酬月額ではなく、実際の賃金総額に料率を乗じて計算してください。
▼あわせて読みたい
以下の記事では、ドライバー業界特有の勤務形態を踏まえた雇用保険料の詳細な計算方法や給付制度について解説しています。実務に即した手続き方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
労災保険料:100%会社負担
労災保険料は唯一、全額を会社が負担する保険料です。従業員の給与からは一切控除されません。料率は業種の危険度に応じて設定されており、事務職では0.25%、建設業では0.9~1.1%など大きな差があります。
労災保険は業務上の災害から従業員を守る制度であり、事業主の安全配慮義務の一環として位置づけられています。
子ども・子育て拠出金:100%会社負担
労災保険料の他に、事業主が全額を負担するものとして「子ども・子育て拠出金」があります。
これは厚生年金保険の被保険者を対象に、標準報酬月額と標準賞与額に拠出金率(令和6年度は0.36)を乗じて計算され、児童手当などの財源となります。社会保険料の納付の際に、厚生年金保険料とあわせて納付します。
3.会社負担額の具体的な計算方法

社会保険料の正確な計算には標準報酬月額の理解が不可欠です。具体的な計算方法を step by step で確認していきましょう。
標準報酬月額を使った計算の基本
標準報酬月額とは、従業員の報酬を1~50等級(厚生年金は1~32等級)に区分した金額のことです。毎年4月から6月までの3ヶ月間に支払われた報酬の平均額をもとに決定され、原則として1年間同じ金額が適用されます。
■具体例:4月25万円、5月28万円、6月32万円の報酬があった場合
(25万+28万+32万)÷3ヶ月=平均28.3万円の報酬
▼等級表に照らし合わせると≪標準報酬月額30万円≫
この標準報酬月額に各保険の料率を乗じることで、保険料を算出します。

標準報酬月額の報酬区分は、日本年金機構のHPにある「厚生年金保険料額表」で確認できます。
賞与にかかる会社負担の計算方法
賞与についても社会保険料の対象となり、標準賞与額に基づいて計算されます。標準賞与額は実際の賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額で、年度の累計上限は健康保険が573万円、厚生年金が150万円です。
■具体例:夏季賞与50万円の従業員の会社負担(東京都)
健康保険料 50万円×9.98%÷2=24,950円
厚生年金保険料 50万円×18.3%÷2=45,750円
介護保険料 50万円×1.60%÷2=4,000円
雇用保険料と労災保険料も同様に計算され、合計約8万円が会社負担額となります。
■ドライバー採用時の社会保険料負担を軽減したい方へ
社会保険料の負担増加に備え、より効率的な採用活動が重要です。カラフルエージェントなら有資格者91%以上の即戦力ドライバーを成功報酬型でご紹介し、採用コストの最適化を実現できます。
▼カラフルエージェントへのお問い合わせはこちら
4.給与計算における社会保険料の処理手順
給与計算における社会保険料の処理手順
1毎月の給与から控除するタイミング
2会社負担分の経理処理
3従業員への給与明細記載事項
社会保険料の処理は給与計算業務の重要な部分です。正しい処理手順を理解し、ミスのない給与計算につなげましょう。
STEP1|毎月の給与から控除するタイミング
社会保険料は「当月分を翌月給与から控除」するのが基本ルールです。例えば、4月分の社会保険料は5月支給の給与から天引きします。このため、入社初月は社会保険料の控除がなく、退職月の保険料は在職中の最後の給与から控除されます。
月末退職の場合は退職月の保険料も控除しますが、月の途中で退職した場合は前月分まで控除し、退職月分は控除不要です。この処理を間違えると、従業員への過大控除や不足控除につながるため、入退社のタイミングには特に注意が必要です。
STEP2|会社負担分の仕訳と経理処理
会社が負担する社会保険料は「法定福利費」として計上します。
■具体例:従業員負担分1万円、会社負担分1万円の健康保険料の場合
| 借方 | 給与手当 20,000円、法定福利費 10,000円 |
| 貸方 | 現金 18,000円、預り金 10,000円、未払金 10,000円 |
預り金は従業員から預かった保険料、未払金は会社負担分の保険料を表します。社会保険料の納付期限は翌月末日のため、適切なキャッシュフロー管理に努めましょう。

法定福利費は人件費の一部として損金算入できるため、税務上のメリットもあります。
▼あわせて読みたい
社会保険料以外の経費管理も効率化したい場合は、燃料費をはじめとした各種経費の精算システム導入がおすすめです。以下の記事では、運送業に特化したシステムを厳選して紹介しています。
STEP3|従業員への給与明細記載
給与明細には社会保険料の控除額を明記する義務があります。健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料を分けて記載し、従業員が内訳を確認できるようにしてください。
また、保険料率の変更があった場合は、従業員向けの説明資料を作成しましょう。「なぜ先月より控除額が増えたのか」といった質問に対して、根拠を示しながら説明できるよう準備しておくことで、従業員との信頼関係を維持できます。
5.社会保険料計算で注意すべき5つのポイント
社会保険料計算で注意すべき5つのポイント
保険料率の年次改定
随時改定と定時決定
短時間労働者の加入
各種手当の取り扱い
端数処理の正しい方法
社会保険料の計算では、制度変更や細かなルールに注意が必要です。実務でよくある注意点を確認しておきましょう。
保険料率の年次改定への対応
健康保険料率と介護保険料率は毎年3月に見直しが行われ、新料率は3月分(4月納付分)から適用されます。協会けんぽでは都道府県ごとに料率が異なるため、支店がある企業は特に注意が必要です。料率改定の通知は例年2月頃に発表されるため、給与計算システムや計算シートの更新を忘れずに行いましょう。
随時改定と定時決定の違い
標準報酬月額は年1回の定時決定(4~6月の報酬平均)で決まりますが、大幅な昇給があった場合は随時改定が必要です。随時改定は、昇給月から3ヶ月連続で報酬が2等級以上変動した場合に行われ、4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。
一方、定時決定は毎年7月に行われ、原則として翌年8月まで同じ標準報酬月額が適用されます。昇給のタイミングによって適用時期が変わるため、正確に把握しましょう。
■具体例:25万円 → 30万円に昇給した場合
- 4月に昇給した場合
7月の定時決定で新しい保険料が適用される - 7月に昇給した場合
7月の定時決定は前の給与で適用される。随時改定を行って10月から新しい保険料が適用される
短時間労働者の加入要件拡大
2024年10月から、厚生年金被保険者数51人以上の企業では短時間労働者の社会保険加入要件が拡大されました。以下の条件をみたす場合は、短時間勤務のパート・アルバイトでも社会保険への加入が必要です。
- 週20時間以上勤務
- 月額賃金8.8万円以上
- 2ヶ月超の雇用見込み
- 学生でない
これまで社会保険に加入していなかった従業員が新たに対象となるため、該当者の洗い出しと加入手続きを適切に行ってください。加入漏れがあると遡及して保険料を納付する必要があり、会社の負担が大幅に増加する可能性があります。
■人事・労務の負担を減らしたいドライバー採用担当者様へ
複雑な社会保険手続きに加えて採用活動まで自社で行うのは大変です。カラフルエージェントなら面接調整から条件交渉まで代行し、工数削減と確実な採用を両立できます。
▼カラフルエージェントへのお問い合わせはこちら
▼あわせて読みたい
人手不足対策として注目される高齢者採用は、社会保険の取り扱いにも注意が必要です。60歳以上の人材活用における採用から定着までのポイントを詳しく解説しています。
通勤手当や各種手当の取り扱い
社会保険料の算定基礎となる報酬には、基本給だけでなく各種手当も含まれます。以下で詳しくみていきましょう。
- 通勤手当
月額15万円まで所得税非課税だが、社会保険料の算定では全額が対象 - 各種手当
残業代、住宅手当、家族手当など
一方、結婚祝い金などの臨時的な支給や年3回以下の賞与は報酬から除外されます。どの手当が報酬に含まれるかは複雑なため、判断に迷った場合は年金事務所に確認するとよいでしょう。
端数処理の正しい方法
社会保険料の端数処理には明確なルールがあります。
■従業員・会社負担分どちらも同様の処理
50銭未満切り捨て・50銭以上切り上げ
ただし、雇用保険料については1円未満の端数を切り捨てるルールとなっており、他の保険料と処理方法が異なるため注意が必要です。端数処理を間違えると、年間を通じて従業員に過大控除や不足控除が発生するため、計算システムの設定も含めて正確に処理しましょう。
6.会社負担軽減のための方法

社会保険料の会社負担を適切に管理することは、人件費の最適化につながります。ここでは、すぐに実践できる負担軽減の方法を解説します。
給与体系の見直しによる最適化
標準報酬月額は等級制になっているため、等級境界を意識した給与設計により負担を軽減できる場合があります。
■具体的には
- 月給を等級にあわせて設定
月給30.5万円と29.5万円では、どちらも標準報酬月額30万円となり、社会保険料は同額。
昇給や新規採用の際の給与設計に活用。 - 定時決定の基準となる4~6月の報酬を調整
この期間の残業時間を他の月に分散させることで、標準報酬月額の上昇を抑制できる。
ただし、労働基準法の範囲内で行う必要があり、従業員の同意も重要です。給与体系の見直しは慎重に検討し、従業員にとってもメリットがある形で実施しましょう。
福利厚生制度の活用
以下のような社会保険料の対象外となる福利厚生を活用することで、実質的な負担軽減が可能です。
- 食事補助(月額3,500円まで)
- 慶弔見舞金
- 研修費用
- 確定拠出年金制度
- 健康診断費用など
これらを充実させることで、従業員満足度を高めながら社会保険料負担を抑制できるでしょう。

福利厚生の設計は税務上の取り扱いも関係するため、税理士や社労士と相談しながら進めることをお勧めします。
雇用形態の多様化による対応
正社員以外の雇用形態を適切に活用することで、社会保険料負担を調整できます。例えば、業務委託契約の場合は社会保険料負担が発生せず、短時間勤務者も一定の条件下では加入義務がありません。
また、正社員の一部を限定正社員や契約社員に変更することで、給与水準を調整し、結果として社会保険料負担を軽減することも可能です。雇用形態の見直しは労働条件の変更を伴うため、従業員との十分な協議が不可欠です。
▼あわせて読みたい
正社員以外の雇用形態を検討する際は、人材派遣の活用も有効な選択肢です。以下の記事では、社会保険料負担の観点も含めた派遣制度の基本から実践的な運用方法まで解説しています。
7.社会保険料滞納のリスクと対処法
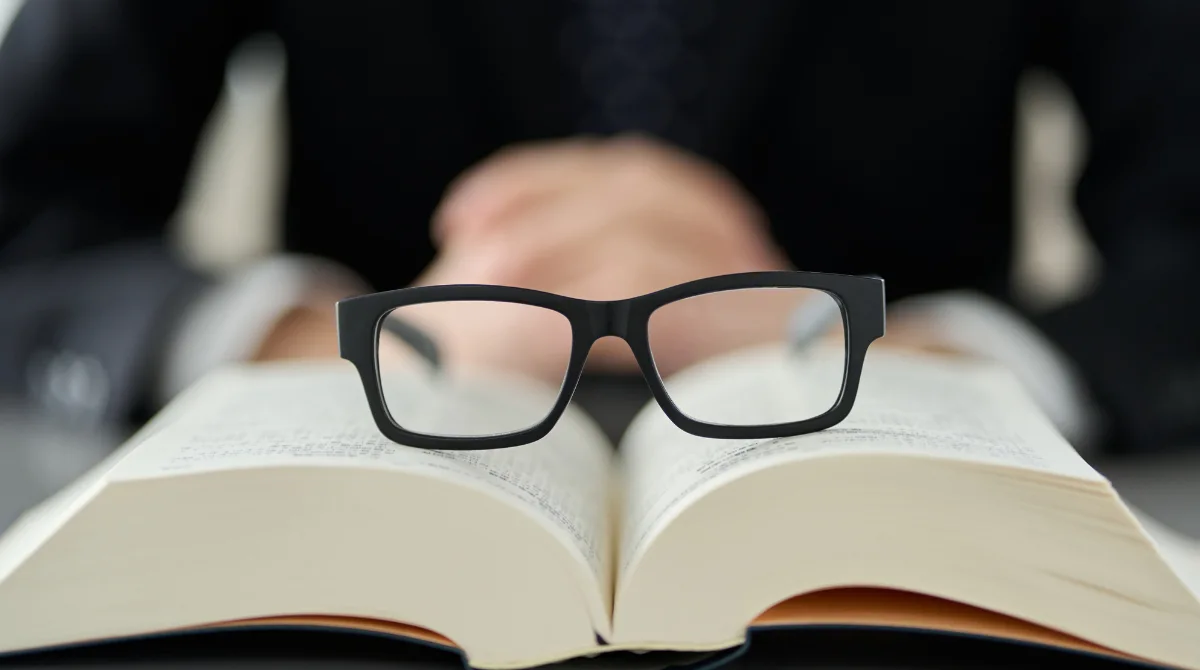
社会保険料の納付は法的義務であり、滞納には重いペナルティが科されます。リスクを理解し、適切な対処法を身につけましょう。
滞納時のペナルティと督促手続き
社会保険料を滞納すると、納期限の翌日から延滞金が発生します。延滞金の利率は年14.6%(納期限から3ヶ月以内は年7.3%)と高額で、滞納期間が長くなるほど負担が重くなります。納期限から約1ヶ月後に督促状が送付され、その後も納付がない場合は催告書や最終催告書が段階的に送られます。
それでも納付しない場合は、預金口座や売掛金の差押え、不動産の公売などの強制執行が行われます。
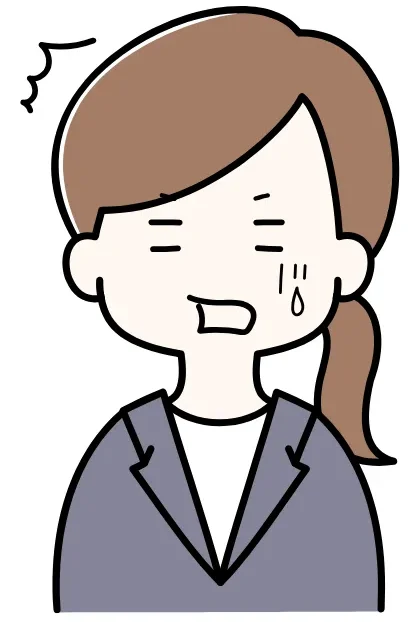
強制執行は事前通知なく実施される場合もあり、事業運営に深刻な影響を与える可能性があります。
■確実な人材確保で経営リスクを回避しませんか
社会保険料の滞納リスクを避けるためにも、安定した事業運営が重要です。カラフルエージェントの成功報酬型サービスなら、採用コストを抑えながら質の高いドライバーを確保できます。
▼カラフルエージェントへのお問い合わせはこちら
資金繰りが困難な場合の相談先
一時的な資金繰り悪化により納付が困難な場合は、早急に年金事務所に相談してください。事情を説明すれば、以下のような制度を利用できる場合があります。
- 分割納付
月々の支払い可能額を設定し、計画的に完納を目指します - 納付猶予
災害や経営悪化などの特別な事情がある場合は、最大1年間の納付猶予を受けられる可能性がある。
ただし、これらの制度を利用するには担保の提供や保証人が必要な場合もあります。放置せずに早期相談することで、より柔軟な対応を受けられる可能性が高まるでしょう。
過去2年間の遡及納付リスク
社会保険の未加入や保険料の未納が発覚した場合、過去2年間に遡って保険料を納付する義務があります。この場合、本来の保険料に加えて延滞金も課されるため、負担額は当初の想定を大幅に上回ります。
特に従業員数の多い企業では、遡及期間の保険料総額が数百万円から数千万円に達することもあり、会社の経営を圧迫する要因となるでしょう。
また、労働基準監督署の調査などをきっかけに未加入が発覚するケースも多く、その場合は他の労務関連法令の違反も同時に指摘される可能性があります。日頃から適正な加入手続きを心がけることが、最も重要な対策といえるでしょう。
8.給与計算システム導入で業務効率化

社会保険料の計算業務を効率化し、ミスを防止するためにはシステム化が有効です。導入のメリットと選定ポイントを確認しましょう。
手計算のリスクとシステム化のメリット
手計算による社会保険料の算出は、計算ミスや料率の更新漏れなど多くのリスクを抱えています。特に従業員数が増加すると、計算作業に要する時間も膨大になり、担当者の負担も重くなるでしょう。作業効率化のためにも、給与計算システムの導入をおすすめします。
■給与計算システムを導入するメリット
- 最新の料率が自動適用される
- 給与明細の自動生成や電子配布により、印刷・配布作業も削減
- 労働保険の年度更新や算定基礎届の作成も自動化
初期投資は必要ですが、人件費削減効果を考慮すると十分に回収可能といえるでしょう。
システム選定時のチェックポイント
給与計算システムを選定する際は、以下のような社会保険料計算機能があるかを確認しましょう。
- 料率の自動更新機
- 随時改定への対応
- 短時間労働者の加入判定機能など
また、他のシステムとの連携性も重要で、勤怠管理システムや会計システムとデータを連携できれば、さらなる効率化が期待できます。

システム導入が初めての場合は、サポート体制も重視しましょう。操作方法のサポートが充実しているベンダーを選ぶことで、安心して運用を開始できます。
導入後の運用体制づくり
システム導入後は、適切な運用体制の構築が成功の鍵です。以下でポイントをみていきましょう。
【導入前】
ベンダーが提供する研修に積極的に参加し、システムの機能を十分に理解する
複数の担当者がシステムを操作できるよう、操作マニュアルを整備する
【導入後】
定期的なデータバックアップや料率更新の確認作業をルーチン化する
法改正や制度変更があった場合の対応手順も事前に決めておく
システムは導入して終わりではなく、継続的な改善により真価を発揮します。
▼あわせて読みたい
給与計算システムと連携する勤怠管理システムの導入も検討されている場合は、業界特化型システムの選定ポイントをご参考ください。建設業向けですが運送業にも応用できる内容です。
9.人事・総務担当者のための社会保険料管理ガイド
本記事では、社会保険料の会社負担について、基本的な仕組みから計算方法、実務上の注意点まで幅広く解説しました。社会保険料の計算は、法改正や複雑なルールにより担当者にとって大きな負担となりがちです。だからこそ、システム化による効率化を進め、ミスの防止と業務の軽減を図りましょう。
人事・総務担当者は、従業員の生活を支える社会保障制度を企業の中で担う存在です。給与の約15%にあたる会社負担は決して小さな額ではありませんが、正しい知識を持つことで適切に管理できます。正確な知識と確実な処理を積み重ね、従業員と企業双方にとって最適な社会保険料管理を実現していきましょう。
■ドライバー採用のお悩みもワンストップで解決
社会保険料の適正管理と並行して、優秀なドライバーの確保も重要な経営課題です。カラフルエージェントなら全国対応で即日紹介、離職防止サポートまで一貫してお任せいただけます。
▼カラフルエージェント へのお問い合わせはこちら