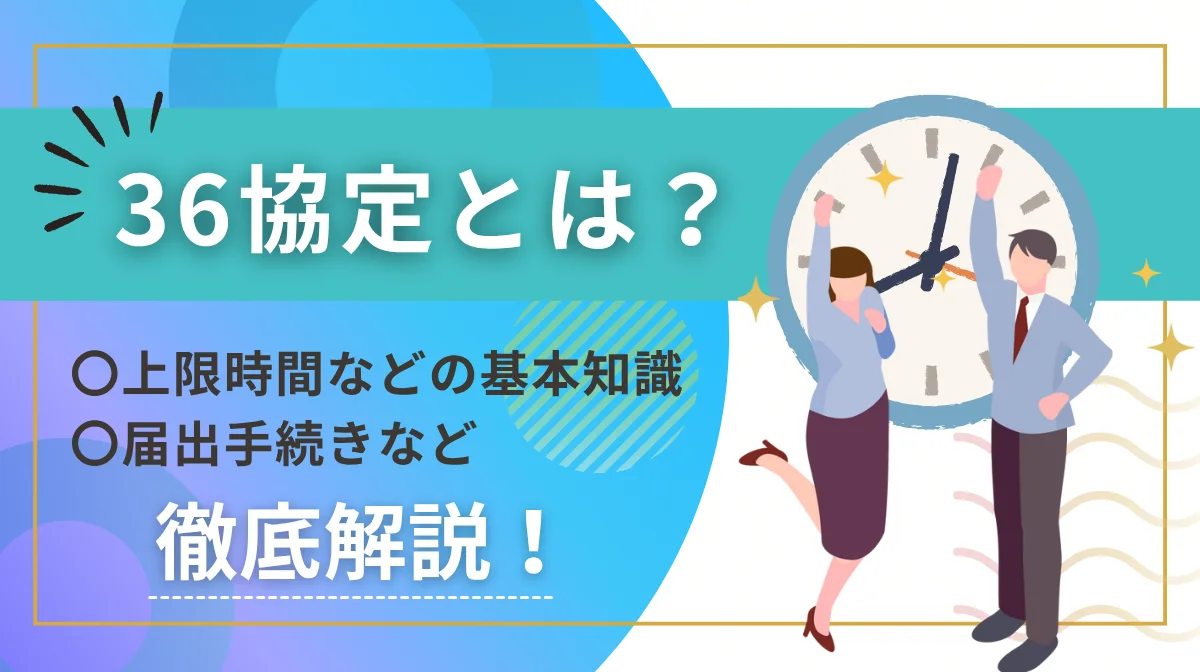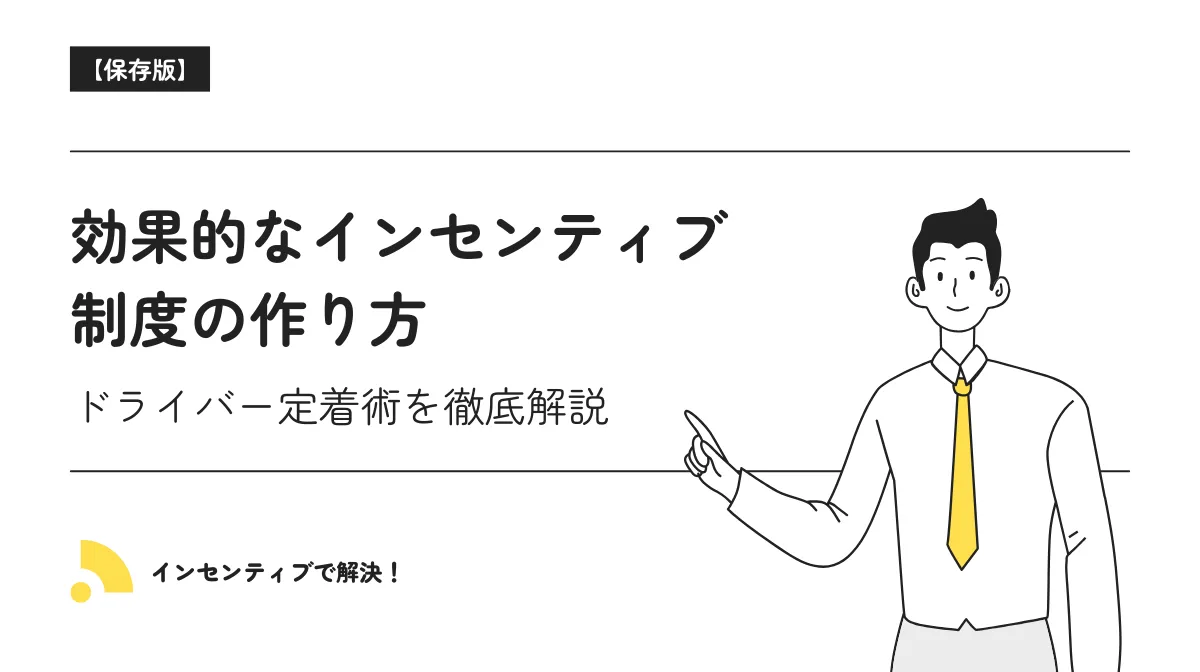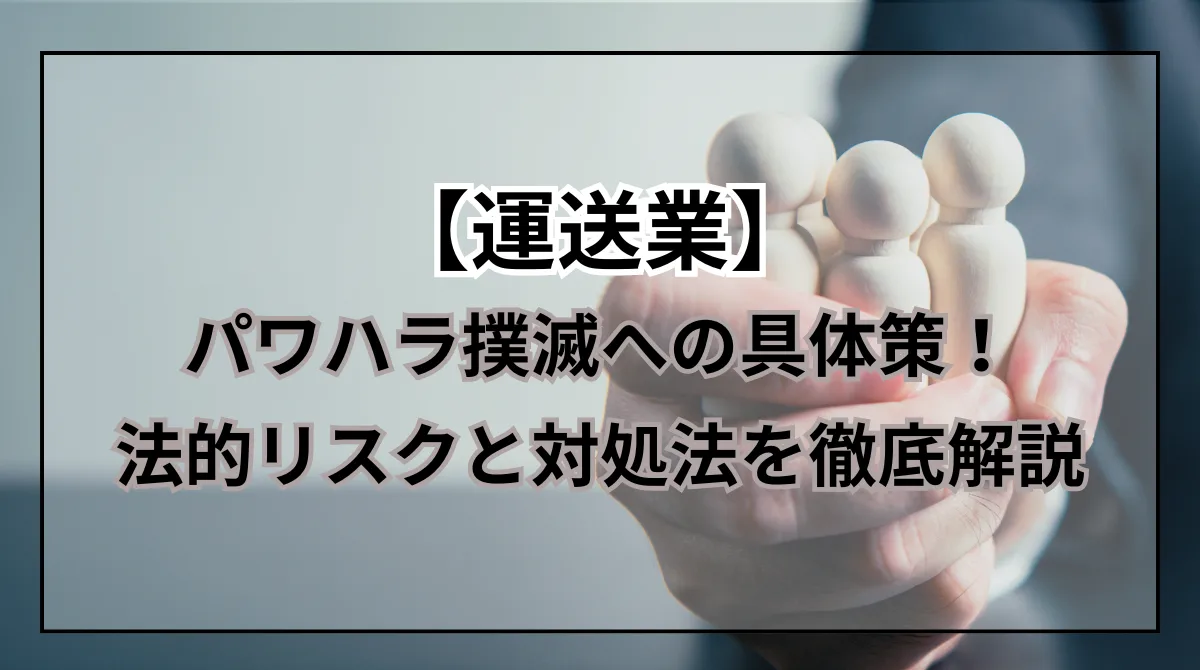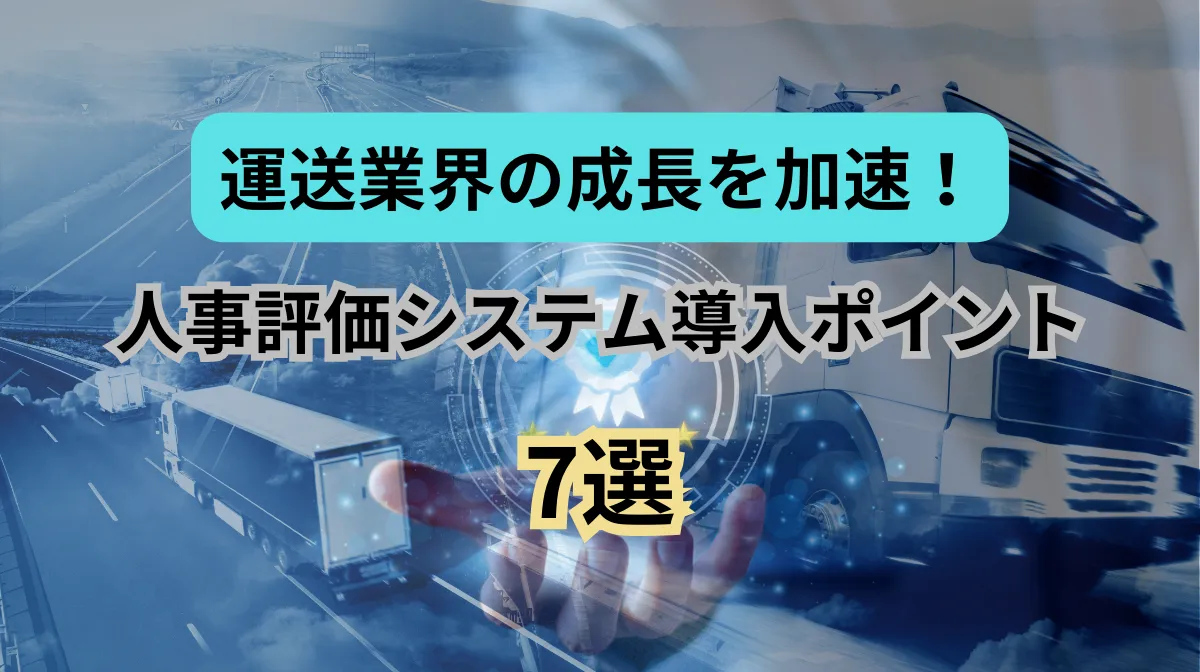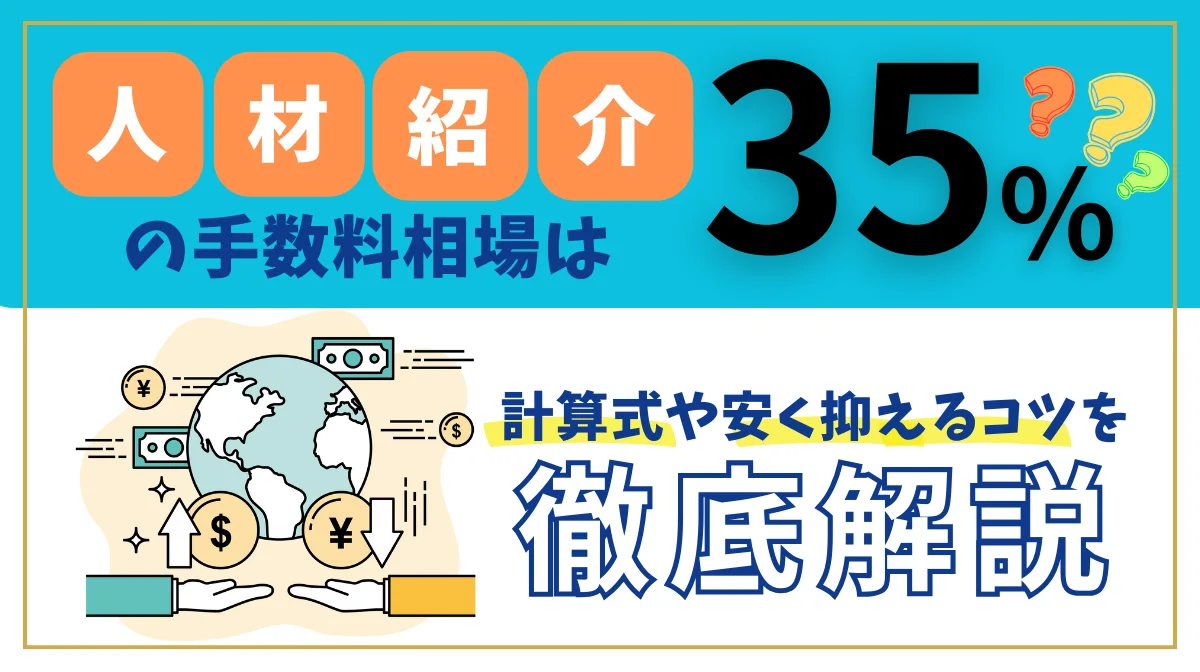36協定は、企業にとって避けて通れない重要な法的手続きの一つです。従業員に残業や休日労働をさせる際に必要となるこの協定ですが、「上限時間の計算方法が複雑で不安」「届出手続きの流れを知りたい」といった声をよく耳にします。
ただでさえわかりづらい36協定ですが、2019年の働き方改革関連法により上限規制がさらに厳格化され、違反すれば刑事罰の対象となるなど、対応のハードルは一層高くなっています。適切な理解がないまま運用すると、企業にとって重大なリスクを招きかねません。
本記事では、36協定の基本知識から具体的な作成手順、違反を防ぐためのポイントまで、人事担当者が知っておくべき内容を分かりやすく解説します。
- 36協定の正式名称や必要性、具体的な書類作成・届出手順など、一連の流れを体系的に把握できます。
- 上限規制の詳細ルールや罰則内容を理解し、うっかり違反を防ぐ具体的な対策を身につけられます。
- 適切な36協定運用により従業員が働きやすく、企業も法的リスクのない職場を実現できます。
1.36協定とは何か?基本知識を分かりやすく解説

36協定とは、企業が従業員に残業や休日労働をさせる際に必要不可欠な労使協定です。人事・総務担当者にとって重要な法的手続きの一つであり、適切な理解と運用が求められています。
36協定の正式名称と由来
36協定の正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定届」といいます。「36協定」と呼ばれている理由は、この制度を定めている労働基準法第36条に由来しているからです。
労働基準法第36条では、労働者の過半数が加入する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、法定労働時間を超えた労働や法定休日の労働が可能になると規定されています。
なぜ36協定が必要なのか
労働基準法では、労働時間の原則として1日8時間、週40時間の法定労働時間が定められています。また、労働者に対して毎週少なくとも1回の法定休日を与えることも義務付けられています。
これらの法定労働時間や法定休日を超えて労働させる場合、企業は事前に36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。つまり36協定は、法定労働時間や法定休日の例外を認めるための法的手続きなのです。
この協定がなければ、たとえ1分でも法定労働時間を超える労働をさせることは労働基準法違反となってしまいます。

ビジネスを運営する上で、繁忙期や緊急対応などで残業が必要になるケースは避けられません。多くの企業にとって36協定は必須の手続きといえるでしょう。
36協定がないとどうなる?法的リスクを解説
36協定を締結・届出せずに従業員に残業や休日労働をさせた場合、労働基準法違反として6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。これは企業にとって非常に重大なリスクです。
さらに、36協定がない状態で労働させた場合、従業員から未払い残業代の請求を受けるリスクも高まります。「当社は残業の予定がないから大丈夫」と考える企業もありますが、意図しない残業が発生した場合でも法違反となるため、事前に36協定を締結しておくことが重要です。
予防的な観点から、残業の可能性がある企業はすべて36協定を締結・届出しておくことをおすすめします。
2.36協定が必要になる具体的なケース

36協定の締結・届出が必要となるのは、法定労働時間や法定休日を超えて労働させる場合です。ただし、実務では判断に迷うケースも少なくありません。ここでは、具体的な例を交えてわかりやすく解説します。
法定労働時間を超える残業をさせる場合
法定労働時間である1日8時間、週40時間を超えて労働させる場合には36協定が必要です。ここで注意したいのは、所定労働時間と法定労働時間の違いです。
| 所定労働時間とは | 会社ごとに就業規則や雇用契約で定めた、通常の労働時間のこと。 例:9:00~18:00(休憩1時間)など |
| 法定労働時間とは | 労働基準法で定められた上限の労働時間のこと。 原則1日8時間、週40時間。 |
■例えば…
9時~17時勤務・休憩1時間(実働7時間)の企業の場合
この企業で毎日18時まで1時間残業した場合、合計労働時間は8時間となり、まだ法定労働時間内といえます。この場合は「法定内残業」となり、36協定は不要です。しかし、毎日18時を超えて労働させる場合は法定労働時間の8時間を超えるため、36協定が必要となります。
また、週単位でも考える必要があります。1日の労働時間が8時間以内でも、週の合計労働時間が40時間を超える場合は時間外労働となり、36協定が必要です。
実務では毎日の労働時間と週の合計労働時間の両方を管理し、いずれかが法定時間を超える可能性がある場合は事前に36協定を締結しておきましょう。
法定休日に労働させる場合
労働基準法では、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが義務付けられています。この法定休日に労働させる場合には36協定が必要です。
■例えば…週休2日制の企業の場合
土日が休日の場合、どちらか一方が法定休日となる。
(一般的には、後に来る休日(日曜日)が法定休日とされることが多い)
日曜日に労働させる→36協定が必要
土曜日に労働させる→法定外休日のため、週40時間以内なら36協定は不要
ただし、土日両方に出勤し、週の労働時間が40時間を超える場合は時間外労働となるため、36協定が必要になります。実務では法定休日がどの曜日に設定されているかを明確にし、その日に労働させる可能性がある場合は必ず36協定を締結しておきましょう。
36協定が不要なケースも理解しよう
36協定が不要なケースを正しく理解することで、適切な労働時間管理が目指せます。主な不要ケースは以下の通りです。
- 法定内残業の場合
所定労働時間を超えても、1日8時間・週40時間以内であれば36協定は不要です。 - 法定外休日の労働かつ週40時間以内の場合
例えば、週休2日制で土曜日に5時間だけ働き、週の合計が40時間以内であれば36協定は不要です。 - フレックスタイム制を導入している企業
清算期間内で法定労働時間の総枠を超えなければ、日々の労働時間が8時間を超えても時間外労働にはなりません。 - 管理監督者に該当する役職者
労働時間の規制が適用されないため、原則として36協定は不要です。ただし、深夜労働(午後10時から午前5時)については管理監督者でも割増賃金の支払いが必要です。
これらのケースを正しく把握し、無駄な手続きを避けながらも、必要な場合には確実に36協定を締結するよう心がけましょう。
法令遵守を支える優秀なドライバー採用をお考えの方へ
36協定の適切な管理には、信頼できる人材の確保が不可欠です。カラフルエージェントなら、法令遵守意識の高い経験豊富なドライバーを即日ご紹介いたします。
3.36協定で設定できる残業時間の上限規制

2019年4月の労働基準法改正により、36協定で設定できる残業時間には罰則付きの上限が設けられました。違反すると刑事罰の対象となるため、人事担当者は必ず理解しておく必要があります。
一般条項での上限時間(月45時間・年360時間)
36協定の一般条項で設定できる残業時間の上限は、月45時間・年360時間です。これは法定休日労働を含まない時間外労働のみの上限です。ただし、1年単位の変形労働時間制を採用している企業では、月42時間・年320時間となります。

例えば、一般の労働者が月に20日間勤務する場合、1日平均2.25時間まで残業が可能です。
なお、残業時間の管理は36協定で定めた起算日から計算します。起算日は企業が自由に設定できますが、給与の締日に合わせることが一般的です。例えば、給与が月末締めの場合は毎月1日、20日締めの場合は毎月21日を起算日とするケースが多いようです。
この起算日から1カ月毎、1年毎に残業時間を合計し、上限を超えないよう管理する必要があります。実務では勤怠管理システムなどを活用し、リアルタイムで残業時間を把握できる体制を整えておきましょう。
特別条項とは何か
特別条項とは、臨時的な特別の事情がある場合に限り、一般条項の上限(月45時間・年360時間)を超えて残業をさせることができる制度です。ただし、特別条項を定める場合は、より厳しい上限規制が適用されます。
特別条項が必要となる企業として、以下のような業種があげられます。
- レジャー・観光業
- 小売販売業
- 人材派遣業など
これらの業種では、長期休暇中の超繁忙期や派遣先企業の勤務状況への対応など、一時的に業務量が大幅に増加することが予想されます。
なお、特別条項を定める場合は健康確保措置の実施も義務付けられており、労働者の健康と安全に配慮した運用が必要です。
特別条項での上限時間と4つのルール
特別条項を締結していても、一般条項の上限を超えて残業を命じるには、以下の4つの条件すべてを満たす必要があります。
- 月45時間を超える残業ができるのは年6回まで
12カ月のうち6カ月は必ず月45時間以内に収める必要があります。 - 年間の残業時間が720時間以内(法定休日労働を除く)
月45時間×6カ月+特別延長時間の合計が720時間を超えてはいけません。 - 1カ月の残業時間と休日労働の合計が100時間未満
単月での絶対的な上限で、特別条項で延長時間を定めていても100時間以上は働かせられません。 - 連続する2カ月から6カ月の残業時間と休日労働の平均が全て80時間以内
例えば、ある月に95時間働いた場合、その月を含む2カ月、3カ月、4カ月、5カ月、6カ月の平均が全て80時間以内になるよう調整が必要です。
これらのルールは複雑ですが、労働者の健康を守るための重要な規制であり、違反すると刑事罰の対象となるため、確実な管理が求められます。
▼あわせて読みたい
36協定で定める残業時間の上限内で生産性を高めるには、インセンティブ制度の活用が効果的です。適切な評価と報酬により、働くモチベーションを向上させることができます。
4.36協定の書類作成から届出まで
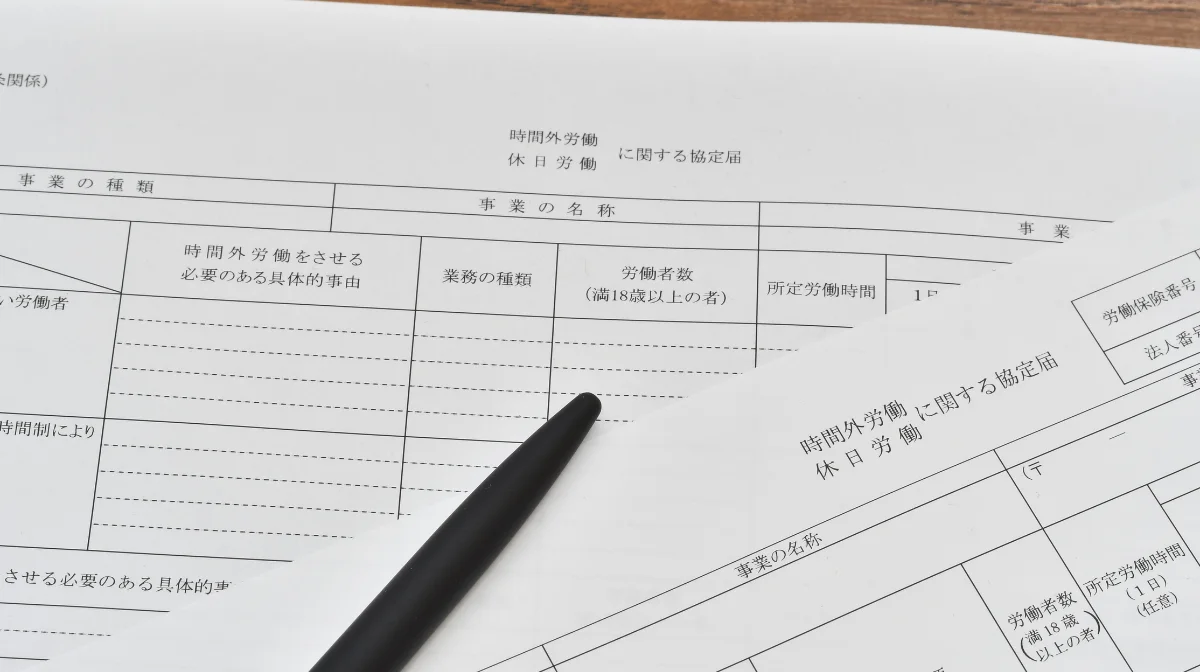
36協定の書類作成から労働基準監督署への届出まで、実際の手続きの流れを具体的に解説します。初めて作成する担当者でも迷わずに進められるよう、わかりやすくポイントを整理しました。
必要な様式の選び方(一般条項 vs 特別条項)
36協定の作成では、まず自社に必要な様式を選択することから始まります。厚生労働省が提供する様式は2種類です。
- 一般条項のみの場合→「様式第9号」
- 特別条項付きの場合→「様式第9号の2」
一般条項で十分かどうかは、月45時間・年360時間の上限内で業務が回るかどうかで判断します。
特別条項付きの様式は2枚構成になっており、1枚目は一般条項と同様の内容、2枚目に特別条項の詳細を記載します。
様式は厚生労働省のホームページからダウンロードできるほか、作成支援ツールも提供されているので、活用するとよいでしょう。なお、将来的に月45時間を超える可能性が少しでもある場合は、予防的に特別条項付きの様式を選択することをおすすめします。
記入時の注意点とポイント
36協定届の記入において、いくつか抑えておくべきポイントがあります。以下で見ていきましょう。
- 【POINT1】協定の有効期間について
協定の有効期間は1年間とすることが望ましいとされています。起算日は給与の計算期間に合わせて設定するのが一般的です。 - 【POINT2】時間外労働をさせる必要のある具体的事由について
「緊急対応が必要な場合」といった抽象的な表現ではなく、「月末決算による業務の集中」「システムの大規模改修作業」など、具体的で客観的な内容を記載する必要があります。 - 【POINT3】延長できる時間数について
法定の上限を超えないよう注意深く設定しましょう。特別条項を定める場合は、限度時間を超えて労働させる場合の割増賃金率を法定の25%を上回る率で設定してください。
また、健康確保措置についても、用紙裏面の選択肢から該当するものを選び、具体的な内容を記入しましょう。 - 【POINT4】労働者代表との締結
管理監督者ではない者を適切に選出し、記名押印または署名を得る必要があります。記入後は内容を十分に確認し、法定上限を超えていないか、記載漏れがないかをチェックしましょう。
▼あわせて読みたい
36協定の適切な運用には、就業規則との整合性も重要です。労働時間や休日に関する規定を明確にし、従業員が安心して働ける環境を整備しましょう。
労働基準監督署への届出方法
36協定届の提出方法には、持参による提出と電子申請の2つの方法があります。
■持参による提出の場合
所轄の労働基準監督署に協定届を2部持参します。
1部は監督署が受理し、1部は受付印を押印した後、控えとして返却されます。
■電子申請の場合
e-Gov電子申請システムを利用して行います。
まずe-Gov電子申請アプリケーションをパソコンにインストールし、ログイン後に「時間外労働・休日労働に関する協定届」を検索します。
一般条項のみか特別条項付きかを選択して必要事項を入力し、送信すると審査が行われ、受付印が付与された控えが電子的に交付されます。
なお、4月前後は労働基準監督署が混み合うことが多いため、36協定の有効期間開始日の2~3週間前には届出を完了させるとよいでしょう。

労働基準監督署までの交通費や時間を考慮すると、電子申請による届出がおすすめです。24時間いつでも提出可能なので、積極的に活用しましょう。
36協定の準備完了!次は即戦力ドライバーの確保を
36協定の適切な管理には、信頼できる人材の確保が不可欠です。36協定の運用体制を整えたら、次は優秀な人材の確保です。カラフルエージェントでは、必要な資格を持つ即戦力ドライバーを成功報酬でご紹介しています。
5.36協定違反の罰則と防止策

36協定の違反は労働基準法違反となり、刑事罰の対象となります。企業のコンプライアンス体制を守るため、罰則の内容と効果的な防止策を理解しておきましょう。
違反時の具体的な罰則内容
36協定に関する違反行為には、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。具体的な違反例をみていきましょう。
- 36協定を締結・届出せずに残業や休日労働をさせた場合
- 36協定で定めた時間を超えて労働させた場合
- 法定の上限時間を超えて労働させた場合
- 労働者代表の選出が不適切だった場合など
これらの違反は労働基準法第32条(労働時間)または第35条(休日)の違反として処罰されます。罰則は企業の代表者個人に科されるため、経営陣にとっても深刻な問題となるでしょう。
また、刑事罰だけでなく、労働基準監督署からの調査や指導、改善命令を受ける可能性もあり、企業の社会的信用失墜や採用活動への悪影響、取引先からの信頼低下なども懸念されます。
▼あわせて読みたい
36協定違反と同様に、パワハラも企業に重大な法的リスクをもたらします。労働環境の改善には、労働時間管理とハラスメント対策の両面からのアプローチが不可欠です。
うっかり違反しやすい2つのケース
実務でよく発生する「うっかり違反」のケースを2つ紹介します。これらのミスを防ぐためにも、休日労働時間も含めた総合的な労働時間管理システムの導入と、36協定の有効期間を定期的にチェックする仕組みづくりをしておきましょう。
【ケース1】休日労働時間のカウント漏れ
平日の残業時間は管理していても、休日労働時間を見落とす企業は少なくありません。36協定の上限規制では、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2~6カ月平均が80時間以内という規制があります。注意しましょう。
■例えば…
平日の残業が月80時間で上限内だと安心していても、休日労働が20時間あれば合計100時間となり、上限違反となるなど
【ケース2】36協定の更新忘れ
36協定の有効期間は通常1年間で、期間が過ぎると自動的に無効となります。有効期間が切れた状態で残業をさせると、36協定がない状態での労働となり、法違反となります。
■例えば…
4月に締結した36協定が翌年3月末で期限が切れたが、年度末の忙しさで更新手続きを忘れるなど
違反を防ぐための勤怠管理のポイント
36協定違反を確実に防ぐためには、効果的な勤怠管理システムの導入と運用が不可欠です。以下でポイントをみていきましょう。
- 【POINT1】リアルタイムでの労働時間把握
勤怠管理システムを活用し、残業時間と休日労働時間を自動的に集計し、36協定の上限に近づいた従業員を早期に発見できる体制を整えましょう。
システムには月45時間、年360時間、月100時間(休日労働含む)、2~6カ月平均80時間などの上限値を設定し、これらに近づいた場合にアラート機能で管理者に通知する仕組みが有効です。 - 【POINT2】36協定の有効期間管理
有効期間の3カ月前、1カ月前、1週間前にリマインド通知を設定し、更新手続きを忘れないようにしましょう。 - 【POINT3】従業員への教育
36協定の趣旨と上限時間について従業員に周知し、長時間労働の問題意識を共有することで、自主的な労働時間管理を促進できます。定期的なノー残業デーの実施や残業事前申請制の導入も効果的な施策です。
これらの取り組みを組み合わせることで、36協定違反のリスクを大幅に軽減できるのです。
▼あわせて読みたい
36協定の管理と併せて、従業員の働きがいを向上させる人事評価システムの導入も重要です。適切な評価制度により、長時間労働の改善と生産性向上を両立できます。
コンプライアンス重視の人材採用で企業リスクを軽減
法令遵守の徹底には、経験豊富で責任感のあるドライバーの採用が重要です。カラフルエージェントなら、登録者の91%以上が有資格者で、信頼できる人材をすぐにマッチングできます。
6.36協定に関するよくある質問

36協定の運用において、人事担当者から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。実務で迷いやすいポイントについて、具体的に解説します。
従業員代表が退職した場合の対応
36協定の有効期間中に従業員代表が退職した場合でも、原則として36協定の再締結は必要ありません。36協定は労使間で一度締結されれば、有効期間中は継続して効力を持ちます。
ただし、特別条項付きの36協定を締結している場合は注意が必要です。特別条項では「限度時間を超えて労働させる場合の手続」として「労働者代表に対する事前申し入れ」が定められているケースが多く、この労働者代表が退職してしまうと手続きが取れなくなってしまうのです。
この場合は、新たに労働者代表を選出する必要があります。

労働者代表の選出は、管理監督者以外の者の中から、投票や挙手などの民主的な方法で過半数の同意を得て行います。選出後は、特別条項に定められた手続きに従って事前申し入れを行うことで、月45時間を超える残業が可能となります。
押印の必要性について
36協定届の押印については、よく誤解される部分です。2021年の労働基準法施行規則の改正により、36協定届自体には押印が不要となりました。しかし、これは36協定届と36協定書を別々に作成した場合の話です。
| 36協定書 | 36協定の内容について、企業と労働者が合意・締結したことを証明する書類 |
| 36協定届 | 36協定について労働基準監督署に届け出るための書類 |
多くの企業では、36協定届が36協定書を兼ねる形で運用されており、この場合は労使双方の記名押印または署名が必要となります。つまり、36協定を締結するという行為においては、必ずどこかで労使双方の記名押印または署名が必要だということです。
押印か署名かは選択可能ですが、いずれも本人確認ができる形で行うことが重要です。
自動更新は可能か
36協定の自動更新は制度上可能ですが、実務的にはあまり推奨されません。自動更新する場合でも、毎年1回は「労使双方から異議の申出がなかった事実を証明する書類」を任意の様式で作成し、労働基準監督署に提出する必要があります。
この書類では、労働者代表と使用者の双方が自動更新に同意していることを確認し、署名または押印することが求められます。しかし、労働関係法令は頻繁に改正されるため、毎年36協定の内容を見直し、必要に応じて改定することが望ましいとされています。
また、業務内容の変化や組織体制の変更に伴い、残業が必要となる事由や延長時間の見直しが必要になることも多いでしょう。
毎年の見直しにより、法改正への対応や業務実態に即した協定内容の調整が可能となり、より適切な労働時間管理を目指せるのです。

自動更新を選択する場合でも、少なくとも3年に1回は協定内容の全面的な見直しを行い、現在の業務実態や法令に適合しているかを確認しましょう。
▼あわせて読みたい
長時間労働の抑制とともに、従業員のメンタルヘルス対策も重要な課題です。36協定の適切な運用により、心身ともに健康な職場環境の実現を目指しましょう。
安心の労働環境で優秀なドライバーを迎えませんか?
36協定を適切に運用し、安心できる職場環境を整えたら、優秀なドライバーの採用で事業を成長させませんか?カラフルエージェントが面接調整から条件交渉まで代行いたします。
7.36協定を正しく理解し、安心できる職場環境を!
本記事では、36協定の基本的な仕組みや実務に必要な締結・届出の手順、陥りやすいミスなどを詳しく解説しました。
36協定は“提出して終わり”ではありません。形だけの届け出に終始するのではなく、協定内容を正しく理解し、継続的な労働時間の管理や定期的な見直しを行うことが、コンプライアンス強化と職場改善につながるのです。
36協定は、時間外・休日労働を適正に管理し、企業と従業員の双方にとって健全な働き方を実現するための重要な制度です。ぜひ、本記事を参考に、持続可能で信頼される企業づくりへの第一歩を踏み出してください。