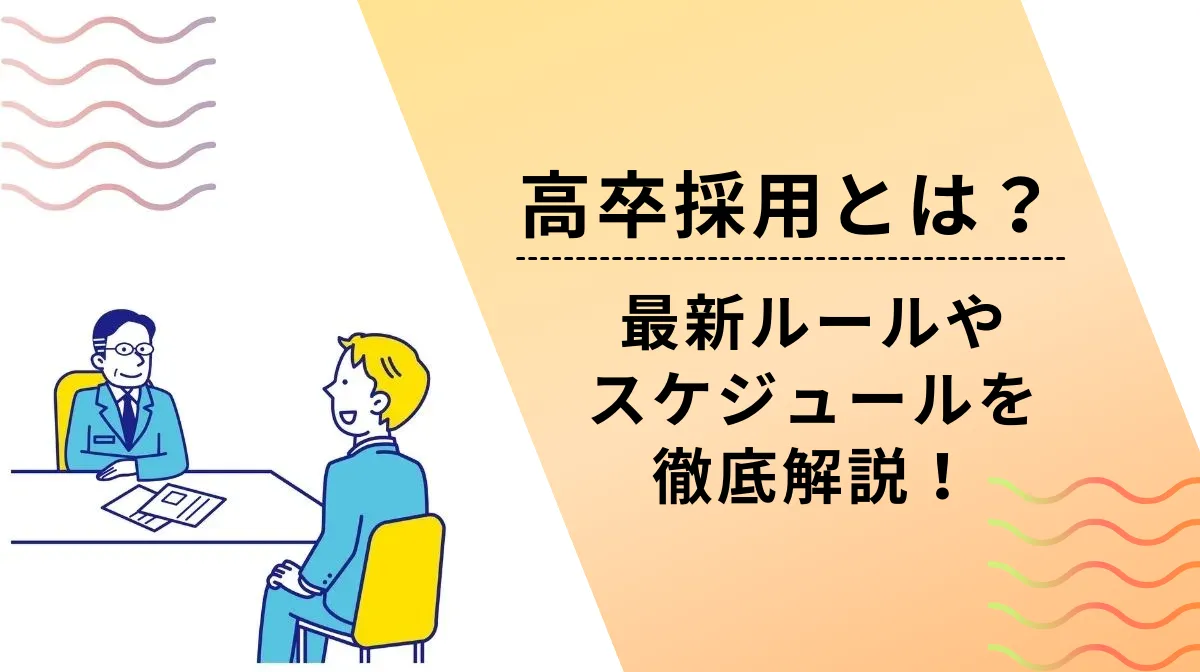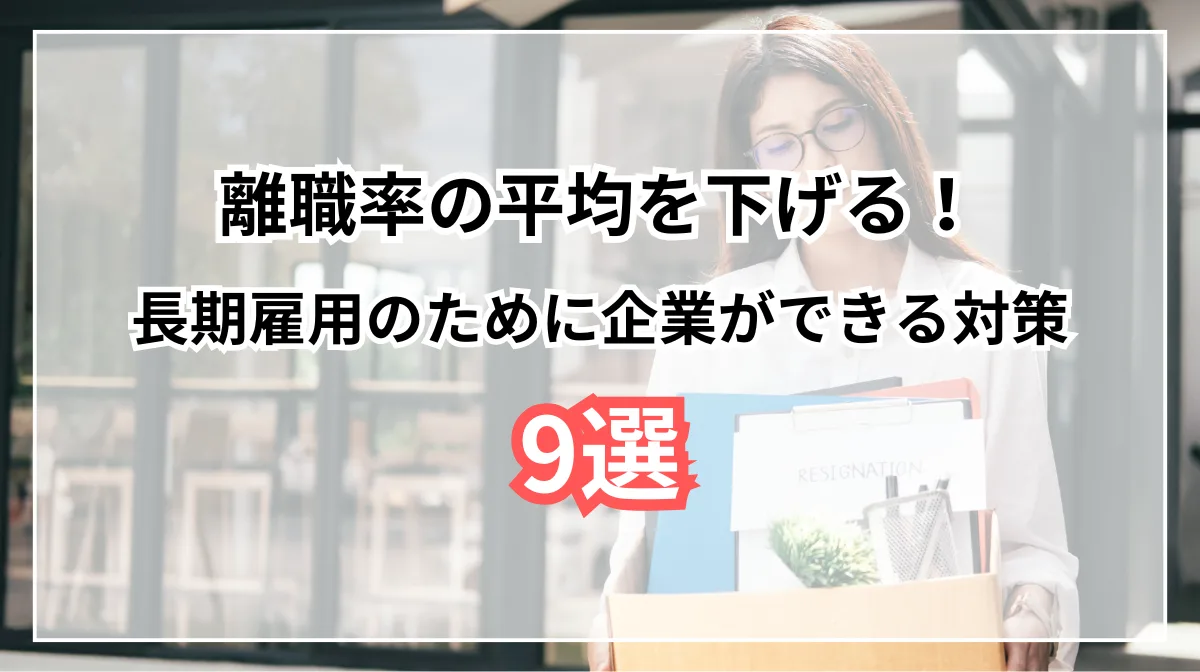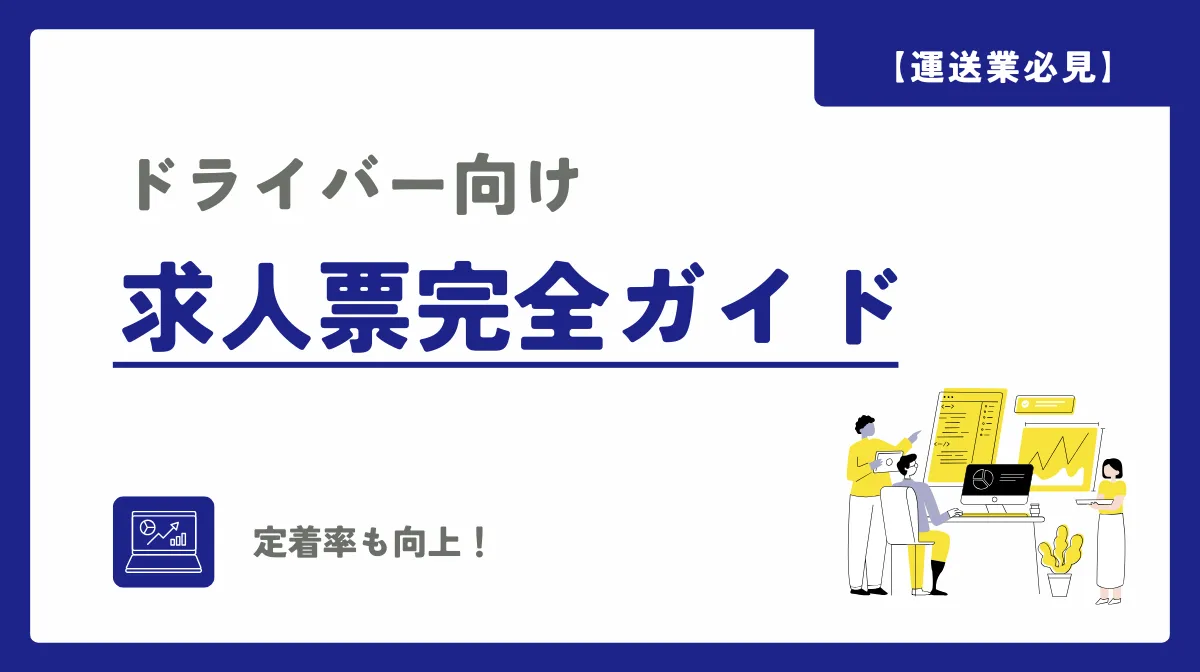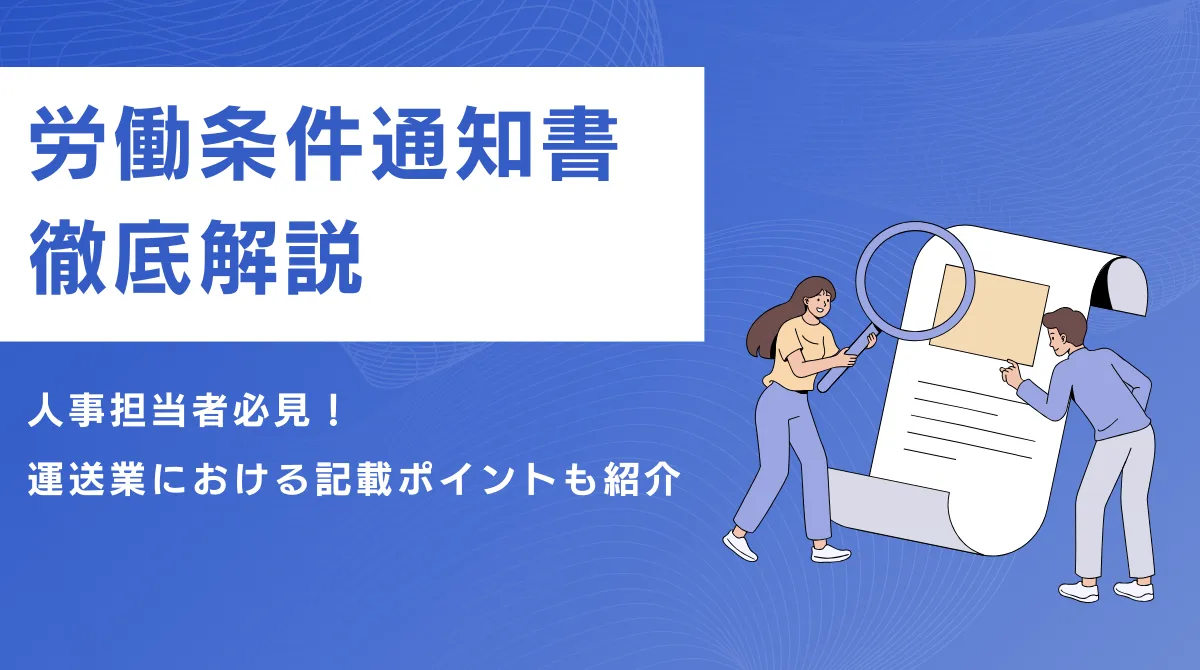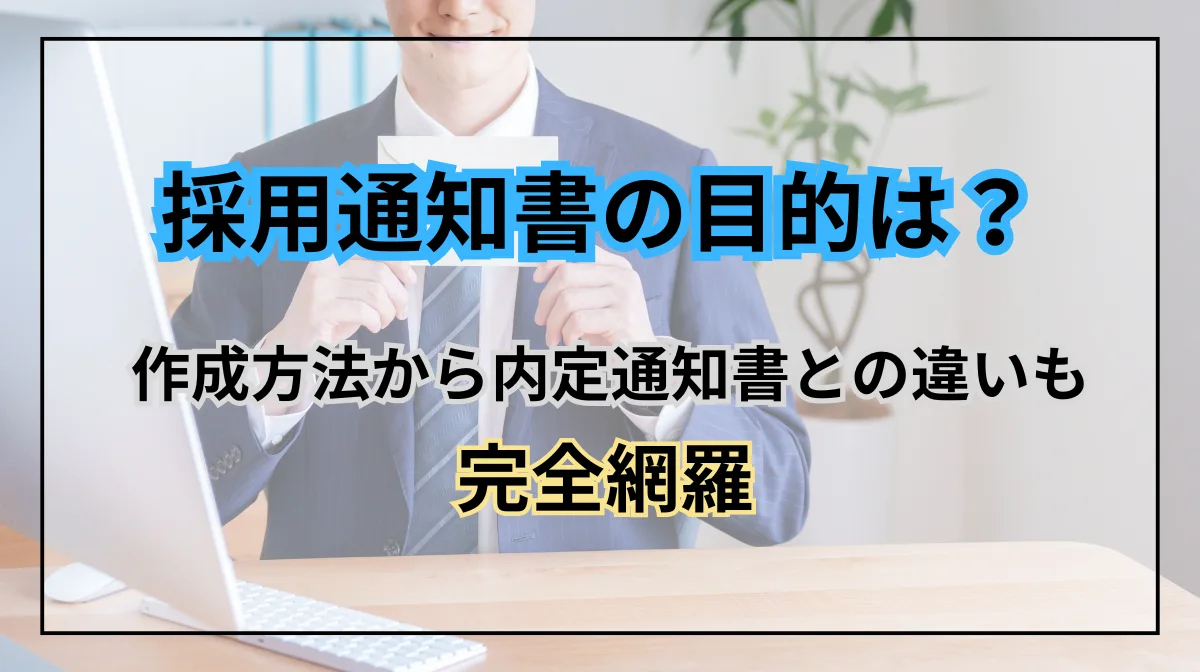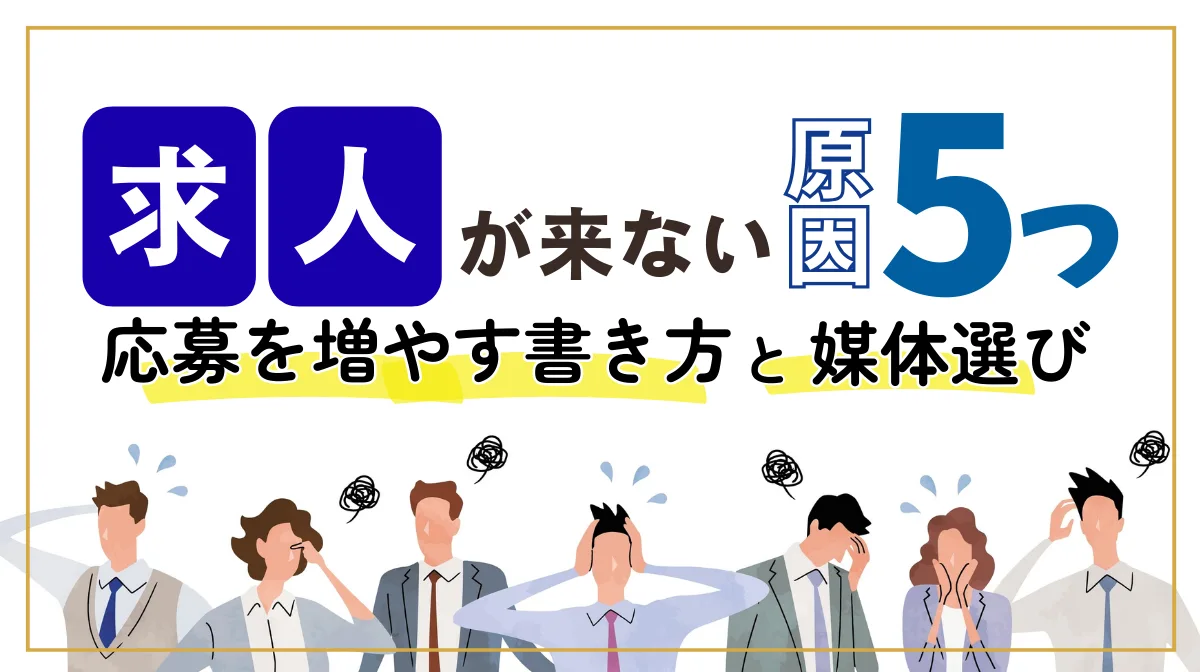高校卒業予定者を採用する「高卒採用」には、大卒採用とは異なる独自のルールやスケジュールがあります。一人一社制や指定校求人など、高卒採用特有の仕組みを理解し、適切に対応することが採用を成功させる鍵となるでしょう。
本記事では、高卒採用の基本的な定義から最新の動向まで、人事担当者が知っておくべき情報を解説します。高卒採用を成功させるためのポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
- 高卒採用には独自ルールがあり、近年は一人一社制の緩和が進行中
- 高卒採用は長期育成可能・コスト低減というメリットと早期離職リスクがある
- 成功には魅力的な求人票・効果的な職場見学・適切な面接・学校との関係構築が鍵
1.高卒採用とは?

大学新卒採用とは異なり、高校卒業予定者を対象とした採用活動には、独自のルールや手続きが存在します。ここでは、高卒採用の特徴について、基本からわかりやすく解説します。
高卒採用とは、高校卒業予定の生徒を対象とした新卒採用のことを指します。大学新卒採用と比べて、より厳格なルールや独自の採用プロセスがあるのが特徴です。
高卒採用は、主に以下の2つの方法があります。
| 指定校求人 | 企業が特定の高校を指定して求人を出す採用方法 |
| 公開求人 | エリアを限定せず広く求人情報を公開する採用方法 |
どちらもハローワークを通じて求人票を提出します。また、高卒採用は採用過程にも特徴があります。
- 企業と生徒は直接コンタクトを取れない
必ず高校を介して連絡や選考が行われます。 - 一人一社制
生徒は原則として一度に1社しか応募できず、選考結果が出るまで次の企業に応募できない。 - 応募前職場見学
生徒が応募前に企業の職場環境や業務内容を直接見学する機会を設けることが推奨されている。
このような厳格なルールは、生徒の学業と就職活動の両立を図るために設けられています。
高卒採用を検討する企業は、こうした独自のルールを十分に理解した上で、採用計画を立てることが重要です。
【ドライバー採用をお考えの担当者様へ】
ドライバー採用ならカラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。
▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら
2.高卒採用のメリットとデメリット

企業の人材戦略において、高卒採用は重要な選択肢の一つです。若手を早期に育成できる一方で、大卒採用とは異なる課題も存在します。
ここからは、高卒者を採用することのメリットとデメリットについて、わかりやすく解説します。
高卒採用のメリット
高卒採用を「大卒採用の補完」として考えていませんか?実は、高卒採用には大卒採用にない多くのメリットがあります。
高卒者の特性を理解し、適切な採用・育成戦略を立てることで、自社にマッチした人材を採用できるでしょう。
長期的な育成が可能
高卒者を採用する最大のメリットは、入社後に長期的な育成が可能なことです。高卒者は、高校卒業後すぐに入社するため、若いうちから企業文化や業務知識を吸収し、将来的に中核を担う人材へと成長させられるでしょう。
また、若く柔軟な思考を持ち、会社の方針や価値観を素直に吸収する傾向がある点も、高卒者の特徴です。先入観が少なく、企業独自の方法やシステムを受け入れやすいため、自社の理念や方針に沿った人材育成が期待できます。
さらに、地元志向が強いケースが多く、地方企業にとっては定着率を高める効果も期待できるでしょう。実務経験を積ませながら必要な知識や技能を身につけさせることで、現場力の強い人材を育てられるのです。
コストが抑えられる
高卒採用は、ハローワークの求人票と高校からの推薦によって採用が決まるのが基本です。大卒採用のように複数の求人広告を出したり、就活イベントの出展したりする必要がないため、広告費や採用業務にかかる時間的コストを抑えられるでしょう。
また、「一人一社制」などの影響により、高校生が一度に応募できる企業数が限られており、内定辞退がほぼない点も特徴です。そのため、選考にかかる業務負担を大幅に軽減できるというメリットがあります。
さらに、高卒採用は初任給をはじめとする人件費を抑えやすく、企業にとっては継続的にコストを抑えられる点も魅力です。
継続採用が期待できる
高卒採用は、主に高校の推薦を通じて行われるため、学校との信頼関係が採用活動の成否を左右します。一度「この企業なら安心して生徒を任せられる」と感じてもらえれば、翌年以降も継続的に優秀な人材を紹介してもらえる可能性が高まります。
学校訪問や先生方との丁寧な対話を重ね、信頼を積み上げていくことが何より重要です。継続的に高卒人材の確保を検討している企業は、こうした信頼づくりを意識的しましょう。
高卒採用のデメリット
高卒者の採用は多くのメリットがある一方で、注意すべき点も少なくありません。特に、採用後の定着や育成、就業意識の差などに課題を感じる企業も少なくないでしょう。
ここでは、高卒採用における主なデメリットについて整理し、成功のポイントを考えていきます。
早期離職率が高い傾向にある
厚生労働省の調査によると、令和3年3月に卒業した新規学卒就職者の離職状況は以下の通りでした。
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | |
| 高卒者 | 16.7% | 12.2% | 9.4% |
| 大卒者 | 12.3% | 12.3% | 10.3% |
この結果からもわかるように、高卒者の場合、1年目の離職率が高くなる傾向にあります。
これは、業界研究や自己分析が大卒者に比べて十分に行われていないことが原因とされており、その結果として入社後にギャップを感じやすくなっていると考えられます。こうしたギャップを減らすためにも、応募前職場見学などを積極的に活用しましょう。
参照:厚生労働省「学歴別就職後3年以内離職率の推移」
ミスマッチが起こりやすい
高卒採用では、企業と人材のミスマッチが起こりやすい傾向があります。その主な要因として、「一人一社制」による選択肢の少なさが挙げられます。
校内推薦に漏れた場合、第一希望の企業に応募できず、やむを得ず第二・第三希望の企業を選ばなければならないケースも少なくありません。その結果、生徒は「本当にやりたかった仕事ではない」と感じ、企業側も「求めていたスキルや適性と違う」といったギャップが生まれ、ミスマッチに繋がってしまうのです。
こうしたミスマッチを防ぐためにも、応募前職場見学の実施や求人票での丁寧な説明などを通じて、相互理解を深める努力が求められます。
▼離職率を下げるために…
以下の記事では、離職率平均の計算方法、業界別の特徴から改善施策まで解説しています。働き手を守る対策とは?!ぜひ参考にしてください。
3.高卒採用の基本的な仕組みと特徴
高卒採用を成功させるためには、特有の仕組みと特徴を理解することが不可欠です。大卒採用とは異なるルールや手続きがあるため、それらを把握した上で採用活動を進めましょう。

指定校求人と公開求人の違い
高卒採用には大きく分けて「指定校求人」と「公開求人」の2つの方法があります。
- 指定校求人
企業が特定の高校を指定して求人を出す方法です。この場合、企業はハローワークに求人票を提出し、ハローワークが内容を確認した後に指定された高校に求人情報が送られます。 - 公開求人
特定の高校を指定せず、広くハローワークを通じて求人情報を公開する方法です。この場合、より多くの高校・生徒に情報が届くため、応募者の母数を増やすことができます。
特に採用人数が多い場合や、特定の高校との関係がまだ構築できていない段階では有効な手段と言えるでしょう。
ただし、学校側の選考を経ていないため、応募者の質にばらつきが生じる可能性があります。企業の知名度や業界によっても効果が異なるため、自社の状況に合わせて選択することが重要です。
高卒・大卒採用で異なるルールと自由度
高卒採用と大卒採用には、多くの違いがあります。最も大きな違いは選考スケジュールです。
高卒採用は法令によりスケジュールが厳密に定められているのに対し、大卒採用は政府からの要請はあるものの最終的には企業に裁量があります。
また、求人票についても、高卒採用ではハローワーク指定のフォーマットを使用する必要がありますが、大卒採用では企業が自由に求人媒体や形式を選べます。
面接回数も高卒採用では原則1回のみとされていますが、大卒採用では複数回の面接を実施するのが一般的です。
4.高卒採用の独自ルール「一人一社制」とは?

ここまで解説したとおり、高卒採用には、大卒採用とは異なる独自のルールが存在します。採用活動を円滑に進めるためにも、これらのルールを正しく理解しておきましょう。
特に重要なルールである「一人一社制」について詳しく解説します。
一人一社制とは何か
一人一社制とは、高校生が原則として一度に1社にしか応募できないという、高卒採用特有の制度です。具体的には、生徒が1社に応募し、不採用だった場合に初めて、次の企業に応募できるという仕組みです。
この制度が設けられた主な理由は、生徒の学業と就職活動の両立を図るためです。高校3年生は学業が最も重要な時期であり、多数の企業の選考を同時に受けることで学業がおろそかになることを防ぐ意図があります。
また、一人一社制には学校側の事情も関係しています。
多くの高校では、応募する生徒を学内で選考し、企業に推薦する形を取っています。特に人気企業に対しては応募希望者が多数いる場合があり、学校側で成績や人物評価などを基に選考を行います。
一人一社制によって、特定の生徒が多数の求人を独占することを防ぎ、より多くの生徒に就職機会を提供することが可能になるのです。
企業側にとっては、学校側の選考を経た生徒が応募してくるため、一定の質が担保されるというメリットがあります。
各都道府県での一人一社制の見直し状況
一人一社制は長年続いてきた制度ですが、近年では生徒の就業機会を制限しているという観点から、各都道府県で見直しが進んでいます。
2025年では、以下のように多くの都道府県で一人一社制の緩和が進んでいます。
| 青森、神奈川、滋賀など | 9月中は1人1社、その後は複数応募可能 |
| 秋田、茨城、沖縄など | 当初から複数応募可能 |
| 和歌山など | 当初から県内に限り複数応募可能 |
このように、生徒がより多くの選択肢から選べる方針を取っている県が増えています。
また、複数企業からの内定を得た場合の対応として、2社目の内定を得てから3日以内に就職先を決定するというルールを設けている都道府県もあります。
企業側としては、これらの地域別の違いを把握し、自社が求人を出す地域の最新ルールに対応することが重要です。
参照:高卒就職情報WEB提供サービス「都道府県高等学校就職問題検討会議における申し合わせ等」
【ドライバー採用をお考えの担当者様へ】
ドライバー採用ならカラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。
▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら
5.高卒採用のスケジュールと流れ

高卒採用を成功させるためには、法令で定められた厳密なスケジュールを把握し、計画的に採用活動を進めることが重要です。大卒採用と異なり、高卒採用では各ステップの時期が明確に定められています。
スケジュールは都道府県によって若干の違いがありますが、代表的なものをご紹介します。
| 6月 | 企業はハローワークへの求人申込を開始します。この時点で求人票を作成し、必要事項を記入して提出します。 |
| 7月 | 求人票が公開され、高校生が閲覧できるようになります。ここから9月初旬にかけて、応募前職場見学を実施することが推奨されています。 |
| 9月 | 9月5日から応募受付が開始され、9月16日以降に企業での選考(主に面接)が実施できるようになります。 |
| 10月以降 | 引き続き選考が進められ、内定が出されます。 |
| 4月 | 正式入社 |
求人を出す地域のスケジュールについては、管轄のハローワークへ直接問い合わせるのが確実です。
6.高卒採用に必要な書類と手続き

高卒採用を進める上で、適切な書類の準備と手続きの理解は欠かせません。特にハローワーク指定の求人票は、高卒採用の要となる重要な書類です。
ここでは、必要な書類と手続きについて詳しく解説します。
ハローワーク指定の求人票の書き方
高卒採用では、ハローワーク指定の求人票を使用することが義務付けられています。この求人票は高校生が企業を選ぶ際の最も重要な情報源となるため、記載内容には特に注意が必要です。
求人票には会社概要、募集職種、仕事内容、勤務条件、応募資格などの基本情報を詳細かつ正確に記入します。特に仕事内容については、具体的な業務内容や1日の流れを分かりやすく記載することで、生徒の理解を深め、入社後のミスマッチを防ぐことができます。
応募資格に関しては、高校生の現状を考慮した柔軟な対応が求められます。例えば、普通自動車運転免許が必要な場合でも、「18歳の誕生日を迎えていない」などの理由で、入社までに取得が難しいケースもあるため「入社後取得可」などの表記を検討しましょう。
また、給与条件や福利厚生、教育制度などは特に生徒や親の関心が高い項目です。これらを具体的に記載することで、自社の魅力をアピールすることができます。
求人票の記載内容は学校の進路指導教諭によって生徒に説明されるため、誤解を招く曖昧な表現は避け、正確な情報提供を心がけましょう。
▼魅力的な求人票作成にお悩みですか?
以下の記事では、ドライバー採用で応募が増える求人票の書き方を徹底解説しています。法的要件、NG表現、魅力的な書き方、成功事例まで網羅した運送会社向けガイドになります。ぜひ参考にしてください。
青少年雇用情報の記載ポイント
高卒採用の求人票には、青少年雇用情報欄が設けられています。
この欄には「新卒者などの採用者数/離職者数」「平均勤続年数」「研修の有無およびその内容」「自己啓発支援の有無およびその内容」「メンター制度の有無」などの情報を記載します。
これらは、企業の人材育成や定着に対する姿勢を示すものであり、可能な限りすべての項目を埋めることが推奨されています。
特に採用者数と離職者数は、企業の実態を示す重要な指標です。過去3年分の数字を記載することで、自社の定着状況を正直に伝えることができます。
また、研修やメンター制度については、具体的な内容や期間を記載することで、自社の人材育成に対する熱意を伝えることができます。
青少年雇用情報は、単に形式的に記入するのではなく、自社の強みや特徴を生徒や学校関係者に伝える機会と捉え、具体的かつ詳細に記載することが重要です。
採用選考時に必要な準備と書類
高卒採用の選考時には、適切な準備と書類の用意が不可欠です。
まず面接実施にあたっては、会社についてより深く理解してもらい、面接をスムーズに進めるためにも、以下の物を準備しましょう。
- 会社案内
- 業務内容の説明資料
- 選考用紙
- 評価シートなど
面接官には高卒採用の特性や注意点を事前に共有し、適切な評価ができるよう準備することが重要です。特に差別的な質問や不適切な言動がないよう、注意しましょう。
選考後、内定を出す際には内定通知書と労働条件通知書を学校経由で生徒に送付します。内定通知書には内定の条件や入社までのスケジュール、提出書類などを明記してください。
労働条件通知書は労働基準法に基づき、給与、勤務時間、休日、福利厚生などの条件を具体的に記載する必要があります。
さらに、入社までの間のフォローとして、研修の案内や定期的な連絡用の書類も準備しておくと良いでしょう。書類の作成にあたっては、高校生にも理解しやすい表現を心がけ、専門用語や業界特有の言葉は避けるか、説明を加えるなどの配慮が必要です。
▼労働条件通知書と採用通知書について詳しく
以下の記事では、労働条件通知書と採用通知書についてそれぞれ解説しています。法的にも重要な通知書にもなりますので、詳しく理解するためにもぜひ参考にしてください。
7.高卒採用成功のための4つのポイント

ここでは、高卒採用を成功させるための4つのポイントを具体的に解説します。高卒採用を単なる採用活動として終わらせるのではなく、優秀な人材の確保と長期的な定着を目指しましょう。
求人票で自社の魅力を効果的に伝える
求人票は高校生が企業を知る最初の窓口です。単なる事務的な情報だけでなく、自社の魅力を効果的に伝えることが重要です。
具体的には、仕事内容や1日の流れを詳細に記載し、生徒がイメージしやすいように工夫しましょう。また、教育・研修制度については、入社直後から何を学べるのか、どのようなスキルが身につくのかを具体的に記載します。
特に効果的なのは、過去の高卒採用者の活躍事例や成長ストーリーを紹介することです。
「入社○年目で○○の資格を取得」「入社○年目で○○の業務を任されている」など、具体的なキャリアパスを示すことで、生徒自身の将来像を描きやすくなります。
求人票の限られたスペースを最大限に活用し、自社の強みや特徴を簡潔かつ魅力的に伝えることを心がけましょう。
職場見学で生徒の興味を引き出す
応募前職場見学は、生徒が企業を理解し、入社後のミスマッチを防ぐために非常に重要です。この機会を単なる施設案内に終わらせるのではなく、実際の業務体験や社員との交流を通じて、職場の雰囲気や仕事の内容を体感できるプログラムを用意しましょう。
例えば、簡単な作業の体験、製品の組み立て、サービス提供のロールプレイなどを取り入れることで、仕事への興味を引き出すことができます。特に効果的なのは、入社後数年の若手社員(できれば高卒入社の先輩)との交流時間を設けることです。
年齢の近い先輩社員の話は生徒にとって現実味があり、自分の将来像を具体的にイメージしやすくなるでしょう。また、質問しやすい雰囲気づくりにも配慮し、生徒が抱く素朴な疑問や不安に丁寧に答えることで、企業への信頼感を高めることができます。
面接での注意点
高校生にとって企業面接は人生初めての経験であることが多く、極度に緊張している可能性があります。
まずは緊張をほぐすため、面接の冒頭で簡単な自己紹介や雑談を交えるなど、リラックスできる雰囲気づくりを心がけましょう。面接中は専門用語や業界用語を避け、高校生にも理解しやすい言葉を意識してください。
また、質問内容についても、高校生の経験に即したものを選ぶよう注意しましょう。
「あなたの強みは何ですか」といった抽象的な質問よりも、「学校生活で頑張ったことは何ですか」「どんな仕事に興味がありますか」など、具体的な経験や興味に関する質問の方が答えやすく、本人の人柄や適性を見極めるのに役立ちます。
また、面接官には高卒採用の特性や注意点を事前に共有し、差別的な質問や不適切な言動がないよう教育することも大切です。
学校との良好な関係を構築する
高卒採用において、学校との良好な関係構築は極めて重要です。特に、進路指導教諭は生徒の進路選択に大きな影響力を持っているため、定期的なコミュニケーションを心がけましょう。
学校訪問や電話連絡を通じて、自社の採用計画や求める人材像を伝えるとともに、学校側のニーズやフィードバックを聞く姿勢が大切です。また、学校が主催する企業説明会や職業講話などに積極的に参加することも効果的です。
このような機会を通じて、企業の認知度を高めるとともに、教諭や生徒との接点を増やすことができるでしょう。過去に採用した卒業生の活躍状況や成長の様子を伝えることも、学校との信頼関係を構築するうえで大切です。
継続的な採用実績を積み重ねることで、「指定校」としての関係を構築し、優秀な生徒の推薦を受けられる可能性が高まります。学校のスケジュールや行事に配慮した対応も、良好な関係維持には欠かせません。
【ドライバー採用をお考えの担当者様へ】
ドライバー採用ならカラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。
▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら
8.高卒採用後|離職を防ぐために企業がすべきこと

時間と労力をかけて採用した高卒の新入社員が、わずか数ヶ月で辞めてしまうのは、企業にとって大きな損失です。だからこそ、採用して終わりではなく、「どうすれば辞めずに定着してくれるか」を考えることが大切です。
この項目では、高卒社員の離職を防ぐために企業が取り組むべき具体的なポイントを紹介します。
高卒者の特性を活かした配属と育成
高卒者の特性を最大限に活かすためには、適切な配属と育成プランが重要です。
まず配属に関しては、入社直後から高度な専門知識や判断を求められる部署ではなく、基本的な業務スキルを身につけられる現場が望ましいです。
たとえば、製造業であれば生産ラインでの実務経験を積ませるなど、企業の基幹業務を理解できる環境を提供しましょう。
育成面では、OJTと集合研修をバランスよく組み合わせた計画が効果的です。特に入社1~3年目は基礎的なビジネススキルの習得に重点を置き、段階的に責任ある業務へとシフトしていくことが重要です。
また、先輩社員がマンツーマンで指導するメンター制度は、高卒者の不安を解消し、スムーズな職場適応を促進する効果があります。
高卒者の「素直さ」と「吸収力の高さ」を活かし、明確な目標設定と定期的なフィードバックを通じて成長を促すことで、将来の中核人材へと育てることができるでしょう。
入社後のフォロー体制の整備
高卒者の定着率を向上させるためには、入社後のフォロー体制も重要です。特に入社直後の3ヶ月~1年は、社会人としての基礎を身につける重要な時期であり、手厚いサポートが必要です。
まず、定期的な面談制度を導入し、業務の習熟度や悩みを把握しましょう。上司や人事部だけでなく、メンターなど複数の視点からフォローすることで、早期の問題発見と対応が可能になります。
また、業務の割り当ては段階的に行い、達成感を味わいながら成長できるよう配慮しましょう。最初から高度な業務を任せるのではなく、基本的な作業から徐々にレベルアップしていくのが理想的です。
さらに、社内に悩み相談窓口を設置し、業務だけでなく、生活面や人間関係の相談にも対応できる体制を整えることで、高卒者が安心して働ける環境を作れます。

高卒者向けの研修を定期的に実施し、同期との絆を深める機会を提供することも定着率向上に効果的です。
メンター制度の導入と効果
メンターとは、業務指導だけでなく、精神的なサポートも行う先輩社員のことを指します。入社後すぐにメンターを任命し、仕事の進め方や職場での人間関係など、新入社員が直面する様々な課題をサポートする体制を整えましょう。
メンターには入社3~5年目の若手社員を選ぶことで、新入社員も相談しやすい関係が構築できます。
メンター制度は新入社員の成長だけでなく、メンター自身のマネジメント能力向上にもつながり、組織全体の活性化も期待できるでしょう。
高卒者の定着率を高める職場環境づくり
高卒者の定着率を高めるためには、彼らが働きやすいと感じる職場環境の整備が不可欠です。
まず、年代の近い社員との交流機会を意図的に創出することが効果的です。若手社員同士の勉強会や親睦会、プロジェクトチームへの参加など、同年代の仲間と切磋琢磨できる環境を提供しましょう。このような横のつながりは、仕事の悩みを共有したり、励まし合ったりする重要なサポート網となります。
また、適切な評価とフィードバックも重要です。高卒者は社会人経験が浅いため、自分の仕事ぶりや成長を客観的に把握することが難しい場合があります。定期的に具体的なフィードバックを行い、成長を実感できる環境作りを意識しましょう。
▼効果的なフィードバック方法とは?
以下の記事では、フィードバックの基本から実践的なテクニックまで解説しています。効果的な伝え方と受け方のポイントを、具体例を交えて紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
9.高卒採用における注意点

高卒採用を実施する際には、法令遵守や倫理的配慮が不可欠です。
不適切な選考や対応は、企業イメージの低下だけでなく、法的トラブルにつながる可能性もあります。ここでは、高卒採用において特に注意すべきポイントを解説します。
選考過程での差別的扱い
高卒採用を含むすべての採用活動は、公正な選考が大原則です。特に高校生は社会経験が乏しく、企業側が優位な立場にあるため、差別的扱いに対する配慮が一層重要になります。
選考過程において、以下のような質問は就職差別につながる恐れがあり、職業安定法や職業安定法施行規則等に抵触する可能性があるため注意が必要です。
- 本籍地
- 家族構成
- 家族の職業
- 宗教
- 支持政党
- その他、応募者の適正や能力に関係のない事項
面接時の何気ない会話や雑談の中で、無意識に不適切な質問をしてしまうケースもよく見られます。面接官には事前に公正採用選考の原則を教育し、質問内容を統一しておきましょう。
また、学校での成績や部活動の実績などは、業務との関連性が明確であれば質問しても問題ありません。ただし、プライバシーに配慮した質問方法を心がけましょう。
選考においては、応募者の能力や適性、意欲など、職務遂行に直接関連する要素に基づいて判断することが重要です。
▼面接官の心得とは!
以下の記事では、ドライバー採用を成功させる面接官テクニックを解説しています。面接官の心得から具体的な質問例、NG言動なども詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
応募前職場見学での禁止事項
応募前職場見学は、生徒が企業や仕事への理解を深める重要な機会ですが、いくつか禁止事項があります。
最も重要なのは、職場見学を選考の場として利用してはならないという点です。見学時に面接のような質問をしたり、評価シートを作成したりすることは避けてください。職場見学はあくまでも情報提供の場であり、見学後の応募を強制することもできません。
また、見学時に過度な個人情報を収集することも控えましょう。氏名や学校名など、必要最小限の情報に留めることが重要です。
日程設定においては、学校行事や試験期間を避け、学業への影響を最小限に抑える配慮が必要です。見学時間も長時間に及ばないよう適切に設定し、生徒の負担に配慮することが重要です。
職場見学では、企業の良い面だけでなく、仕事の大変さや課題なども含めて現実的な情報を提供することが、入社後のミスマッチを防ぎます。また、生徒が質問しやすい雰囲気づくりを心がけ、疑問や不安に丁寧に応えることで、企業への信頼感を高めることができるでしょう。
【ドライバー採用をお考えの担当者様へ】
ドライバー採用ならカラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。
▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら
10.高卒採用の最新動向と今後の展望

高卒採用を取り巻く環境は、社会情勢の変化や技術の進化に伴い、大きく変化しています。企業は、新しい動向を把握し、柔軟に対応することが求められています。ここでは、高卒採用の最新動向と今後の展望について解説します。
一人一社制の変化と今後の見通し
長年高卒採用の特徴とされてきた「一人一社制」は、近年大きく見直されています。9月の選考開始時点から複数の企業へ応募を認めている県もあれば、一定期間は一人一社制を適用し、その後に複数応募を可能とする県もあるなど、対応はさまざまです。
今後も、この緩和の流れは全国的に広がっていくことが予想されます。特に人手不足が深刻な地域や業種では、より積極的な見直しが進むでしょう。企業側にとっては、複数応募が可能になることで、人材確保の競争が激化することを意味します。
応募の早期化を図るとともに、自社の魅力をより効果的に伝える工夫が必要となるでしょう。教育制度や将来のキャリアパスの明確化、職場環境の整備など、他社との差別化ポイントを明確にすることが重要です。
デジタル化が進む高卒採用
高卒採用においても、デジタル技術の活用が急速に進んでいます。特にコロナ禍を契機に、オンライン職場見学やバーチャル工場見学などの取り組みが増加しました。
地理的な制約を受けずに企業情報を提供できるため、ポストコロナ時代でも継続して活用されています。また、求人情報のデジタル化も進んでおり、QRコードを活用した詳細情報の提供や、動画による会社紹介など、より視覚的でわかりやすい情報提供が一般的になっています。
選考プロセスにおいても部分的にオンライン面接が導入されるケースが増えています。特に遠方の生徒に対する一次面接や、急な日程変更が必要な場合などに活用されています。ただし、高卒採用においては最終的な選考は対面で行われるケースが依然として主流です。
これは、高校生の場合、オンラインよりも対面でのコミュニケーションの方が本人の人柄や適性を見極めやすいという判断からです。
今後もデジタル技術とリアルな交流を適切に組み合わせたハイブリッドな採用活動が主流になっていくでしょう。特に、SNSやウェブサイトを活用した日常的な企業情報の発信は、採用活動期間外でも生徒の関心を高めるうえで重要な取り組みとなっています。
高卒採用市場の変化と対応策
少子化による高校生人口の減少と大学進学率の上昇により、高卒就職市場は大きな変化を迎えています。就職希望者数が減少していることで、人材確保の競争が激化しているのです。
また、現代の高校生は従来と比べてデジタルリテラシーが高く、情報収集能力や価値観も大きく変化しています。これらの変化に対応するためにも、従来型の採用活動だけでなく、新たなアプローチが必要です。
特に重要なのは他社との差別化戦略です。給与や福利厚生だけでなく、教育研修制度の充実や明確なキャリアパスの提示、ワークライフバランスへの配慮など、若者が重視する要素を強化することが効果的です。
また、地域に根差した採用活動も重要です。高校との継続的な関係構築や、地域貢献活動を通じた企業イメージの向上などは、地元志向の強い高卒者の獲得につながるでしょう。
さらに、インターンシップや体験型プログラムの充実も効果的です。短期間でも実際の業務を体験することで、入社後のミスマッチを防ぎ、仕事への理解と意欲を高めることができます。
11.高卒採用を成功に導く戦略

高卒採用は独自のルールやスケジュールが存在する特殊な採用活動です。しかし、適切な戦略と準備によって、企業の将来を担う優秀な人材を獲得することができるでしょう。
ここでは、これまでの内容を踏まえ、高卒採用成功のための総合チェックリストと自社に合った採用プランの作り方をまとめます。
高卒採用成功のための総合チェックリスト
高卒採用を成功させるためには、計画的かつ体系的な取り組みが必要です。以下のリストを活用して、自社の高卒採用活動をチェックしてみましょう。
| 法令・ルールの理解 □ 一人一社制の地域ごとの運用状況を把握している □ 高卒採用のスケジュールを理解し、準備を進めている □ ハローワーク指定の求人票の記載ルールを理解している 採用計画の立案 □ 採用人数と職種、配属先を明確に決定している □ 求める人物像を具体的に定義している □ 採用活動の担当者と役割分担を決めている 求人票・応募書類の準備 □ 魅力的かつ正確な求人票を作成している □ 青少年雇用情報を詳細に記載している □ 会社案内や補足資料を準備している 学校・教諭との関係構築 □ ターゲット校を選定し、進路指導教諭と連携している □ 学校の企業説明会や職業講話に参加している □ 過去の採用実績や卒業生の活躍状況を伝えている 応募前職場見学の準備 □ 見学プログラムを計画し、担当者を決めている □ 若手社員(できれば高卒入社者)の参加を手配している □ 質問しやすい雰囲気づくりに配慮している 面接・選考の準備 □ 面接官を選定し、公正な選考についての教育を実施している □ 面接の質問内容や評価基準を統一している □ 高校生の緊張を和らげる工夫をしている 内定後のフォロー □ 定期的な連絡体制を整えている □ 入社前研修や企業情報の提供を計画している □ 内定者同士の交流機会を設けている 入社後の育成計画 □ 研修プログラムを整備している □ メンター制度など育成体制を整えている □ 定期的な面談や評価の仕組みを構築している 評価と改善 □ 採用活動全体を振り返り、成果と課題を整理している □ 内定者・入社者からのフィードバックを収集している □ 次年度の採用活動に向けた改善点を明確にしている |
このチェックリストを定期的に確認し、必要な対応を迅速に行いましょう。
自社に合った高卒採用プランの作り方
効果的に高卒採用を進めるためには、自社の特性や状況に合わせたプランを作成することが重要です。
以下の手順で、自社に最適な高卒採用プランを策定してみましょう。
- 自社の現状分析
現在の人員構成や年齢バランス、将来の人材ニーズ、育成環境などを客観的に評価します。特に、高卒者を受け入れる現場の体制や教育能力を確認することが重要です。 - 高卒採用の目的を明確化
単なる人員補充なのか、将来の幹部候補の育成なのか、技能継承なのかなど、採用の目的によって求める人物像や採用後の育成方針が変わってきます。 - ターゲット校の選定
地域性、学科(普通科、商業科、工業科など)、過去の採用実績などを考慮し、自社に合った人材を輩出している高校を選びます。継続的な採用関係を構築できる学校を見つけることが、長期的な採用成功につながります。 - 採用スケジュールをたてる
地域のルールに合わせて策定し、各段階での担当者や必要なリソースを確認しておきましょう。 - 採用基準を具体的に設定する
「前向きな姿勢がある」のような抽象的な表現ではなく、「質問に対して自分の言葉で具体的に答えられる」「部活動や学校行事で最後まで粘り強く取り組んだ経験がある」など、具体的な基準を設けることが重要です。 - 入社後の定着・育成策を作成する
研修制度、メンター制度、評価制度などを整備し、高卒者が着実に成長できる環境を整えましょう。
今後も高卒採用を長期的に考えている場合は、採用活動の成果を測定するための指標(応募倍率、内定承諾率、入社後の定着率など)を設定するとよいでしょう。PDCAサイクルを回すことで、継続的な採用活動の改善が目指せます。
【ドライバー採用をお考えの担当者様へ】
ドライバー採用ならカラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。
▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら
12.「計画的な準備」と「受け入れ環境」で高卒採用を成功させる
本記事では、高卒採用の基本的な定義から最新の動向、採用を成功させるためのポイントなどを解説しました。
高卒採用は、若く柔軟な人材を早期に育成できる貴重な機会です。人件費を抑えつつ、地域に根ざした人材の安定的な確保が可能であり、定着率の向上も期待できます。
また、学校推薦制度を活用することでミスマッチを減らし、企業文化に合った人材を採用しやすくなる点も大きな魅力です。長期的な視点で人材育成に取り組むためには、高卒採用は非常に有効な手段といえるでしょう。
ぜひ本記事を参考に、高卒採用の成功に向けた一歩を踏み出してみてください。