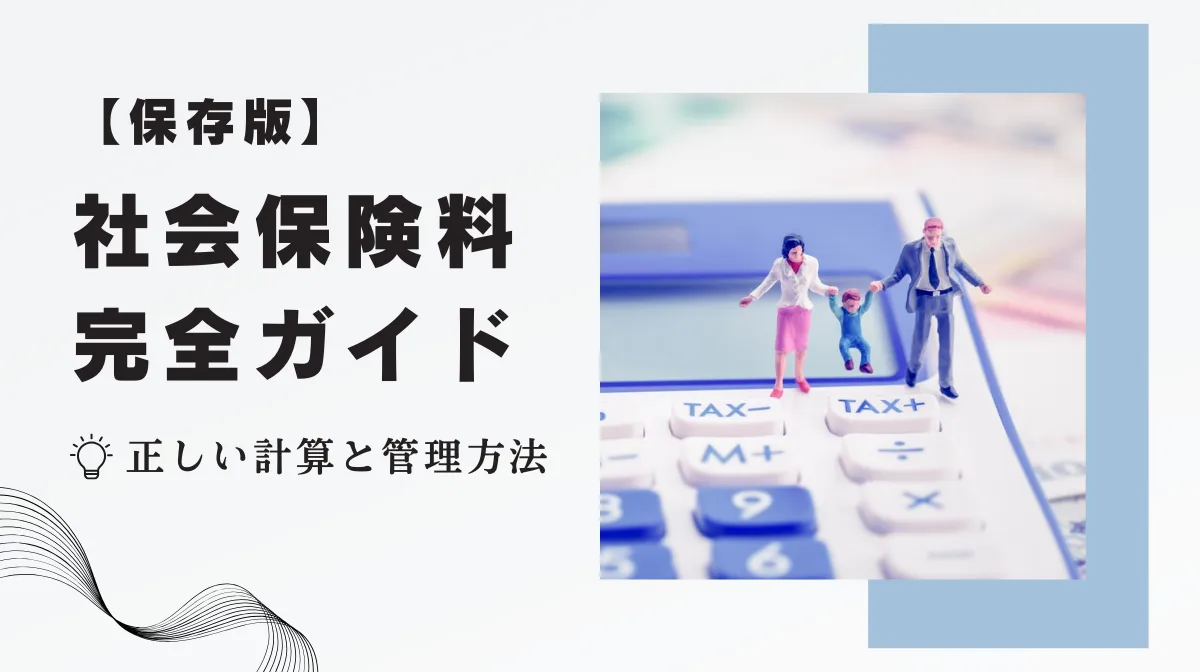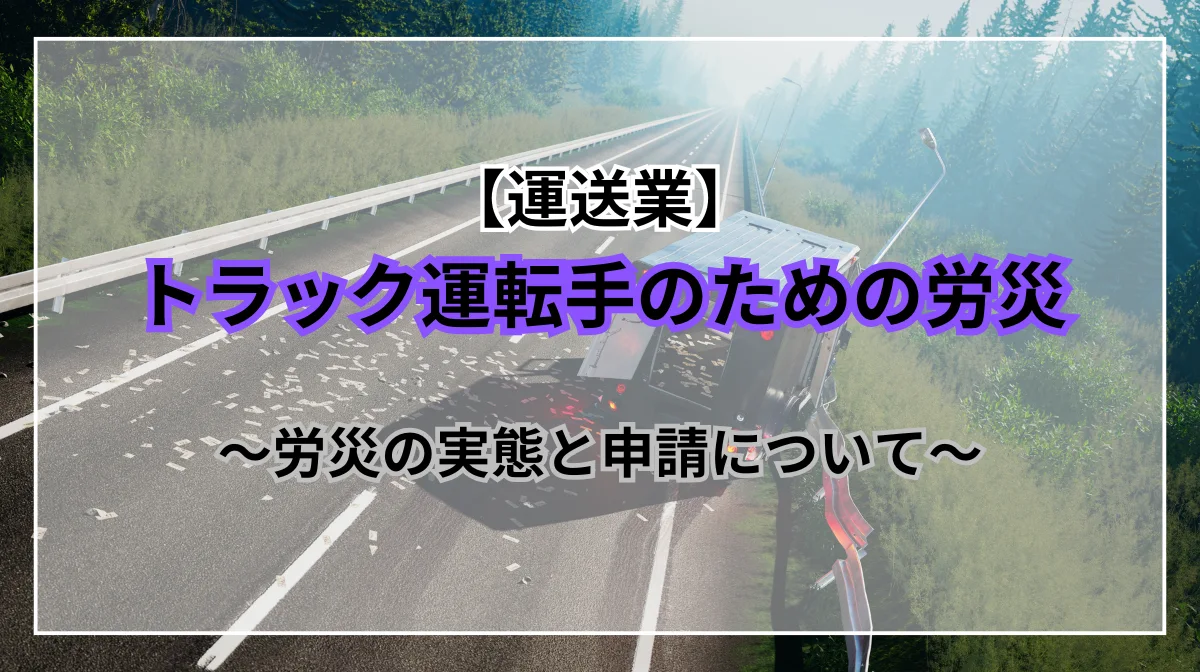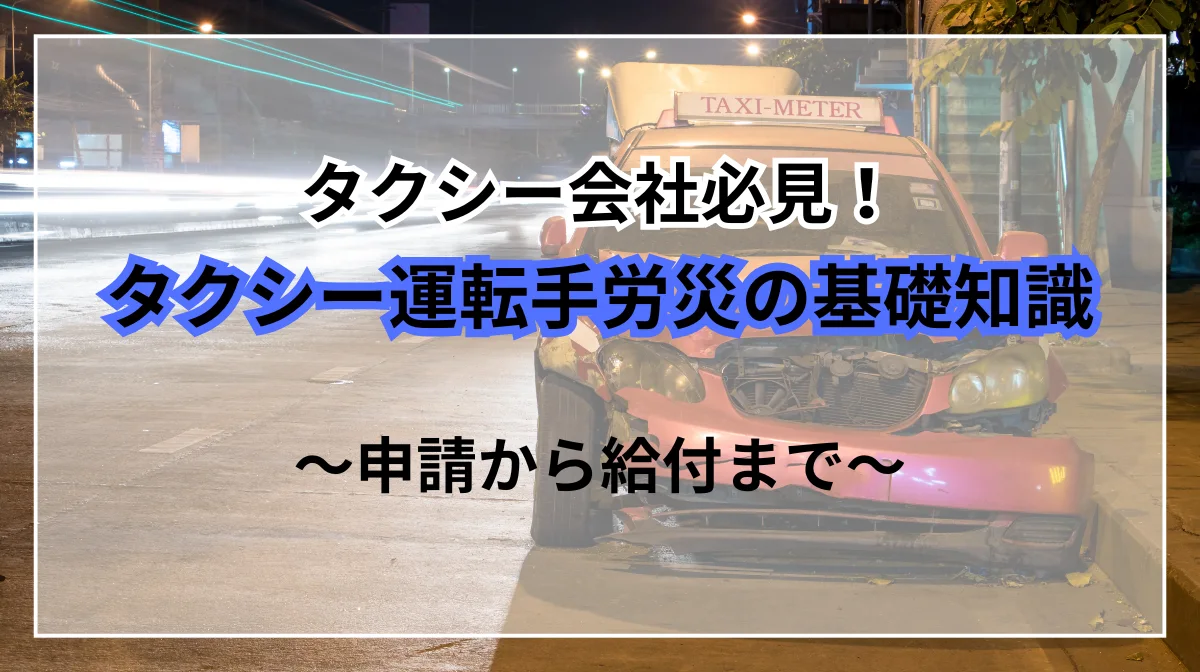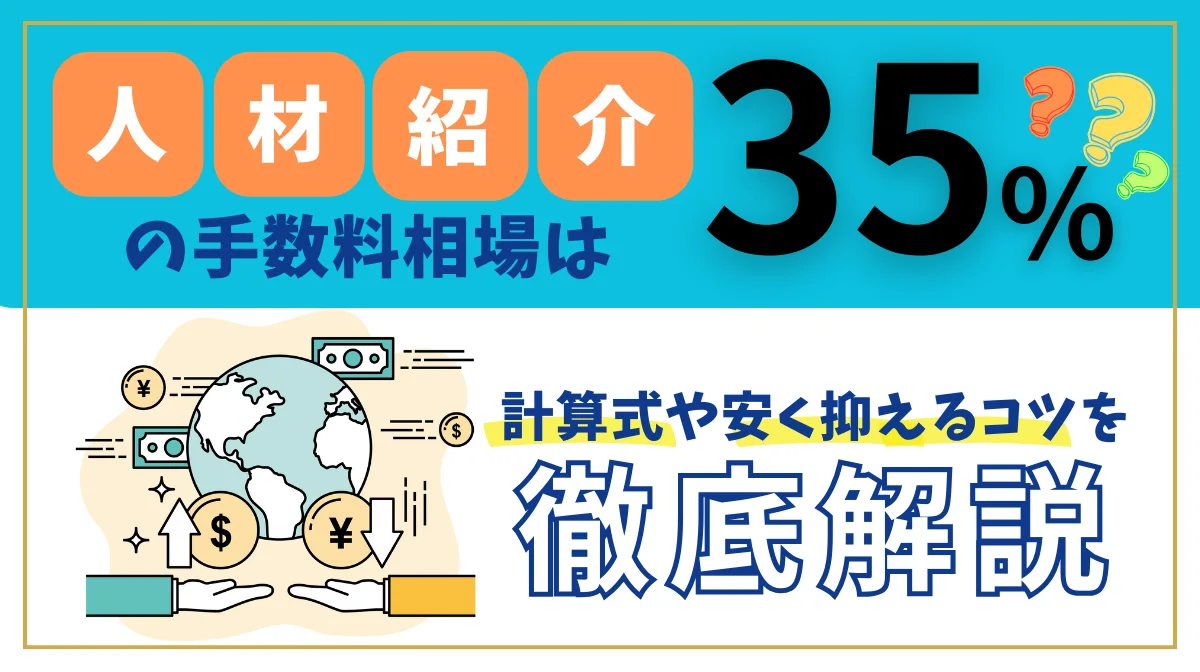企業における社会保険料の管理は、経営者にとって重要な責務の一つです。
健康保険や厚生年金保険など5つの社会保険制度について、それぞれの計算方法や負担割合を正しく理解し、適切に管理することが求められます。
本記事では、企業の社会保険料について基本的な知識から実務上の注意点まで、わかりやすく解説していきます。
- 5つの社会保険の種類と企業負担の範囲について
- 各社会保険料の具体的な計算方法と実例
- 社会保険料の決定タイミングと改定のポイント
1.企業における社会保険料の基本とは

企業が従業員のために加入が義務付けられている社会保険制度について解説します。健康保険や厚生年金など5つの保険制度の基本的な仕組みと、企業の負担割合、納付方法などをわかりやすく説明していきます。
企業における社会保険料とは?
企業における社会保険料とは、5つの社会保険に対する保険料のことです。
5つの社会保険とは「健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険」であり、国や地方自治体によって運営されている保険制度です。
企業に勤める人は、社会保険の加入条件に該当する場合、加入が義務付けられています。
5つを「広義の社会保険」とし、そのうちの「健康保険・厚生年金保険・介護保険」の3つは「狭義の社会保険」、「雇用保険・労災保険」の2つは「労働保険」とも呼ばれています。
社会保険料の種類と企業負担の範囲
5つの社会保険について、それぞれの保険料の内容は、以下の通りです。
| 健康保険料 | 病気・ケガをした時に使う保険料(労災以外の病気・ケガ) |
| 厚生年金保険料 | 老後、障害、死亡などに備える保険料 |
| 介護保険料 | 介護サービスの利用に必要な保険料(要介護・要支援認定を受けた場合) |
| 雇用保険料 | 雇用保険料:失業や産休・育休に備える保険料 |
| 労災保険料 | 労働災害(労災)に備える保険料 |
企業が負担する社会保険料の割合は、以下の通りです。
| 健康保険 | 50%(※1) |
| 厚生年金保険 | 50%(※2) |
| 介護保険 | 50%(※3) |
| 雇用保険 | 業種によって異なる(※4) |
| 労災保険 | 100%(※5) |
※1 参考:健康保険法 第161条|e-Gov法令検索
※2 参考:厚生年金保険の保険料|厚生年金機構
※3 参考:介護保険制度について|厚生労働省
※4 参考:令和6年度の雇用保険料率について|厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
※5 参考:労働保険料の申告・納付|厚生労働省
健康保険・厚生年金保険・介護保険に関しては、業種・職種にかかわらず、企業負担50%、従業員負担50%です。なお、労災保険については、従業員負担はなく、100%企業負担です。
企業は従業員負担分の保険料を毎月の給与から天引きし、企業負担分とあわせて納付します。
期限は、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料については翌月末日です。納付期限は社会保険によって異なるので注意しましょう。
雇用保険料に関しては、従業員負担分の保険料を分割し、各月の給与額から天引きし、企業負担分とあわせた上で1年分をまとめて納付します。
健康保険料と厚生年金保険料は従業員と企業で折半
健康保険料と厚生年金保険料は、企業と従業員の折半になります。
標準報酬月額とは、平均額などから算出した制度上の月収のことです。また保険料率は、企業の所在地や年度によって異なります。決定した健康保険料と厚生年金保険料は、企業と従業員それぞれが50%負担します。
令和6年度の東京都における健康保険料率と厚生年金保険料率は、以下の通りです。なお、数値は令和6年3月分(4月納付分)から適用になっているものです。
- 健康保険料率:9.98%
- 厚生年金保険料率:18.30%
上記の保険料率は、企業と従業員の折半になるので、企業が負担する保険料率は、健康保険料率が4.9%、厚生年金保険料率が9.15%になります。
企業の社会保険料加入条件
法人企業であれば社会保険の加入を義務付けられています。たとえ1人経営であっても、社長自らが加入する必要があります。
また法人化していない個人事業所であっても、従業員を5人以上雇用している場合は加入義務が発生します。
社会保険に加入している事業所は「適用事業所」と呼ばれ、適用事業所で働く正社員、法人代表者、役員は原則として、社会保険の被保険者です。
パートタイマーやアルバイトについては、所定の労働時間や労働日数が正社員の「4分の3基準」など、いくつかの加入条件があります。
短時間労働者(パートタイマー・アルバイト)の加入条件
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 雇用契約期間が2か月と1日以上である。(雇用契約が2か月以内であっても、就業規則や雇用契約書などに、契約について「更新される」旨や「更新される場合がある」旨の明確な記載がある)
- 賃金が月額88,000円以上
- 昼間学生ではない
- 厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の事業所に勤務している ※2024年10月に被保険者数が以前の「101名以上」から変更
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内
これらの条件に該当する従業員は、パートタイマーやアルバイトなどの雇用形態にかかわらず、社会保険に加入する義務があります。
2.社会保険料の計算方法

社会保険料は従業員の標準報酬月額や標準賞与額、社会保険の種類によってそれぞれ定められている保険料率から算出します。
健康保険料の計算方法
健康保険料の計算式
健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率
健康保険料は「標準報酬月額」に健康保険料率を掛けて算出するため、まず標準報酬月額を保険料額表から確認します。
これは従業員の社会保険料を計算する際、もとになる金額で、計算しやすいように月給が等級別に区分されています。
標準報酬月額の等級は1~50等級まであり、標準報酬月額表を見れば簡単に把握できます。健康保険料率は、各都道府県で異なるので、事業所のある都道府県の保険料率を確認してください。
実際の計算例
- 月給25万円の健康保険料(標準報酬月額が20等級の26万円)※協会けんぽで東京都の場合
健康保険料=26万円(標準報酬月額)×9.98%=25,948円
企業負担額は50%なので【25,948円×50%=12,974円】 - 月給35万円の健康保険料(標準報酬月額が25等級の36万円)※協会けんぽで東京都の場合
健康保険料=36万円(標準報酬月額)×9.98%=35,928円
企業負担額は50%なので【35,928円×50%=17,964円】
厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料の計算式
厚生年金保険料=標準報酬月額×厚生年金保険料率
厚生年金保険料は、「標準報酬月額」に厚生年金保険料率を掛けて算出します。厚生年金保険料率は、以前は毎年改定されていましたが、2017年9月以降、18.300%で固定されています。
これを企業と従業員が折半するので、企業負担は9.15%です。健康保険料率とは違い、全国で統一されているのが特徴です。
実際の計算例
- 月給25万円の厚生年金保険料(標準報酬月額が20等級の26万円)※協会けんぽで東京都の場合
厚生年金保険料=26万円(標準報酬月額)×18.300%=47,580円
企業負担額は50%なので【47,580円×50%=23,790円】 - 月給35万円の厚生年金保険料(標準報酬月額が25等級の36万円)※協会けんぽで東京都の場合
厚生年金保険料=36万円(標準報酬月額)×18.300%=65,880円
企業負担額は50%なので【65,880円×50%=32,940円】
介護保険料の計算方法
介護保険料の計算式
介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率
介護保険料は「標準報酬月額」に介護保険料率を掛けて算出しますが、介護保険料率は健康保険組合によって異なります。
例えば協会けんぽにおいては、毎年更新されますが、令和6年度の介護保険料率は、3月分(4月納付分)からの適用で、全国一律の1.60%です。
こちらも健康保険料や厚生年金保険料と同様、企業と従業員で折半します。
介護保険料は従業員全員が対象ではなく、40歳以上の従業員が対象です。40~64歳までは第2号被保険者となるため、健康保険料・厚生年金保険料と合算して給料から天引きします。
65歳以上は第1号被保険者となるため、企業に勤めている場合でも、居住する各市町村に個人で納付します。
実際の計算例
- 月給25万円の介護保険料(標準報酬月額が20等級の26万円)※協会けんぽで東京都の場合
介護保険料=26万円(標準報酬月額)×1.6%=4,160円
企業負担額は50%なので【4,160円×50%=2,080円】 - 月給35万円の介護保険料(標準報酬月額が25等級の36万円)※協会けんぽで東京都の場合
介護保険料=36万円(標準報酬月額)×1.6%=5,760円
企業負担額は50%なので【5,760円×50%=2,880円】
雇用保険料の計算方法
雇用保険料の計算式
雇用保険=賃金(総支給額)×雇用保険料率
雇用保険料は「賃金(総支給額)」に雇用保険料率を掛けて算出します。標準報酬月額のような仕組みはなく、毎月の賃金によって保険料額が変動します。
また、健康保険料や厚生年金保険料などと同様、給与からの天引きです。
雇用保険料の計算に用いる「賃金(総支給額)」に含まれるのは基本給だけではありません。雇用保険料の算出対象となる賃金には、基本給のほかに賞与や各種手当も含まれます。
雇用保険料の算出対象となる賃金
- 賞与(ボーナス)
- 通勤手当
- 残業手当・深夜手当・休日出勤手当
- 扶養手当・家族手当・子供手当
- 教育手当・特殊作業手当・技能手当
- 住宅手当
- 地域手当
- 皆勤手当、精勤手当などの奨励手当
- 休業手当
- 宿直手当・日直手当
一方、雇用保険料の対象にならない賃金もあります。以下の賃金は、雇用保険料の対象外です。
雇用保険料の対象にならない賃金
- 役員報酬
- 退職金・結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金・年功慰労金・勤続褒賞金
- 出張旅費や宿泊費
- 休業補償費
- 傷病手当金
- 解雇予告手当
雇用保険料率は業種によって異なり、毎年見直されていますが、どの業種においても、従業員よりも企業が多く負担する仕組みになっています。主な業種の雇用保険料率は以下の通りです。
- 一般の事業
従業員負担:6/1,000
企業負担:9.5/1,000 - 農林水産・清酒製造の事業
従業員負担:7/1,000
企業負担:10.5/1,000 - 建設の事業
従業員負担:7/1,000
企業負担:11.5/1,000
参考:社会保険料とは 給与から控除する保険料の計算方法を解説|日本の人事部
実際の計算例
- 基本賃金25万円、通勤手当1万円、家族手当2万円、残業代1万円、合計29万円の雇用保険料(一般事業)
従業員が負担する雇用保険料=29万円×0.6%=1,740円
企業が負担する雇用保険料=29万円×0.95%=2,755円
参考:
雇用保険料の対象となる賃金|厚生労働省
令和6年度の雇用保険料率について|厚生労働省
3.社会保険料が決まるタイミング
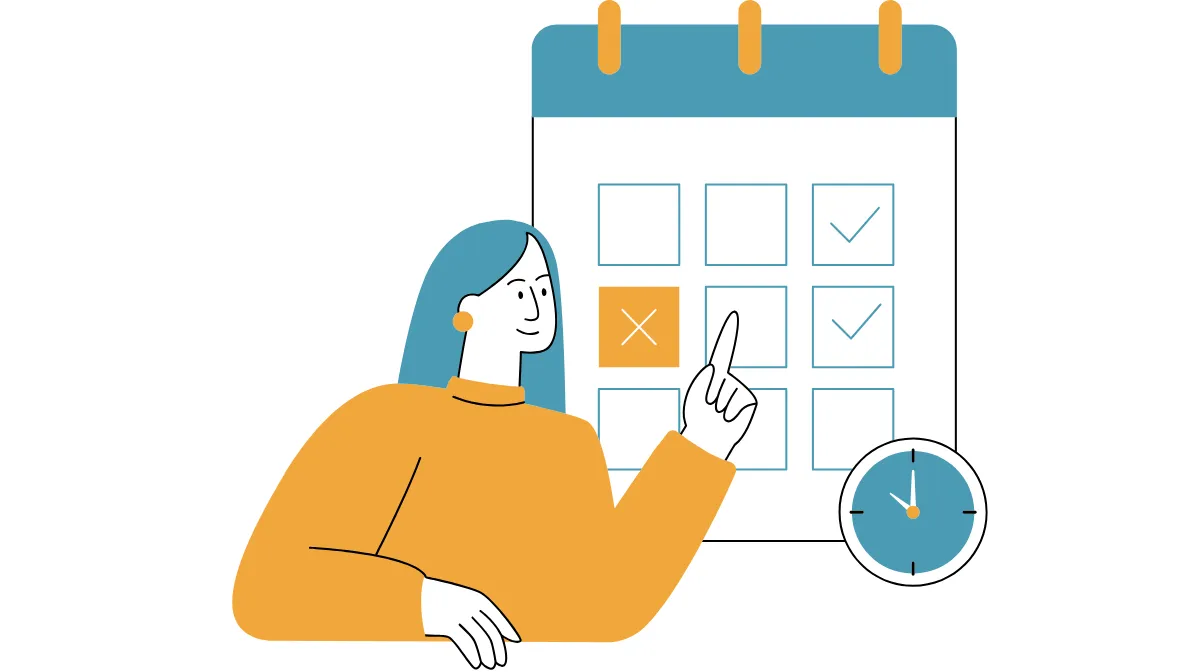
社会保険料が決まる、下記の3つのタイミングについてそれぞれ解説します。
入社のタイミング
入社したばかりの従業員はまだ給料が支払われていない状態なので、入社後に受け取ると思われる給料額をもとにして標準報酬月額を決定します。
定時改定
社会保険料は定時改定のタイミングで決まります。定時改定とは、毎月4月~6月の給与をもとに計算する「標準報酬月額」の定期的な見直しのことです。
毎年7月に提出する算定基礎届によって決定され、変更された標準報酬月額が適用されるのは9月からです。
随時改定
社会保険料は随時改定のタイミングで決定します。随時改定とは毎月支給される給与が変更になった場合に、標準報酬月額を変更することです。
随時改定は以下の条件をすべて満たした場合に行います。
- 昇給・降給などによる固定賃金が変動
- 変動月から3か月の間に支給された報酬の平均月額に該当する「標準報酬月額」と、これまでの「標準報酬月額」との間に、2等級以上の差が生じている
- 変動月からの3か月間、すべての月で支払基礎日数が17日以上
4.ボーナス(賞与)にも社会保険料の控除が必要

ボーナス(賞与)の支払いにおいても、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料などの社会保険料の控除が必要です。
ボーナスの社会保険料は標準報酬月額・保険料額表は使用せず、「標準賞与額」を使用します。
標準賞与額とはボーナス額から1,000円未満を切り捨てた金額です。標準賞与額に保険料率を掛けて、社会保険料を計算します。
ボーナス(賞与)の社会保険料の計算式
- 健康保険料
保険料=標準賞与額×健康保険料率÷2 ※保険料率は地域や年度により異なる - 厚生年金保険料
保険料=標準賞与額×厚生年金保険料率÷2 ※現在の保険料率は18.3%で固定 - 介護保険料
保険料=標準賞与額×介護保険料率÷2 ※令和6年の保険料率は全国一律1.6% - 雇用保険料
保険料=賞与支給額×雇用保険料率 ※保険料率は業種により異なる
5.【社会保険料】よくある質問
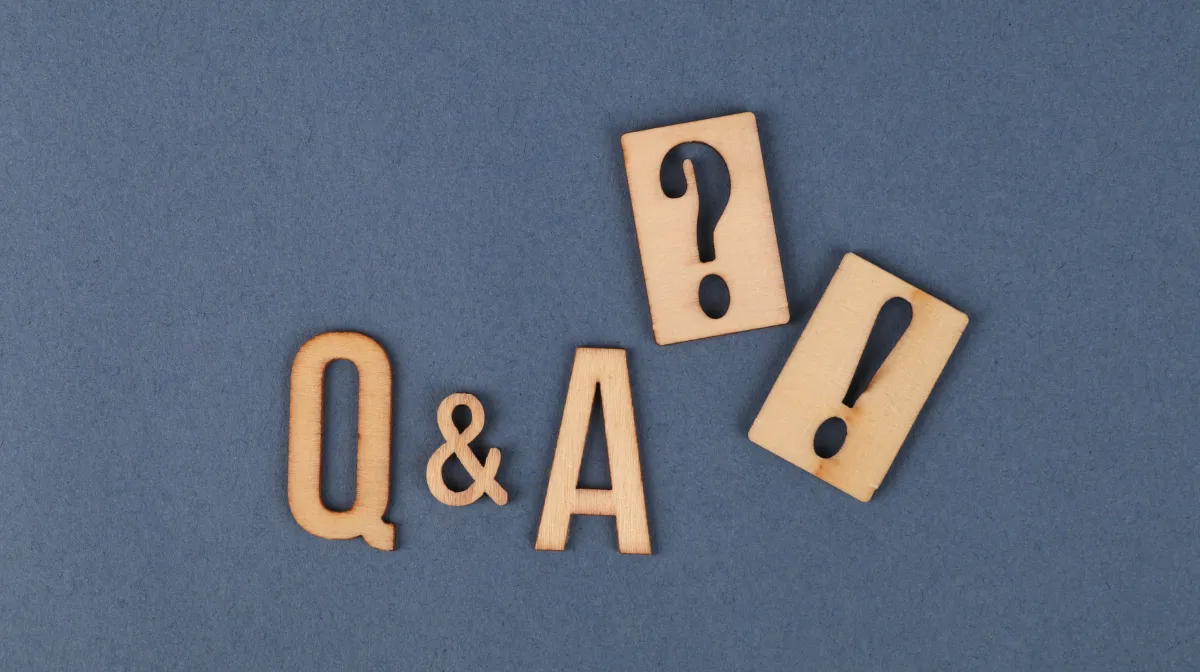
社会保険についてよくある質問をまとめました。
企業が社会保険の徴収を間違えたらどうしたらいいですか?
企業側の問題で社会保険の徴収ミスが発生した場合、従業員に対してすみやかにお詫びをしましょう。従業員との信頼関係を保つためにも、謝罪や説明をきちんと行ってください。
その際、社会保険料を計算する段階でのミスだったのか、従業員から徴収する段階でのミスだったのか等、細かく状況を伝えます。さらに、過不足分をどのように清算する必要があるかを明確に説明しましょう。
計算を間違えていた項目は修正して、再計算した正しい金額を記載した給与明細を再発行します。社会保険料の正しい金額を算出した後、過不足分を精算します。
過剰に徴収していた場合は従業員に返金し、不足している場合は追加で徴収してください。ただし、追加徴収が必要な場合、企業側がすべて負担するケースもあります。

清算のタイミングとしては、当月中に清算する/翌月以降の給与計算の中で清算する/年末調整で清算するの3つからの選択になります。
休職中の従業員も社会保険の支払い義務はありますか?
休職中の従業員も社会保険の支払い義務はあります。休職していても従業員に対して社会保険料が発生しているため、当然支払わなければなりません。
本人が支払う、また企業が立て替えるなど、各企業によって対応は異なります。企業が立て替えた場合には、復職後などに本人に支払いを求めます。
ただし、休職からそのまま退職となり、立て替え分を返却してもらえないおそれがあり、トラブルになりかねません。

トラブルを防ぐために、あらかじめ従業員と取り決めをしておくことをおすすめします。
5.適切な社会保険料管理で築く健全な企業運営
社会保険料の適切な管理は、企業の法令順守と従業員の福利厚生の両面で重要な役割を果たします。
健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの保険制度について、それぞれの特徴と計算方法を理解し、正確な徴収と納付を行うことが求められます。
特に保険料率の改定や従業員の状況変更には細心の注意を払い、定期的な見直しと確認を怠らないようにしましょう。適切な社会保険料の管理は、企業の健全な運営と従業員との信頼関係構築の基盤となります。