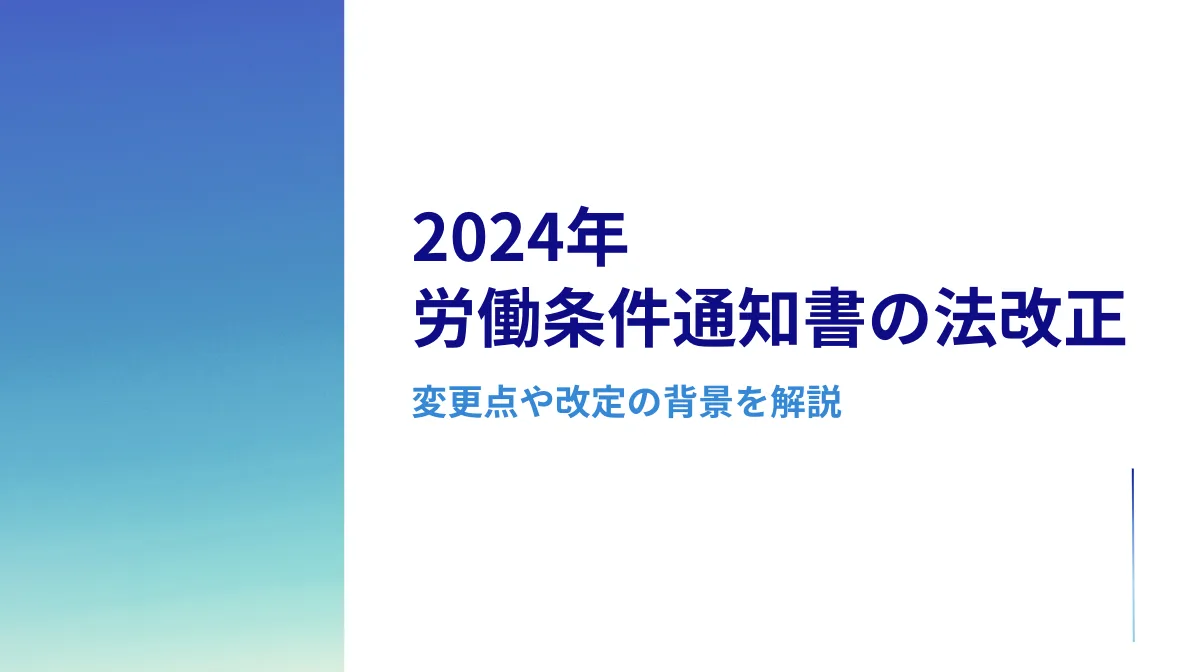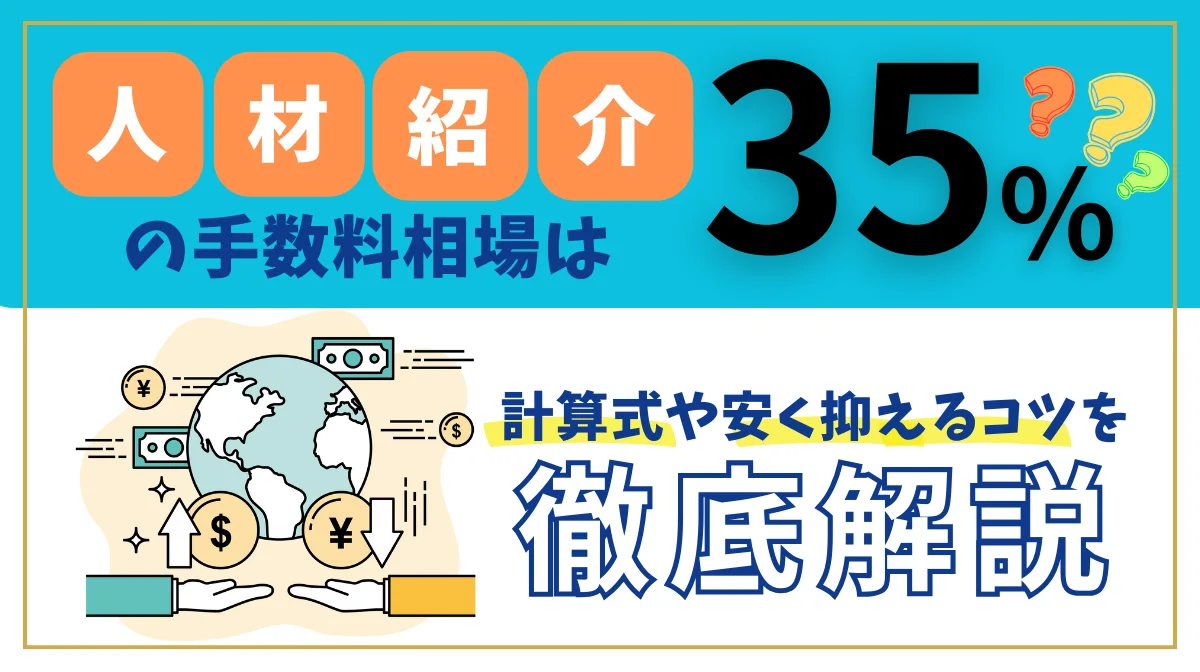2024年4月から労働条件通知書の記載事項が大幅に改正されました。就業場所や業務内容の具体的な明示、有期労働契約の更新上限の明確化、無期転換に関する権利の説明など、労働者の権利保護が強化されています。本記事では、改正の背景から具体的な改定ポイントを解説します。
- 労働条件通知書の2024年改正における必須記載事項と推奨事項の具体的な内容
- 有期労働契約の更新基準や無期転換制度に関する新しい開示ルール
- 就業場所や業務内容の明示に関する具体的な記載方法と注意点
1.労働条件通知書とは

労働条件通知書とは、労使間で雇用契約の条件を正確に共有し、双方が納得の上で雇用関係を結ぶために事業者が発行する文書を指します。
以下では、労働条件通知書の法的な位置づけや雇用契約書との違いについて解説します。
労働条件開示義務にともなう書面
労働条件通知書は、労働基準法第15条第1項によって、事業者が労働者と労働契約の締結をする際に発行が義務付けられている文書です。
詳しい内容については後述しますが、賃金や業務内容、契約期間などの労働条件の主な記載事項です。
従来は書面(紙)による発行しか認められていませんでした。しかし、2019年4月から、労働者が希望した場合に限りFAXやメールなどの電子媒体による発行も可能となりました。
雇用契約書との違い
労働条件通知書は、雇用契約書とは似て非なるものです。
その名の通り、労働条件通知書は労働条件の「通知」を目的としており、基本的には事業者が労働者へ一方的に交付します。また、上述した通り、労働条件通知書の交付は事業者に義務付けられています。
他方で、雇用契約書は、事業者と労働者双方の合意に基づいて署名捺印を行う「契約書」です。雇用契約は口頭での合意のみでも成立するため、雇用契約書の作成・交付は法的義務ではありません。
2.労働条件明示のルール改正の背景

近年の労働環境は、雇用形態の多様化や働き方の変化に伴い大きく変革しています。2024年の労働条件通知書改正は、これらの変化に対応し、労働者の権利保護と雇用の安定性を高めることを目指しています。
無期転換ルール
2013年の労働契約法改正により、有期雇用から無期雇用への円滑な移行を促進するルールが確立されました。契約社員が安定した雇用を得たり、アルバイトが正社員として長期的なキャリアを築いたりする機会が広がっています。
特に、5年を超えて更新された有期労働契約では、労働者からの申し込みにより無期労働契約への転換が可能となり、雇用の安定性が高まるとともに、企業にとっても優秀な人材の確保につながったりするなど、双方にメリットをもたらしています。
同一労働同一賃金の原則
2020年から2021年にかけての法改正により、雇用形態による不合理な待遇差の解消が求められるようになりました。正社員と非正規社員の間で基本給や手当に差をつけたり、福利厚生の利用を制限したりする場合には、その根拠を明確に示す必要があります。
また、職務内容や勤務時間が同じであれば、契約形態に関わらず同等の待遇を提供したり、能力や成果に応じた公平な評価を行ったりするなど、公正な処遇の実現が重要視されています。
働き方の多様化への対応
テレワークやフレックスタイム制が普及したり、勤務地や職種を限定した採用が増えたりするなど、従来の画一的な働き方からの転換が進んでいます。このような状況下では、在宅勤務時の通信費負担を明確にしたり、時短勤務者の評価基準を設定したりするなど、個々の労働条件を詳細に定める必要性が高まっています。
また、職種や勤務地の変更可能性について事前に合意したり、キャリアパスを明示したりすることで、労使間の信頼関係が強化されています。
3.2024年4月の労働条件通知書改正の主なポイント

労働条件通知書の2024年4月改正では、就業場所の明示や有期労働契約の更新基準など、労働者の権利を保護する重要な変更が加えられました。特に雇用条件の透明性向上が重視されています。
就業場所・業務内容の明示強化
労働条件通知書における就業場所と業務内容の明示が大幅に強化されました。改正後は、雇用直後の具体的な就業場所や業務内容を明確に示すだけでなく、将来的な配置転換などによって変更される可能性のある範囲までも具体的に記載することが必須となりました。
「会社の事情により変更することがある」といった曖昧な表現は認められず、労働者が将来的なキャリアパスを具体的にイメージできる内容の記載が求められています。
有期労働契約の更新上限に関する明示
有期労働契約における更新上限の明示に関する規定が厳格化されました。契約締結時に更新の基準と上限回数を明確に提示し、更新の都度、その時点での更新回数の上限の有無とその具体的な内容を労働者に明示する必要があります。
また、更新上限を新たに設定する場合や既存の上限を短縮する場合には、事前に労働者への丁寧な説明が求められ、労働者の将来設計に影響を与える重要な変更として扱われます。
無期転換に関する権利と条件の明示
無期転換制度に関する情報提供が義務化されました。通算契約期間が5年以上となる有期契約労働者に対して、雇用者は重要な情報開示を行う必要があります。具体的には、無期雇用への転換可能性とその手続き方法、さらには転換後の具体的な労働条件について、明確な説明を提供することが新たな要件となりました。
さらに、この労働条件通知書の改正では、既存の正社員や無期雇用者との待遇差に関する透明性も重視されています。契約更新時には、給与体系や福利厚生などの労働条件について、他の雇用形態との比較情報を提示することが求められるようになりました。これにより、労働者は自身のキャリアパスをより明確に描けるようになっています。
4.2024年の労働条件通知書改正における追記事項

2024年4月の労働条件通知書改正では、有期労働契約の更新基準や就業場所の明示など、必須記載事項が新たに定められました。さらに、高齢者の就業機会確保や退職金制度など、企業の自主的な取り組みを促す推奨事項も示されています。以下で詳しく解説します。
必須記載事項
2024年4月の法改正により、労働条件通知書には雇用者が必ず遵守しなければならない記載事項が定められました。この改正は労働者の権利保護と雇用条件の透明性確保を主な目的としており、すべての雇用者に対して厳格な情報開示を求めています。
特に、有期労働契約に関する事項と就業条件の明示について、具体的かつ明確な記載が必要とされています。
有期労働契約の更新と転換【有期契約労働者】
有期労働契約における重要な変更点として、契約更新の上限設定に関する明確な記載が義務付けられました。通算契約期間や更新回数の上限がある場合は、その具体的な内容を労働条件通知書に明記する必要があります。
また、5年を超える有期契約労働者に対しては、無期労働契約への転換機会について詳細な説明を提供することが求められています。
就業場所と業務内容の明示【全ての労働者】
就業条件の明示に関する要件が強化され、雇用開始時の就業場所や業務内容について具体的な記載が必要となりました。将来的な配置転換や業務内容の変更可能性についても、その範囲を明確に示すことが求められています。
「会社の都合により変更あり」といった曖昧な表現は認められず、労働者が将来のキャリアを具体的に計画できる情報提供が必要です。
注意点
労働条件通知書の記載においては、具体性と明確性が重視されます。たとえば、就業場所については「東京本社、または国内各支店」のように具体的な場所を明示し、業務内容も「営業職、将来的にマーケティングや広報への異動可能性あり」といった形で、現在の業務と将来的な可能性を明確に示す必要があります。一方で、「入社後に決定」といった不明確な記載は認められません。
推奨記載事項
法的な強制力はないものの、厚生労働省のモデル労働条件通知書では、高齢者の就業機会確保に関する情報や中小企業の退職金制度、就業規則の確認方法などの記載が推奨されています。
これらの情報は、労働者の長期的なキャリアプランニングを支援し、安定した雇用環境の整備に貢献することが期待されています。
創業支援等措置
少子高齢化に伴う労働力不足に対応するため、企業は70歳までの就業機会確保に関する情報提供が求められています。具体的には、経験豊富な先輩社員が若手の指導をしたり、短時間勤務で技術継承を担ったりするなど、柔軟な働き方を通じて高齢者の知識や技能を活用することが重要視されています。
また、高齢者が自身の体力や生活スタイルに合わせて働ける環境づくりを推進したり、新たな職務に挑戦する機会を提供したりすることで、組織の活性化にもつながります。
中小企業退職金共済制度・企業年金制度による追加事項
従業員の将来の経済的な安定を支援するため、中小企業における退職金制度や企業年金制度の整備が推奨されています。制度の内容として、長期勤続者への特別加算を設けたり、従業員の貢献度に応じた給付を行ったりするなど、働き手のモチベーション向上につながる工夫が求められています。
また、若手従業員の定着率を高めたり、熟練した先輩社員の継続雇用を促進したりするなど、人材確保の観点からも重要な役割を果たしています。
就業規則を確認できる場所・方法
労働者が自身の権利や義務を適切に理解し、働きやすい職場環境を実現するため、就業規則の確認方法と場所を明確に示すことが推奨されています。社内イントラネットで常時閲覧できる環境を整備したり、各部署に紙媒体を設置したりするなど、アクセスしやすい体制づくりが重要です。
また、定期的な説明会を開催して内容の理解を深めたり、改定時には速やかに周知したりすることで、労使間の信頼関係構築にも寄与します。
5.労働条件通知書改正で働きやすい世の中へ
2024年4月の労働条件通知書改正は、労働者の権利保護と雇用条件の透明性向上を目的としています。特に就業場所や業務内容の具体的な明示、有期労働契約の更新上限の明確化、無期転換制度に関する情報開示など、従来以上に詳細な記載が求められるようになりました。
また、高齢者の就業機会確保や退職金制度といった推奨事項も示され、より包括的な労働条件の提示が期待されています。企業は本改正の趣旨を理解し、適切な対応を進めることが重要です。