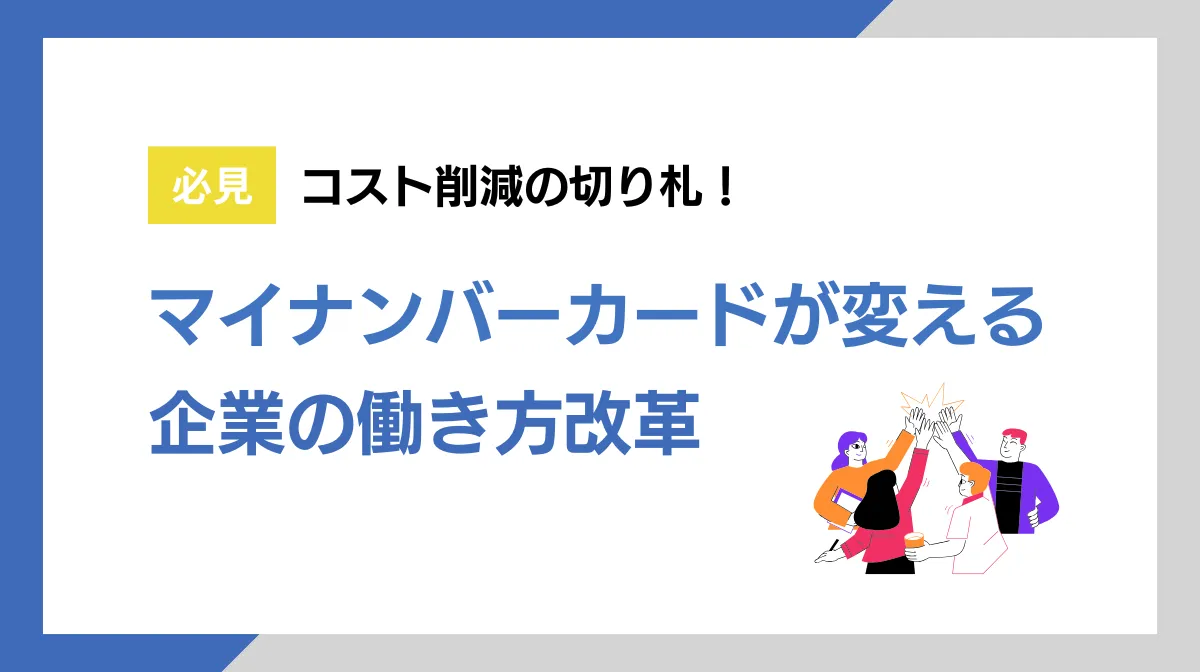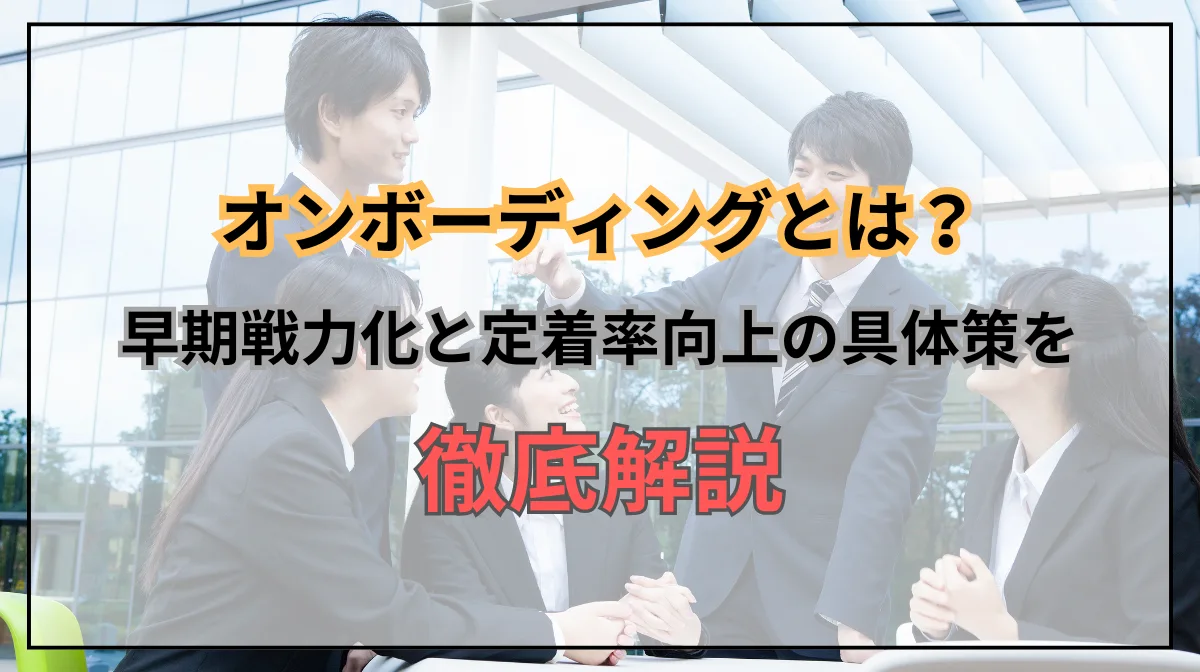マイナンバーカードは単なる身分証明書から企業成長を促進する戦略的ツールへと進化しています。
2024年12月から健康保険証の新規発行が停止され、完全にマイナンバーカードへの移行が進んでいる今、企業がこのカードを活用することで実現できる5つの業務効率化とコスト削減ポイントを解説します。
業務プロセスの革新を目指す経営者・総務担当者必見の内容です。
- マイナンバーカードの健康保険証機能と人事・給与システム連携による具体的な業務効率化手法
- 書類の電子化や本人確認プロセスの簡略化によるコスト削減の実例と投資回収期間
- マイナンバー情報の適切な管理体制構築と企業のDX推進におけるマイナンバーカード活用戦略
1.マイナンバーカードとは?企業担当者が押さえるべき基本情報
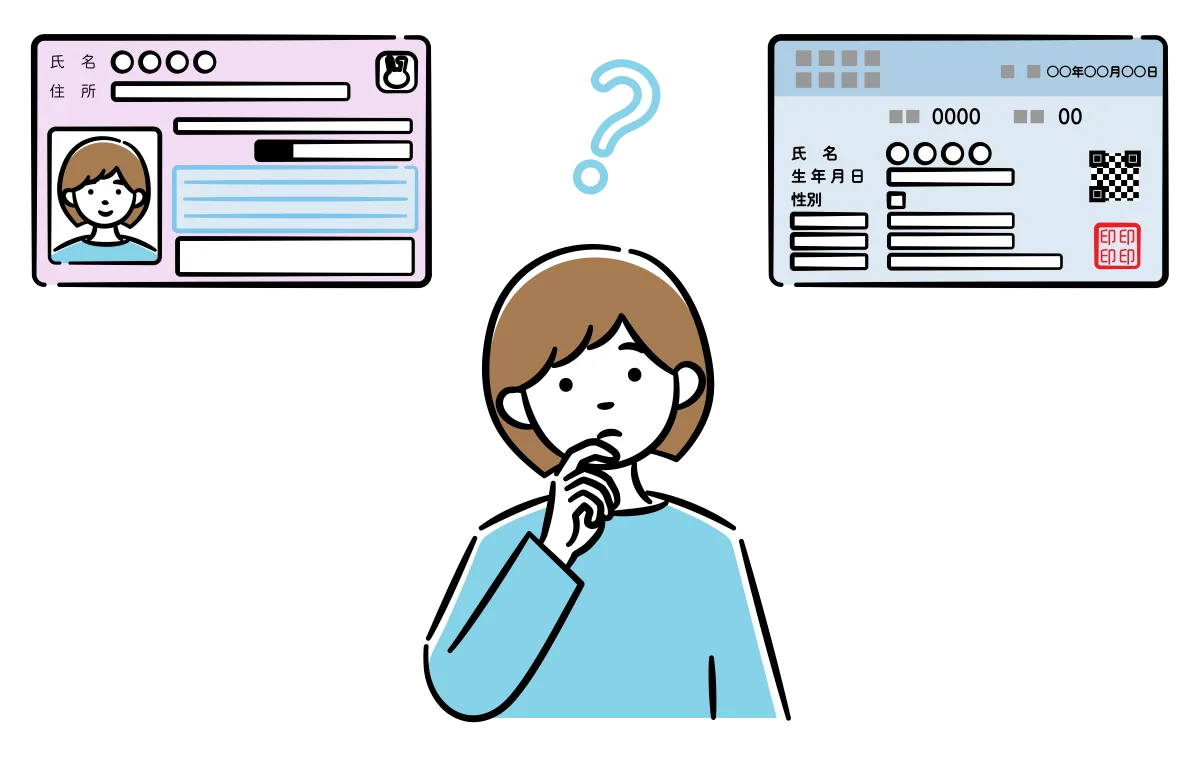
マイナンバーカードは企業の業務効率化において重要な役割を果たします。その基本情報と機能を理解することで、企業活動における活用可能性が広がります。
以下では、カードの概要から法的位置づけまで、企業担当者が押さえるべきポイントを解説します。
マイナンバーカードの概要と発行状況
マイナンバーカードは、平成28年(2016年)1月から交付が開始された、ICチップ付きのカードです。
国民一人ひとりに割り当てられた個人番号(マイナンバー)を証明する公的な身分証明書として機能します。交付手数料は無料で、申請者本人の申請により交付されます。
カードの記載内容
| 記載面 | 記載情報 |
|---|---|
| 表面 | 氏名・住所・生年月日・性別・顔写真 |
| 裏面 | 個人番号 |
2024年3月末時点で70%台の交付率が報告されており、政府はさらなる普及促進策を進めています。
企業担当者が特に注目すべき点
- 本人確認書類としての利用
- 電子証明書による電子申請
- 健康保険証としての利用
- 多様な行政サービスを受けるための基盤
デジタル社会の実現に向けて、企業活動においても活用範囲が拡大し、様々な業務プロセスでの活用が当たり前になってきています。
参考:総務省|マイナンバーカードの交付・保有枚数等について(令和6年3月末時点)
マイナンバーカードに搭載された主要機能
マイナンバーカードのICチップには、大きく分けて4つのアプリケーションが搭載されています。
| 券面アプリケーション | 表面情報(氏名・住所・生年月日・性別と顔写真)と裏面情報(個人番号)の画像データが記録されている |
| 公的個人認証サービスによる電子証明書アプリケーション | 署名用電子証明書(e-Taxの確定申告など電子文書を送信する際に利用可能)、利用者証明用電子証明書(マイナポータルやコンビニ交付の利用、本人であることを証明する際に使用)の情報が記録されている |
| 券面入力補助アプリケーション | 個人番号や4情報をテキストデータとして利用する際に活用される |
| 住民基本台帳アプリケーション | 住民票ネット接続の際に住民票コードをテキストデータとして利用するためのもの |
これらの機能は企業の人事・給与処理システムとの連携や、各種行政手続きの電子化、従業員の健康保険証としての利用など、多岐にわたるビジネスプロセスの効率化に寄与しています。
特に電子証明書機能は、企業の電子申請やオンライン手続きにおいて重要な役割を果たしており、2025年にはさらに機能拡充が予定されています。
企業における法的位置づけと対応の必要性
企業は、マイナンバー制度において重要な法的義務を負っています。まず、従業員やその扶養家族、報酬を支払う取引先などからマイナンバーを収集し、適切に管理する義務があります。
これは社会保険手続きや源泉徴収票作成、支払調書の提出など税務関連業務において必須です。
特に注意すべき点として、マイナンバーの取扱いには厳格な安全管理措置が法令で定められており、法令違反の場合は罰則も設けられています。
2025年現在、健康保険証としてのマイナンバーカード利用移行はほぼ完了し、従来の健康保険証は2024年12月以降発行されなくなりました。多くの企業では従業員のほぼ全員がマイナンバーカードを健康保険証として利用しています。
今後は、デジタル庁が推進するマイナンバーカードの機能拡充や利用シーンの多様化に対応するため、企業内のシステム整備や業務フローの最適化を継続的に行うことが必要です。
特に2025年後半から予定されている電子証明書の機能拡充や、スマートフォンとの連携強化に向けた準備が重要となっています。
【効率的なドライバー採用がしたいなら】
カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら
2.マイナンバーカードの健康保険証利用で実現する業務効率化①|従業員の医療費管理の簡素化

2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行が停止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する制度へと完全移行しました。
これにより企業は従業員の医療費管理に関する業務を大幅に簡素化できています。ここではその具体的な仕組みとメリットを解説します。
健康保険証としてのマイナンバーカード利用の仕組み
マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みは、2025年現在ではすでに一般的な医療受診の形となっています。
医療機関や薬局に設置された顔認証付きカードリーダーでの受付が標準化され、ほぼすべての医療機関で対応しています。従業員は医療機関受診時にマイナンバーカードを提示するだけで保険資格確認が完了します。
健康保険証としてのマイナンバーカードのメリット
- 企業側では健康保険証の発行・管理・回収業務が完全になくなり、業務負担が大幅に軽減されている
- 従業員の異動や扶養家族の変更時も、オンライン資格確認システムを通じてリアルタイムで情報が更新されるため、旧保険証の回収や新保険証の発行といった煩雑な手続きが不要となっている
さらに、医療機関側でのスムーズな受付により、従業員の診療待ち時間短縮や誤登録防止にも貢献しています。
2025年に入ってからは、特に緊急時の医療対応においてもマイナンバーカードの有用性が高まっており、救急搬送時の迅速な保険資格確認や既往症の把握が可能となり、より適切な医療提供につながっています。
医療費情報の一元管理によるメリット
マイナンバーカードの健康保険証利用による医療費情報の一元管理は、2025年現在、企業の福利厚生業務に大きな変革をもたらしています。
従業員はマイナポータルを通じて自身の医療費や薬剤情報を簡単に確認でき、医療費控除の申請も効率化されています。
企業側のメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
- 書類確認・集計作業の削減
・従業員の医療費領収書確認がほぼ不要に
・申請書類の集計作業の大幅効率化 - データ連携によるリスク低減
・手入力による転記ミスの防止
・不正請求リスクの大幅削減
多くの企業では従業員がマイナポータルからダウンロードした医療費データを企業の経費精算システムと連携させています。
また、社会保険料や健康保険組合の運営状況の可視化も進み、企業の健康保険料負担の予測精度が向上しています。
特に2025年に入ってからは、高額医療費の発生時に従業員がマイナポータルを通じて簡単に限度額適用認定証の電子申請を行えるようになり、企業側の事務手続き負担がさらに軽減されています。
多くの先進企業では、このようなデータ連携を活用して従業員の医療費負担を軽減する施策を展開し、従業員満足度の向上につなげています。
企業の健康経営推進におけるデータ活用法
マイナンバーカードの健康保険証利用から得られるデータ活用は、2025年現在、企業の健康経営の中核を担うようになっています。
マイナポータルを通じて取得できる匿名化された健康データ分析により、従業員の健康課題を客観的に把握し、効果的な健康増進施策を展開する企業が増加しています。
これにより、企業内の健康リスクを評価し、重点的に取り組むべき健康課題を特定することで、より効果的な施策展開が可能になっています。
主な活用データ
- 特定疾患の受診傾向
- 予防接種状況
- 健診受診率
- 生活習慣病リスク指標
また、健康経営銘柄や健康経営優良法人認定の取得企業が増加しており、これらの企業ではマイナンバーカードから得られる健康データを取り組みの効果測定や報告資料作成の基盤として活用しています。
データ活用の範囲も拡大しており、2025年には匿名加工された健康データを活用した企業間ベンチマークも一部で始まっています。
もちろん、健康データの活用には法的・倫理的な制限があることから、個人が特定されないよう匿名化処理を徹底し、利用目的を明確にした上で従業員からの同意取得プロセスを整備する企業が多数を占めています。
▼健康診断についてもっと詳しく
以下の記事は、人事担当者必見の健康診断実務について紹介しています。法的義務から結果管理まで、実務に必要な知識と方法を解説しています。産業医との連携や従業員対応の要点も網羅していますので、ぜひ参考にしてください。
3.マイナンバーカード活用による業務効率化②|人事・給与事務の簡素化

人事・給与事務は企業にとって重要かつ負担の大きい業務のひとつです。マイナンバーカードの活用により、これらの業務プロセスを大幅に効率化することが可能になっています。電子化による手続きの簡素化や業務負担の軽減など、具体的な活用方法を見ていきましょう。
マイナポータル連携による各種手続きの電子化
2025年現在、マイナポータルと企業の人事システムの連携は大幅に進化し、様々な行政手続きの電子化が実現しています。
特に社会保険・雇用保険の資格取得・喪失届や住所変更など、従業員のライフイベントに関連する手続きの電子申請が標準化されています。
電子申請による主なメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
●業務効率化
- 紙の書類作成が不要に
- 郵送・窓口提出のための移動時間削減
- 入社時の事務作業の削減(先進企業の事例)
この連携により、従来は紙の書類作成と郵送または窓口提出が必要だった手続きがオンラインで完結するため、書類作成の手間や提出のための移動時間が削減されています。
先進企業では、新入社員の入社手続きにおいて、マイナポータルを通じて健康保険・厚生年金保険の資格取得届や雇用保険の被保険者資格取得届をまとめて電子申請するワンストップサービスを導入しており、入社時の事務作業を削減している事例も報告されています。
また、従業員が引越しをした場合も、マイナンバーカードで本人確認を行った上で住所変更情報を電子的に取得し、関連する手続きを一括処理することが一般的になっています。
2025年に入ってからは、企業の人事システムとマイナポータルAPIの連携がさらに強化され、ほぼリアルタイムでのデータ連携が実現し、転記ミスや二重入力のリスクもほぼゼロになっています。
特に複数拠点を持つ企業や多くの従業員を抱える企業では、この電子化によって年間数百時間の業務時間削減が実現しています。
源泉徴収票等の電子的交付による業務負担軽減
マイナンバーカードを活用した電子証明書機能により、源泉徴収票や給与明細などの法定調書の電子的交付が2025年現在では一般的になっています。
これにより印刷・封入・配布といった一連の作業が不要となり、企業の年末調整業務の負担は大幅に軽減されています。
電子的交付の主なメリット
●業務効率化の実績
- 年末調整業務の工数 平均50%以上削減
- 従業員1,000名規模企業での効果
・業務時間 年間約100時間削減
・コスト 約30万円削減
電子的交付の法的要件としての従業員の事前同意取得や電子文書の真正性確保、改ざん防止措置などは、マイナンバーカードの電子証明書を利用することで容易に満たせるようになっています。
また、郵送費や印刷コストの削減、紛失リスクの低減といった副次的効果も顕著です。
2025年からは、マイナポータルと連携した給与所得の源泉徴収票データの自動連携も始まっており、従業員は確定申告時にマイナポータル経由で源泉徴収票データを自動取得できるようになりました。
これにより、企業側の源泉徴収票再発行業務も大幅に減少しています。電子的交付システムの導入・運用コストも低減し、中小企業でも容易に導入できるクラウドサービスが普及しています。
社会保険手続きのペーパーレス化の実現方法
2025年現在、社会保険関連の手続きのペーパーレス化は大幅に進展しています。
e-Gov等の電子申請システムとマイナンバーカードの連携により、健康保険・厚生年金保険の資格取得届や喪失届、算定基礎届、月額変更届などの手続きをオンラインで提出することが標準的な方法となっています。
多くの企業では、人事・総務担当者がマイナンバーカードを活用した電子申請を行い、紙の書類作成や郵送、窓口提出の手間がほぼなくなっています。
特に中堅・大企業では、API連携に対応した人事システムの導入が進み、社内システムからe-Govへのデータ連携が自動化されています。
手続きごとの電子化も進展し、頻度の高い資格取得・喪失届だけでなく、算定基礎届や月額変更届、賞与支払届など、ほぼすべての社会保険関連手続きが電子化されています。
2025年に入ってからは、マイナンバーカードの電子証明書を活用した「ワンクリック申請」機能も導入され、事前に登録したテンプレートを使って、より簡単に申請できるようになっています。

電子申請の完全導入により、企業は年間で社会保険関連手続きの工数を最大80%削減できたという事例も多く報告されています。
社会保険労務士事務所でも電子申請サービスが標準となり、企業とのデータ連携もスムーズに行われるようになっています。
4.マイナンバーカード導入がもたらすコスト削減③|書類作成・保管コストの削減
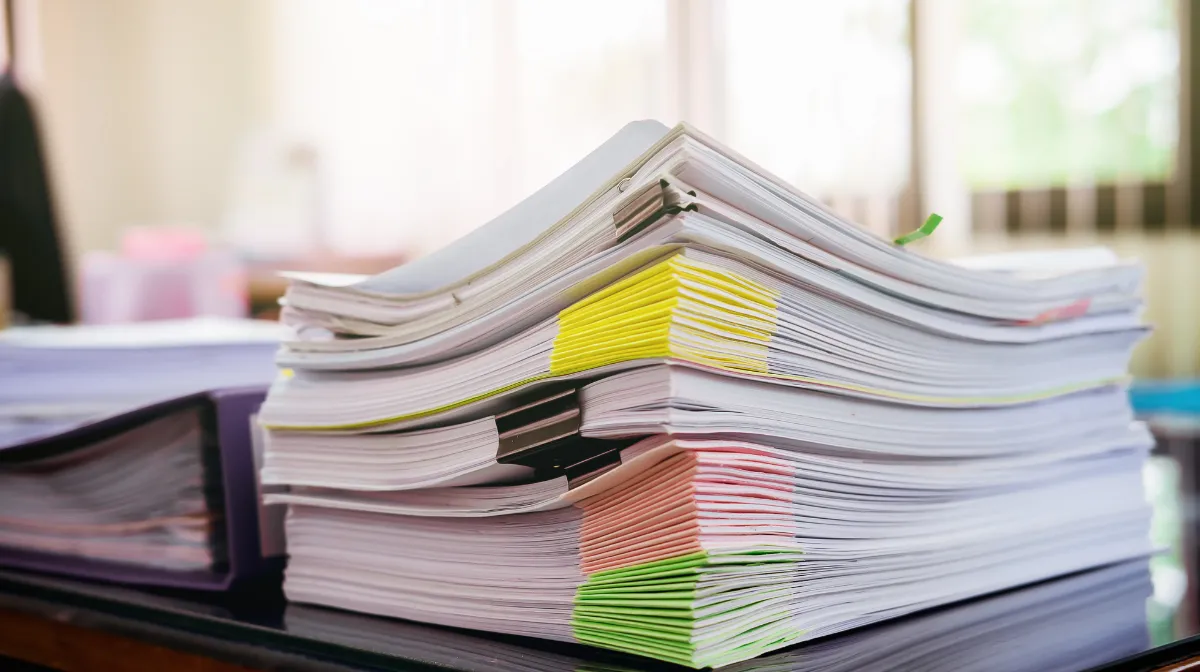
企業活動では膨大な書類の作成・管理が必要となり、その保管コストは決して小さくありません。マイナンバーカードの導入により、書類の電子化や本人確認プロセスの効率化が進み、これらのコストを大幅に削減できています。ここではその具体的な方法とメリットを解説します。
電子証明書を活用した本人確認プロセスの効率化
マイナンバーカードに搭載された電子証明書は、2025年現在、オンライン上での本人確認の標準的な手段となっています。
従来の対面による本人確認では、身分証明書の提示や複数書類の照合、写しの保管などが必要でしたが、電子証明書を活用することでこれらのプロセスがデジタル化され、大幅な効率化が実現しています。
●具体的な活用シーン
- 新入社員のオンボーディング
- 内部システムへのアクセス認証
- 契約書の電子署名
例えば、新入社員100名の入社手続きでは、従来の対面確認方式と比較して、電子証明書を活用したオンライン本人確認により、一人あたり約30分の時間短縮が実現し、企業全体で約50時間の工数削減になるという成果が報告されています。
また、本人確認書類のコピーや保管が不要になったことで、紙のコスト削減と情報漏洩リスクの低減も同時に実現しています。
2025年には、マイナンバーカードの電子証明書を活用した「トラストサービス」の普及も進み、より高度な本人確認や契約の電子化が可能になっています。
さらに、リモートワークの定着に伴い、場所を問わない本人確認手段としてのマイナンバーカード活用も増加しており、特にセキュリティレベルの高い業務においても、電子証明書を活用した本人確認により安全かつ効率的な業務遂行が可能になっています。
▼オンボーンディングについて詳しく解説
以下の記事では、オンボーディングの基礎から実践まで、人材育成のノウハウを解説しています。具体的な導入事例と成功のポイントをわかりやすく紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
紙文書の電子化による保管スペース・コストの削減
2025年現在、企業における紙文書の電子化は急速に進展し、保管スペースの有効活用とコスト削減を実現しています。
マイナンバーカードの電子証明書を活用することで、電子化された文書の真正性を担保しつつ、法的要件を満たした文書管理が一般的になっています。
●電子化される主な書類
- 雇用契約書
- 各種申請書
- 源泉徴収票
- 健康保険・年金関連書類
- 取引契約書 など
電子化される書類は多岐にわたり、大企業では90%以上、中小企業でも70%以上の文書が電子化されています。
e-文書法や電子帳簿保存法の要件対応も、マイナンバーカードの電子証明書活用により容易になっており、特に2025年の法改正により要件が簡素化されたことで、より多くの企業が電子化に踏み切っています。
保管コスト削減の具体例として、従業員500名規模の企業では、人事関連書類の電子化により年間約150万円の保管コスト削減と約20平方メートルのオフィススペース削減を実現した事例が多く報告されています。
また、テレワークの定着に伴い、場所を問わず必要な文書にアクセスできる環境の構築が進み、業務効率の向上にもつながっています。
電子文書管理システムの導入コストも低減し、クラウドサービスの普及により中小企業でも手軽に導入できるようになっています。
さらに、AIを活用した文書の自動分類や検索機能の向上により、電子化のメリットはさらに拡大しています。
情報セキュリティ対策コストの最適化
マイナンバーカードのセキュリティ機能を活用した情報セキュリティ対策は、2025年現在、企業のセキュリティコスト最適化に大きく貢献しています。
マイナンバーカードのICチップの「耐タンパー性」や国際規格ISO/IEC15408認証取得といった高度なセキュリティ機能を企業の認証システムに活用することで、従来のセキュリティ対策よりも高いセキュリティレベルを低コストで実現する企業が増加しています。
これにより、パスワード管理コストやセキュリティトークンの発行・管理コストが大幅に削減されています。
情報漏洩リスク低減の経済効果も顕著で、マイナンバーカードを活用したセキュリティ強化により、情報漏洩対応コストの潜在的リスクを大幅に低減している企業が増加しています。
また、2025年に入ってからは、マイナンバーカードを活用した「ゼロトラストセキュリティ」の導入も進んでおり、リモートワーク環境でも安全なアクセス制御が可能になっています。
さらに、多要素認証やシングルサインオン環境の構築により、従業員一人あたり年間約3万円のIT管理コスト削減を実現した企業も多数報告されています。
セキュリティ対策の効率化により、企業は限られたセキュリティ予算をより重要な領域に集中投資できるようになり、全体的なセキュリティレベルの向上にもつながっています。
【効率的なドライバー採用がしたいなら】
カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら
5.企業の法令遵守体制強化④|マイナンバー管理の適正化
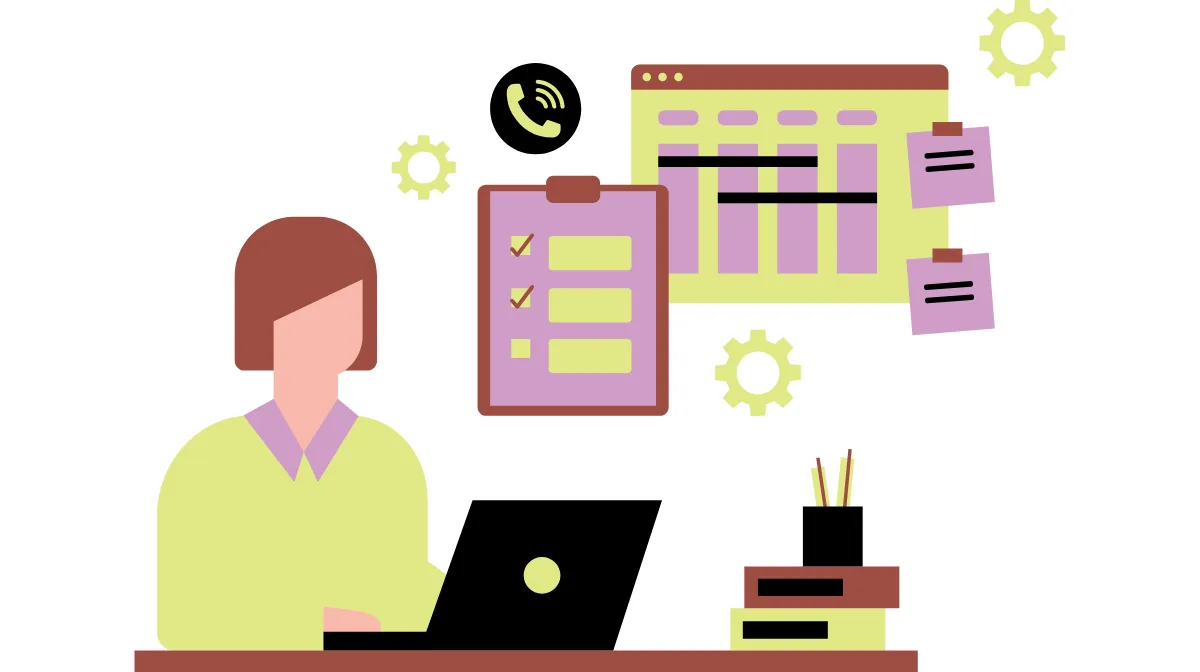
マイナンバー制度への対応は企業にとって法的義務であり、適切な管理体制の構築が求められています。マイナンバーカードの活用により、情報管理の効率化と法令遵守体制の強化を同時に実現できています。
以下では、具体的な管理体制の構築方法からセキュリティ対策まで詳しく解説します。
マイナンバー情報の適切な管理体制の構築方法
2025年現在、マイナンバー情報の適切な管理体制構築は、ほとんどの企業で実現しています。
マイナンバーの取扱責任者と事務取扱担当者を明確に指定し、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」と「特定個人情報等取扱規程」を策定・運用することが標準的な対応となっています。
多くの企業では、マイナンバー管理システムの導入が進み、アクセス権限の厳格な管理と操作ログの自動記録・保管が実現しています。
また、定期的な内部監査とリスク評価の実施も一般化し、PDCAサイクルによる継続的な改善が行われています。
2025年の法改正により、マイナンバー情報の管理要件が一部明確化されたことで、より効率的かつ確実な管理体制の構築が可能になりました。
特に注目されているのは、マイナンバーカードの電子証明書を活用した「特定個人情報閲覧ログ管理システム」で、誰がいつどのマイナンバー情報にアクセスしたかを厳格に管理できるようになっています。
また、クラウドサービスの普及により、中小企業でも安全かつ効率的なマイナンバー管理が可能になっており、マイナンバー情報の取扱いに関するリスクが大幅に低減しています。
さらに、従業員のマイナンバー情報管理に関する意識も向上し、社内研修の実施率も高まっています。
情報漏洩リスクへの対応とセキュリティ対策
マイナンバー情報の漏洩リスクへの対応は、2025年現在、より高度化・効率化されています。
マイナンバーカード自体のセキュリティ対策に加え、企業内でのマイナンバー情報管理においても、システムによる自動化と厳格な管理が標準となっています。
- 物理的なセキュリティ
マイナンバーが記載された書類の電子化と原本の安全な廃棄が進み、紙媒体での管理リスクが大幅に低減 - 技術的なセキュリティ
マイナンバー情報を含むデータの自動暗号化や、アクセス権限の多層化、AIを活用した異常検知システムの導入など
特に2025年に普及したのは、マイナンバーカードの電子証明書を活用した「特定個人情報アクセス認証システム」で、マイナンバー情報へのアクセスに二要素認証を必須とする仕組みが多くの企業で導入されています。
また、マイナンバー情報の取扱いを最小限の担当者に限定する「Need to Know原則」の徹底も進み、アクセス権限の定期的な見直しと剥奪が自動化されています。
さらに、インシデント対応訓練の実施も一般化し、万が一の情報漏洩時の対応手順が明確化されています。
2025年には、マイナンバー情報の漏洩事案が前年比で約40%減少したというデータもあり、企業のセキュリティ対策の成果が表れています。
特に、マイナンバーカードの普及により、従業員自身のセキュリティ意識も向上し、企業全体のセキュリティレベル向上にも寄与しています。
マイナンバーカードを活用した個人情報保護体制の強化
マイナンバーカードを活用した個人情報保護体制の強化は、2025年現在、企業のコンプライアンス戦略の中核を担っています。
個人情報保護法の改正に伴い、企業に求められる個人データの管理レベルは高まっていますが、マイナンバーカードの電子証明書機能を活用することで、効率的かつ確実な本人確認が実現しています。
多くの企業では、従業員や顧客の個人情報に関する開示請求や訂正請求の際に、マイナンバーカードによる電子署名認証を導入し、なりすましリスクを大幅に低減しています。
また、企業内の個人情報データベースへのアクセス権限管理にマイナンバーカードの多要素認証を活用する事例も増加しており、不正アクセスのリスク低減と操作ログの信頼性向上が実現しています。
2025年に導入された個人情報の越境移転規制強化にも、マイナンバーカードの電子証明書を活用した本人同意の取得・記録システムが対応しており、国際的なデータ流通においても法令遵守が確保されています。
さらに、個人情報取扱規程や従業員教育プログラムもマイナンバーカードの仕組みに合わせて最適化され、組織全体の個人情報保護意識は大きく向上しています。
このように、マイナンバーカードを活用した本人確認強化は、法令遵守体制の強化だけでなく、企業全体の情報ガバナンス向上と業務効率化という相乗効果をもたらしています。
6.未来を見据えた戦略⑤|マイナンバーカードを活用したDX推進

マイナンバーカードは2025年現在、デジタル社会の重要なインフラとして定着しています。企業のDX戦略においても、このカードを戦略的に活用することで、業務効率化やコスト削減にとどまらない新たな価値創造が実現しています。ここでは、現在の展開状況と今後の展望について解説します。
マイナンバーカードの今後の展開予測と企業戦略
2025年4月現在、マイナンバーカードはデジタル社会の基盤として完全に定着し、70%以上の普及率を達成しています。政府のデジタル戦略においても「デジタル社会の入口」として多様なサービスとの連携が加速しています。
現在の主な機能としては、健康保険証としての完全移行が完了し、行政手続きのオンライン化が大幅に進展したほか、民間サービスとの連携も拡大しています。
先進企業の多くは、すでに人事・給与システムとマイナポータルの連携を完了し、電子契約の標準化やバックオフィス業務の自動化を実現しています。
今後2年間の重点課題としては、顧客サービスとの連携強化やデータ連携基盤の整備が挙げられます。
特に注目されているのは、マイナンバーカードを活用した「デジタルID基盤」の構築で、企業の認証システムとの統合により、セキュリティ強化とユーザー体験向上の両立が期待されています。
また、地方自治体のデジタル化推進に合わせ、地域に根ざした企業では行政サービスとの連携による新たなビジネスモデルの創出も検討されています。
企業の規模や業種を問わず、マイナンバーカードを活用したDX推進は、今後の競争力を左右する重要な経営課題となっています。
デジタル庁が推進する各種施策との連携方法
2025年現在、デジタル庁が推進する「デジタル社会の実現に向けた重点計画」は着実に進展しており、マイナンバーカードを活用した様々な施策が本格的に運用されています。
多くの企業では、マイナポータルAPIを活用して人事・給与システムと行政手続きを直接連携させ、従業員の各種申請をシームレスに処理できる環境を構築しています。
また、「法人共通認証基盤」の活用も一般化し、法人として行政機関に提出する電子申請の認証プロセスが大幅に効率化されています。
2025年から新たに導入された施策としては、「デジタル社会推進給付金」制度があり、マイナンバーカードを活用したDX推進に積極的に取り組む中小企業向けの支援が強化されています。
また、「マイナンバーカード活用民間サービス認証制度」も創設され、安全性と利便性が確認されたサービスには公的な認証マークが付与されるようになりました。
これにより、企業が提供するマイナンバーカード連携サービスへの消費者の信頼も向上しています。
企業が活用できる支援制度も拡充され、「デジタル化推進税制」の適用範囲拡大や「DX投資促進補助金」の予算増額など、マイナンバーカード関連システムの導入に対する支援が強化されています。
これらの施策を最大限に活用するためには、デジタル庁の情報発信チャネルを定期的にチェックし、早期の対応を検討することが重要です。
マイナンバーカードを活用した新しいビジネスモデルの可能性
2025年現在、マイナンバーカードを活用した新しいビジネスモデルは多くの業界で創出されています。
金融業界
マイナンバーカードの電子証明書を活用したオンライン完結型の口座開設・ローン申込サービスが一般化し、審査時間の大幅短縮と本人確認コストの削減を実現している
小売業
マイナンバーカードを活用した年齢確認システムが普及し、医薬品や成人向け商品の販売プロセスが効率化されるとともに、不正購入のリスクも低減されている
シェアリングエコノミー分野
マイナンバーカード認証による利用者の本人確認強化が信頼性向上につながり、市場規模の拡大を後押ししている
製造業
従業員の資格情報とマイナンバーカードを連携させた現場作業の適格者管理システムが導入され、安全管理と業務効率の両立が図られている
医療・介護業界
マイナンバーカードと連携した患者情報システムにより、医療機関間での情報共有が円滑化し、医療の質向上と業務効率化が実現している
教育分野
学習履歴のデジタル管理と最適な学習コンテンツの提供など、個別最適化された教育サービスが広がりつつある
これらの新しいビジネスモデルを成功させるためには、自社の強みとマイナンバーカードの機能を組み合わせた独自の価値提案が重要です。
特に、スタートアップとの協業やオープンイノベーションの手法を活用することで、革新的なサービス創出の可能性が広がっています。
マイナンバーカードの機能拡充が続く中、今後も新たなビジネスチャンスが生まれ続けると予測されています。
7.企業におけるマイナンバーカード普及促進の具体策

2025年現在、マイナンバーカードの普及率は70%を超えていますが、新入社員や外国人従業員など、まだ取得していない従業員への対応や、カードの有効活用を促進するための施策は引き続き重要です。企業として継続的にマイナンバーカードの活用を推進するための効果的な方法を紹介します。
従業員向けマイナンバーカード取得促進キャンペーンの実施方法
2025年現在、マイナンバーカード取得率は全国的に70%を超えていますが、新入社員や外国人労働者などを中心に未取得者も存在しています。
効果的な取得促進キャンペーンとしては、入社オリエンテーションにマイナンバーカード申請サポートを組み込む企業が増加しています。
具体的には、人事部門が主導して、申請に必要な書類の準備から写真撮影、オンライン申請までをワンストップでサポートする体制を整えています。
特に外国人従業員向けには、多言語対応の申請サポート資料を用意し、在留カードとマイナンバーカードの関係や利用メリットをわかりやすく説明する取り組みが効果を上げています。
また、健康保険証としての利用がすでに標準となっている現在では、「医療機関での受診にはマイナンバーカードが必須」という点を強調する説明が特に有効です。
取得促進と併せて重要なのが、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限管理です。
2025年は初期に発行されたカードの電子証明書更新時期にあたるため、多くの企業では電子証明書の有効期限管理システムを導入し、更新時期が近づいた従業員への通知と更新サポートを行っています。
これらの取り組みにより、ほとんどの企業ではマイナンバーカードの取得が進み、健康保険証としての利用や各種電子申請の完全導入が実現しています。
取得促進と有効活用を組み合わせたアプローチが、マイナンバーカードの企業内での定着に大きく貢献しています。
社内制度とマイナンバーカード活用の連携事例
2025年現在、マイナンバーカードと社内制度の連携は多くの企業で実現し、業務効率化と従業員体験の向上につながっています。福利厚生制度との連携では、マイナポータルと連動した健康経営ポイント制度が一般化しています。
福利厚生制度との主な連携事例
- 健康経営ポイント制度
・健診データや予防接種記録に基づくポイント付与
・福利厚生サービスや報奨金への交換 - 医療費自己負担分補助の自動化
・手続き不要の補助金受給
・申請業務の効率化
従業員はマイナポータルで確認できる健診データや予防接種記録に基づいてポイントを獲得し、福利厚生サービスや報奨金に交換できる仕組みが浸透しています。
また、医療費の自己負担分補助制度もマイナポータルとの連携により自動化され、従業員は手続きなしで補助を受けられるようになっています。
社内システムとの統合も進展し、マイナンバーカードを活用した社内認証基盤の構築が一般化しています。
具体的には、勤怠管理システムとの連携による出退勤記録の自動化や、社内文書管理システムとの連携による電子署名の標準化などが定着しています。
特に先進的な企業では、マイナンバーカードの認証機能とAIを組み合わせた「スマートオフィス」環境を実現し、従業員一人ひとりの働き方に合わせたオフィス環境の自動最適化を実現しています。
テレワーク環境でのセキュアなアクセス認証にもマイナンバーカードの電子証明書が広く活用されており、場所を問わない安全な業務環境が確立されています。
これらの連携により、従業員はマイナンバーカードの利便性を実感し、企業は業務プロセスの効率化と正確性向上を同時に実現するという好循環が生まれています。
さらに、こうした取り組みがESG評価の向上にもつながっているという報告も増加しています。
マイナンバーカード取得・活用に関する従業員教育の進め方
2025年現在、マイナンバーカードの取得はほぼ完了していますが、その機能を最大限に活用するための従業員教育はますます重要になっています。
多くの企業では、従業員のマイナンバーカード活用スキルに応じた段階的な教育プログラムを構築しています。
- 基礎レベル
マイナポータルへのログイン方法や健康保険証としての利用設定など、基本機能の活用方法を学ぶ - 中級レベル
各種電子申請の方法や電子証明書の活用法など、より高度な機能の使い方を習得する - 上級レベル
APIを活用したシステム連携や電子契約への応用など、業務プロセス改善につながる活用方法を学ぶ
教育実施のアプローチとしては、オンデマンド型の動画教材とライブセッションを組み合わせたハイブリッド形式が一般的になっています。
特に効果を上げているのは、各部門に「マイナンバーカード活用推進リーダー」を設置し、部門の特性に合わせた活用方法を開発・共有する取り組みです。
教育ツールとしては、インタラクティブな操作シミュレーションや、ゲーミフィケーションを取り入れたe-ラーニングが高い効果を上げています。
また、マイナンバーカードの機能拡充に合わせて、四半期ごとに「アップデートセミナー」を開催する企業も増えています。
教育効果の測定では、マイナポータルの利用頻度や電子申請の活用率などの定量指標と、利用者満足度調査などの定性指標を組み合わせた総合的な評価が行われています。
これらの取り組みにより、従業員のデジタルリテラシー向上と業務効率化の両立が実現しています。
【効率的なドライバー採用がしたいなら】
カラフルエージェント ドライバーにお任せください。即日でお近くのマッチした転職希望のドライバーをご紹介します。面接調整、条件交渉なども代行するため、簡単に採用活動ができます。▼カラフルエージェント ドライバーへのお問い合わせはこちら
8.マイナンバーカード導入・活用に関するよくある質問と回答
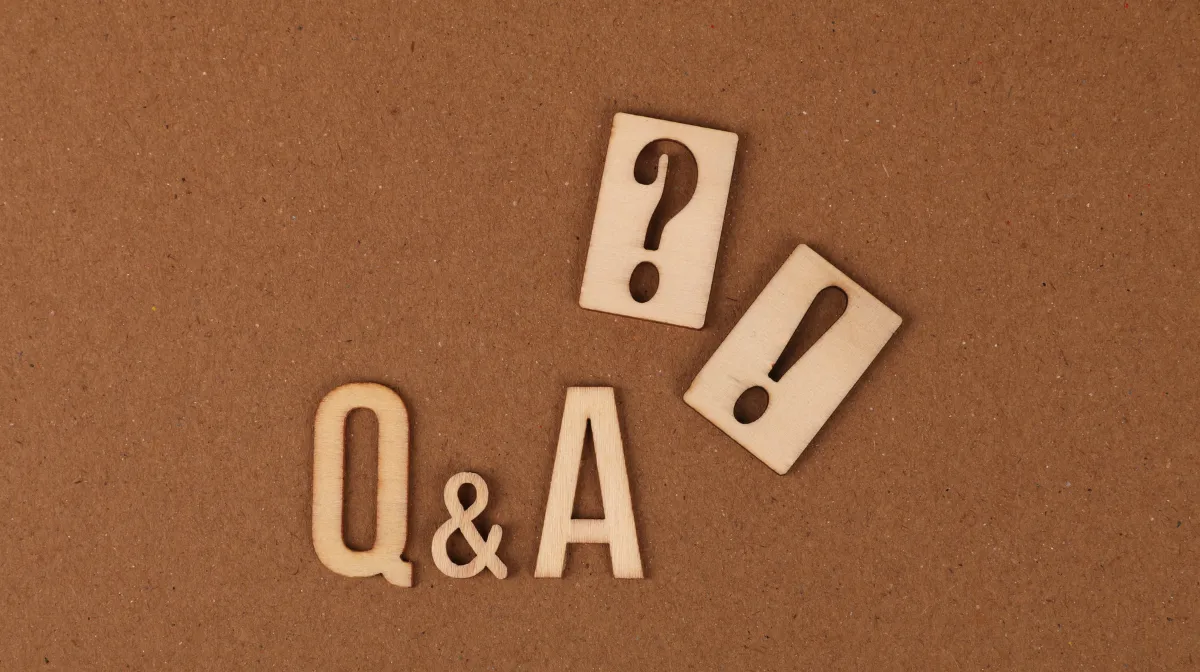
2025年現在でも、マイナンバーカードの導入・活用に関して企業担当者から様々な質問が寄せられています。ここでは、特に多い質問について、最新の動向を踏まえた回答を提供します。
マイナンバーカードの安全性に関する懸念への回答
-
マイナンバーカードのセキュリティ対策はどうなっていますか?
-
2025年現在、マイナンバーカードは「耐タンパー性」機能と「アプリケーションファイアウォール」による情報分離で高度に保護されています。ISO/IEC15408認証により国際水準のセキュリティが確認され、過去5年間で情報漏洩事案はありません。
紛失時には24時間対応コールセンターに加え、スマホアプリでの即時停止機能も利用可能です。2024年末の不正アクセス事案後は生体認証による多要素認証が強化されています。
2025年現在、マイナンバーカードのセキュリティ技術はさらに進化し、その安全性は実績を伴って証明されています。
ICチップの技術的なセキュリティ対策として、「耐タンパー性」機能はさらに強化され、物理的な攻撃に対する防御力が向上しています。また、「アプリケーションファイアウォール」による情報の分離管理も高度化され、各機能間でのデータ流出リスクは最小化されています。
2024年に更新されたISO/IEC15408認証では、より厳格な評価基準が適用され、国際的にも最高水準のセキュリティレベルであることが再確認されています。過去5年間の運用実績においても、ICチップからの情報漏洩事案は報告されておらず、技術的な安全性は実証されています。
マイナンバーカードの紛失・盗難時のリスク対策も強化され、24時間365日対応のコールセンターでの一時利用停止に加え、2025年からはスマートフォンアプリでの即時停止機能も導入されました。
このため、カード紛失による不正利用のリスクは大幅に低減しています。
また、2024年末に発生した一部の不正アクセス事案を受けて、セキュリティ対策の緊急強化が行われ、特に生体認証との組み合わせによる多要素認証が標準化されました。これにより、不正アクセスの可能性はさらに低減しています。

企業における安全な活用のポイントとしては、ICカードリーダーなどの周辺機器のセキュリティアップデートの定期的な実施や、従業員への継続的なセキュリティ教育が挙げられます。
また、マイナンバーカードのセキュリティ機能を活用した企業内認証基盤の構築により、既存の社内システムのセキュリティレベル向上にも貢献しています。
導入コストと投資対効果の考え方
-
マイナンバーカード活用システムの導入コストと投資対効果はどうなっていますか?
-
2025年現在、導入コストは大幅に低下しています。ICカードリーダーは1台3,000〜10,000円、マイナポータル連携もクラウド月額制で利用可能です。
投資効果は明確で、健康保険証移行後は年間300時間(約150万円相当)の工数削減、紙の書類削減で年間約100万円の直接コスト削減が実現しています。
投資回収期間は中堅企業で平均1.5〜2年、2025年度の「マイナンバーカード活用推進特別措置」では中小企業の導入コスト負担が最大70%軽減されています。
2025年現在、マイナンバーカード活用システムの導入コストは大幅に低減し、投資対効果も明確になってきています。一方で運用コストも最適化され、システムの保守・運用がAIによる自動化で効率化されています。
導入・運用コストの現状
●初期導入コスト
- ICカードリーダー:
1台 約3,000〜10,000円 - マイナポータル連携:
クラウドサービス(月額制)
●運用の効率化
- AI活用による保守・運用の自動化
- クラウドサービスによる管理負担軽減
これらの投資に対するリターンは、多くの企業で明確に測定されるようになり、特に健康保険証としての利用完全移行後は、保険証関連業務の効率化だけでも年間約300時間の工数削減を実現した事例が報告されています。
これを人件費に換算すると年間約150万円のコスト削減となり、5年間の累積効果は750万円に達します。
また、紙の書類削減による直接コスト(印刷費、郵送費等)の削減効果も年間100万円程度と試算されており、間接的な効果も含めるとさらに大きな経済効果が見込まれます。
投資回収期間は企業規模や活用範囲により異なりますが、中堅企業の場合、平均で1.5〜2年程度まで短縮されています。
投資対効果を最大化するポイントとしては、複数業務での活用によるシナジー効果の創出がより重要になっており、人事・総務・経理・情報システムなど部門横断的な活用計画の策定が効果的です。
また、政府のDX推進補助金や税制優遇措置も拡充されており、特に2025年度は「マイナンバーカード活用推進特別措置」により、中小企業の導入コスト負担が最大70%軽減されています。
これらの支援策を活用することで、導入ハードルはさらに低くなっています。
法令遵守における注意点と対応策
-
マイナンバー情報の取扱いに関する法令遵守のポイントは何ですか?
-
2025年現在、マイナンバー情報管理における法令遵守のポイントは
- 2024年改正番号法により利用目的の限定が厳格化され目的外利用の罰則が強化されている
- 電子証明書を活用した本人確認手続きが対面確認と同等の法的効力を持つことが明文化された
- 2025年個人情報保護法改正でマイナンバーカードによる本人確認が「適正な取得」基準として明確化された
企業の対応策としては、取扱規程の定期更新、アクセス権限管理の強化、AIを活用した不正検知システムの導入、オンライン研修と理解度テストの実施などが効果的です。
2025年現在、マイナンバーカード活用における法令遵守の重要性はさらに高まっています。2024年の改正番号法施行により、マイナンバー情報の取扱いに関する規定が一部見直され、より明確な管理基準が示されました。
特に注意すべき点として、マイナンバーの利用目的の限定はより厳格化され、目的外利用に対する罰則も強化されています。
2025年の個人情報保護法改正では、マイナンバーカードを活用した本人確認・同意取得のプロセスが「適正な取得」の基準として明確化され、特に越境データ移転における本人同意の取得・記録方法としてマイナンバーカードの電子署名が推奨されています。
企業における対応策としては、まず最新の法令動向を把握し、社内のマイナンバー取扱規程を定期的に更新することが重要です。
特に2025年の法改正に対応するため、多くの企業ではコンプライアンス部門と情報システム部門が連携し、マイナンバー情報管理システムのアップデートを進めています。
また、マイナンバー情報へのアクセス権限管理と操作ログの記録・保管体制も強化されており、AIを活用した不正アクセス検知システムの導入も進んでいます。
コンプライアンス体制構築の新しいポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。
- マイナンバー取扱いに関する社内研修のオンライン化と定期的な理解度テストの実施
- 内部監査と外部監査の組み合わせによる多層的なチェック体制の構築
これらの取り組みにより、法令遵守を確保しつつ、マイナンバーカードのメリットを最大限に活用できる体制が整ってきています。
9.マイナンバーカードでデジタル変革を加速する
マイナンバーカードは2025年現在、企業のデジタルトランスフォーメーションにおける重要な基盤として定着しています。
健康保険証利用の完全移行、人事・給与手続きの電子化、書類保管コストの削減、法令遵守体制の強化、そしてDX推進基盤としての活用—これら5つのポイントはどれも企業競争力の強化に直結します。
初期投資の回収期間も短縮され、導入メリットが明確になってきた今こそ、積極的な活用を検討すべき時期です。
電子証明書更新管理の仕組み構築、マイナポータルとの連携強化、部門横断的なデジタル化計画の策定に取り組むことで、貴社の業務効率化とコスト削減を実現しましょう。
マイナンバーカードは今後も機能拡充が続く見込みであり、単なる対応コストではなく、ビジネス変革のための戦略的投資として捉えることが重要です。